2017年09月30日
伊佐山紫文75
現代日本では「詩」は死滅したという話があって、まあ、それはその通りだと思うのだけれど、それじゃあ、現代以前の日本に「詩」が生き生きと息づいていたのかと言えば、それもまた疑問だと思う。
そもとも日本語にとって「詩」とはなんだ。
韻文という意味でとらえるなら俳句や短歌も「詩」だろうから、死滅どころか、結社だのカルセンだのでますます盛ん、ご同慶の至りである。
息子の通う小学校でも俳人とやらのご指導のもと、全校生徒が俳句を詠んでいる。
死滅どころか、日本は詩の咲き誇る国だと言わざるを得ない。
いやいや、それでも、俳句や短歌とは違う「詩」というものがあるような気がする。
あっていいような気がする。
あるべきだという気がする。
あくまでも、そういう気がするという話だけれど。
と言うか、そういう気がするという、「その気」が実は大事なんであって、この「その気」が日本の近代詩を産んだと言っても過言ではない。
「その気」、つまり日本近代の精神は『徳川時代の鎖国によって日本が世界から取り残された』という明治維新のセントラル・ドグマから出発する。
遅れた日本がいかにして西洋に追いつくか。
それは科学技術だけの話ではない。
文化の面でも西洋に追いつかなければならない。
たとえば日本にはないAという文化が西洋にあるとすれば、それは日本の遅れなのだから、早急に同じものを作らなければならない。
それがたとえ、西洋のAに見劣りするaであったとしても、ないよりはマシだ。
日本にある幼稚なzも、西洋のZに近づけるべく改良していかなければならない。
場合によっては西洋のものに置き換えなければならない。
明治時代、こういう運動が文化の各分野で澎湃としてわき上がる。
すなわち、あっていいような気がする、あるべきだという気がする、なければ作ろう、の運動を日本国全体で繰り広げたというわけだ。
その先鞭を付けたのが演劇で、当時は演劇改良運動などと呼ばれ、歌舞伎の近代化、つまりは舞台の西洋化を目指した。
音楽も西洋音楽がスタンダードとされた。
小説も言文一致が目標とされ、名作なのか駄作なのかよく分からないものが量産された。
それまで詩と言えば漢詩だったのが、明治になると新体詩なるものが生まれ、これが「短歌」に対する形で「長詩」と呼ばれるうち、ただの「詩」になった。
現代日本の詩は、翻訳も含め、すべてこの新体詩に源流を持つ。
ただし、と改めて但し書きをつけるまでもなく、あらゆるジャンルでそうなのだろうが、新体詩に名作は少なく、ほとんどがゴミである。
考えてみれば当たり前で、最初に新体詩を試みたのは詩人でも何でもない、ただの語学者にすぎないのだから。
もちろん、その中から島崎藤村という素晴らしい詩人が出たのだから、新体詩運動も無意味ではなかったのだろう。
新体詩運動がなければ島崎藤村は出なかったし、現代日本の詩そのものが成立していない。
だとすれば、もし現代日本で詩が死滅しているとするなら、その死の種は、新体詩の中にすでに胚胎されていたのではなかったか。
比べるに、たとえばリルケの『ドゥイノの悲歌』から神を除いたら何が残るだろう。
ただの「言葉、言葉、言葉」(ハムレット)であって詩ではない何か。
ポエジーの源泉が失われてしまうだろう。
西洋の詩にあり、新体詩になかったもの。
それは神である。
詩は神と共にあり、神へと至る、あるいは遠ざかる道なのである。
西洋の詩人は意識するとしないとに関わらず、あるいはその存在を肯定すると否定するとに関わらず、皆、神と共にある。
すなわち詩は、信仰の告白であり、あるいは信仰の否定である。
ポエジーは神との関係性によって生み出されるのだ。
よって、神と共にない詩はポエジーを失い、詩たり得ず、滅ぶほかはない。
これが現代日本で詩が死滅した根本原因だと、私は思っている。
そもとも日本語にとって「詩」とはなんだ。
韻文という意味でとらえるなら俳句や短歌も「詩」だろうから、死滅どころか、結社だのカルセンだのでますます盛ん、ご同慶の至りである。
息子の通う小学校でも俳人とやらのご指導のもと、全校生徒が俳句を詠んでいる。
死滅どころか、日本は詩の咲き誇る国だと言わざるを得ない。
いやいや、それでも、俳句や短歌とは違う「詩」というものがあるような気がする。
あっていいような気がする。
あるべきだという気がする。
あくまでも、そういう気がするという話だけれど。
と言うか、そういう気がするという、「その気」が実は大事なんであって、この「その気」が日本の近代詩を産んだと言っても過言ではない。
「その気」、つまり日本近代の精神は『徳川時代の鎖国によって日本が世界から取り残された』という明治維新のセントラル・ドグマから出発する。
遅れた日本がいかにして西洋に追いつくか。
それは科学技術だけの話ではない。
文化の面でも西洋に追いつかなければならない。
たとえば日本にはないAという文化が西洋にあるとすれば、それは日本の遅れなのだから、早急に同じものを作らなければならない。
それがたとえ、西洋のAに見劣りするaであったとしても、ないよりはマシだ。
日本にある幼稚なzも、西洋のZに近づけるべく改良していかなければならない。
場合によっては西洋のものに置き換えなければならない。
明治時代、こういう運動が文化の各分野で澎湃としてわき上がる。
すなわち、あっていいような気がする、あるべきだという気がする、なければ作ろう、の運動を日本国全体で繰り広げたというわけだ。
その先鞭を付けたのが演劇で、当時は演劇改良運動などと呼ばれ、歌舞伎の近代化、つまりは舞台の西洋化を目指した。
音楽も西洋音楽がスタンダードとされた。
小説も言文一致が目標とされ、名作なのか駄作なのかよく分からないものが量産された。
それまで詩と言えば漢詩だったのが、明治になると新体詩なるものが生まれ、これが「短歌」に対する形で「長詩」と呼ばれるうち、ただの「詩」になった。
現代日本の詩は、翻訳も含め、すべてこの新体詩に源流を持つ。
ただし、と改めて但し書きをつけるまでもなく、あらゆるジャンルでそうなのだろうが、新体詩に名作は少なく、ほとんどがゴミである。
考えてみれば当たり前で、最初に新体詩を試みたのは詩人でも何でもない、ただの語学者にすぎないのだから。
もちろん、その中から島崎藤村という素晴らしい詩人が出たのだから、新体詩運動も無意味ではなかったのだろう。
新体詩運動がなければ島崎藤村は出なかったし、現代日本の詩そのものが成立していない。
だとすれば、もし現代日本で詩が死滅しているとするなら、その死の種は、新体詩の中にすでに胚胎されていたのではなかったか。
比べるに、たとえばリルケの『ドゥイノの悲歌』から神を除いたら何が残るだろう。
ただの「言葉、言葉、言葉」(ハムレット)であって詩ではない何か。
ポエジーの源泉が失われてしまうだろう。
西洋の詩にあり、新体詩になかったもの。
それは神である。
詩は神と共にあり、神へと至る、あるいは遠ざかる道なのである。
西洋の詩人は意識するとしないとに関わらず、あるいはその存在を肯定すると否定するとに関わらず、皆、神と共にある。
すなわち詩は、信仰の告白であり、あるいは信仰の否定である。
ポエジーは神との関係性によって生み出されるのだ。
よって、神と共にない詩はポエジーを失い、詩たり得ず、滅ぶほかはない。
これが現代日本で詩が死滅した根本原因だと、私は思っている。
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
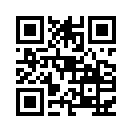
アクセスカウンタ
読者登録
