2019年10月18日
伊佐山紫文416
今日のグーグルのイメージを見て「これは何だ?」と思った人は多いと思う。
左前のチョゴリのようなキモノを着たお婆さんが、得体の知れない文字の書かれた紙なんだか板なんだかを持ち、なんだか不機嫌そうに歩んでいる。
その後ろではこれもまた国籍不明の髪形をした男女が得体の知れないものを読むのか眺めるのか、のぞき込んでいる。
なんだ、こりゃ。
で、文字通りググれば、これは日本の「民権バアさん」と呼ばれた「楠瀬喜多(くすのせきた)」を記念するイメージだと分かった。
楠瀬喜多は天保7年9月9日、新暦では1836年10月18日に生まれたから、それを記念するつもりなんだろう。
だったら、もっと調べて、きちんとしたイメージで描けよ。
楠瀬喜多は、そのうち夙川座の「上方うた芝居」でも主役を張らせたいと思っているような、土佐の傑物である。
そもそもが、明治13年(1880年)だよ、江戸幕府崩壊からたった13年しか経っていない時点で、今で言えば村議会議員選挙での女性参政権を認めさせたんだから。
楠瀬喜多も凄いが、当時の土佐も凄い。
ただ、楠瀬喜多のよって立つ論理「同じ戸主なのに女性にだけ参政権がないのはおかしい」という論理は、「戸主」という言葉の強権的イメージがアカデミック左翼の拒絶反応を呼び、今でも正当な評価を得ているとは言いがたい。
実際にはアメリカのワイオミング州に次ぐ、世界で二番目の女性参政権獲得という偉業を成し遂げた女性なんだ。
このことはもっと知られて良いはずだ。
今日のグーグルのイメージは、楠瀬喜多の現在の評価を示すものとして絶妙だと思う。
是非ご覧あれ。
左前のチョゴリのようなキモノを着たお婆さんが、得体の知れない文字の書かれた紙なんだか板なんだかを持ち、なんだか不機嫌そうに歩んでいる。
その後ろではこれもまた国籍不明の髪形をした男女が得体の知れないものを読むのか眺めるのか、のぞき込んでいる。
なんだ、こりゃ。
で、文字通りググれば、これは日本の「民権バアさん」と呼ばれた「楠瀬喜多(くすのせきた)」を記念するイメージだと分かった。
楠瀬喜多は天保7年9月9日、新暦では1836年10月18日に生まれたから、それを記念するつもりなんだろう。
だったら、もっと調べて、きちんとしたイメージで描けよ。
楠瀬喜多は、そのうち夙川座の「上方うた芝居」でも主役を張らせたいと思っているような、土佐の傑物である。
そもそもが、明治13年(1880年)だよ、江戸幕府崩壊からたった13年しか経っていない時点で、今で言えば村議会議員選挙での女性参政権を認めさせたんだから。
楠瀬喜多も凄いが、当時の土佐も凄い。
ただ、楠瀬喜多のよって立つ論理「同じ戸主なのに女性にだけ参政権がないのはおかしい」という論理は、「戸主」という言葉の強権的イメージがアカデミック左翼の拒絶反応を呼び、今でも正当な評価を得ているとは言いがたい。
実際にはアメリカのワイオミング州に次ぐ、世界で二番目の女性参政権獲得という偉業を成し遂げた女性なんだ。
このことはもっと知られて良いはずだ。
今日のグーグルのイメージは、楠瀬喜多の現在の評価を示すものとして絶妙だと思う。
是非ご覧あれ。
2019年10月18日
伊佐山紫文416
息子が「AI時代を迎えて、(もし研究者になったとして)将来役に立つスキル」は何かと聞いてきて、「俺に聞くなよ」と思いつつも「そりゃ英語だろ」と答えた。
そもそもプログラム言語そのものが英語をベースにしているから、たとえば「print」の意味が分からなければ、印刷さえ出来ないことになる。
それでも、と、ここからが厄介な話なのだが、プログラム言語とか専門用語とか、そういう基礎的な部分に使う英語さえ憶えておけば、専門的な研究生活であっても、日本だけならそう困ることはない。
私の大学の先生で英会話に堪能な方など一人もいなかったし、むしろ、外国から来たお客様の案内はもっぱら私が務めていたほどだ。
先生方は英語の論文は読めていたにしても、発表は全て日本語だった。
その媒体にしてからが、たとえば『Zoological Magazine』という得体の知れないものだった。
「動物学みたいな雑誌」って、そりゃいったいなんだよ。
さすがに今では違ったタイトルになったみたいだが、私が学生だった頃は、こんなものがまかり通っていた。
日本はそれなりに大きな国だし、研究者はみんな優秀だし、日本語だけのコミュニケーションでも、専門的な研究生活は成り立っていたのである。
だから、もし、日本語で書かれた論文の全てが英語に翻訳されていたら、日本人のノーベル賞受賞者の数は今の二倍や三倍では済まないだろうと言われているのも、これは決して誇張ではない。
英語圏の書籍を読むと日本の文献など無きがごとしだが、実際には日本語圏では英語圏に負けず劣らず豊潤な研究がなされ、日本語の文献も山ほどある。
まるでSFでいうような平行世界である。
けれど、実際には「世界」とは英語圏であり、日本語圏は日本というローカルでしかない。
どれだけ専門的に優れていようが、英語で発信(プレゼンテーション)出来なければ、(英語圏という)世界的には存在しないのと同じなのである。
好むと好まざるとに関わらず、これからは「世界」で仕事をすることが必要になる。
だから、英語を読めるだけではなく、書ける。
書けるだけではなく、話せる。
話せるだけではなく、発信(プレゼンテーション)出来る。
これからの時代、それが大事だと思うんだよ、お父さんはね。
まあ、お前が何になるのかは知らんが、とにかく単語帳読もう。
そもそもプログラム言語そのものが英語をベースにしているから、たとえば「print」の意味が分からなければ、印刷さえ出来ないことになる。
それでも、と、ここからが厄介な話なのだが、プログラム言語とか専門用語とか、そういう基礎的な部分に使う英語さえ憶えておけば、専門的な研究生活であっても、日本だけならそう困ることはない。
私の大学の先生で英会話に堪能な方など一人もいなかったし、むしろ、外国から来たお客様の案内はもっぱら私が務めていたほどだ。
先生方は英語の論文は読めていたにしても、発表は全て日本語だった。
その媒体にしてからが、たとえば『Zoological Magazine』という得体の知れないものだった。
「動物学みたいな雑誌」って、そりゃいったいなんだよ。
さすがに今では違ったタイトルになったみたいだが、私が学生だった頃は、こんなものがまかり通っていた。
日本はそれなりに大きな国だし、研究者はみんな優秀だし、日本語だけのコミュニケーションでも、専門的な研究生活は成り立っていたのである。
だから、もし、日本語で書かれた論文の全てが英語に翻訳されていたら、日本人のノーベル賞受賞者の数は今の二倍や三倍では済まないだろうと言われているのも、これは決して誇張ではない。
英語圏の書籍を読むと日本の文献など無きがごとしだが、実際には日本語圏では英語圏に負けず劣らず豊潤な研究がなされ、日本語の文献も山ほどある。
まるでSFでいうような平行世界である。
けれど、実際には「世界」とは英語圏であり、日本語圏は日本というローカルでしかない。
どれだけ専門的に優れていようが、英語で発信(プレゼンテーション)出来なければ、(英語圏という)世界的には存在しないのと同じなのである。
好むと好まざるとに関わらず、これからは「世界」で仕事をすることが必要になる。
だから、英語を読めるだけではなく、書ける。
書けるだけではなく、話せる。
話せるだけではなく、発信(プレゼンテーション)出来る。
これからの時代、それが大事だと思うんだよ、お父さんはね。
まあ、お前が何になるのかは知らんが、とにかく単語帳読もう。
2019年10月18日
伊佐山紫文415
『異端の数ゼロ 数学・物理学が恐れるもっとも危険な概念』
チャールズ・サイフェ著 林大訳
ハヤカワノンフィクション文庫
西洋はついに「ゼロ0」を発見することはなかった。
それは東洋からもたらされた。
ここまでは周知のことだろう。
いわゆる「ゼノンのパラドックス」、アキレスは亀に永遠に追いつけない、というあれも、ギリシア人が「ゼロ」を拒絶したことから生じた。
本書は様々な文明を比較しつつ、古代ギリシャを起点に、微分積分の「極限」概念をエレガントに解説したかと思うと、一気に相対性理論や量子力学をくぐり抜け、ブラックホールやビッグバンにまで至る。
まさに人類の知的遺産をめぐる手引き書である。
文句なしに面白く、内容も濃い。
数式はほとんど出てこない。
チャールズ・サイフェ著 林大訳
ハヤカワノンフィクション文庫
西洋はついに「ゼロ0」を発見することはなかった。
それは東洋からもたらされた。
ここまでは周知のことだろう。
いわゆる「ゼノンのパラドックス」、アキレスは亀に永遠に追いつけない、というあれも、ギリシア人が「ゼロ」を拒絶したことから生じた。
本書は様々な文明を比較しつつ、古代ギリシャを起点に、微分積分の「極限」概念をエレガントに解説したかと思うと、一気に相対性理論や量子力学をくぐり抜け、ブラックホールやビッグバンにまで至る。
まさに人類の知的遺産をめぐる手引き書である。
文句なしに面白く、内容も濃い。
数式はほとんど出てこない。
2019年10月18日
伊佐山紫文414
映画『イエスタデイ』令和元年2019年イギリス
監督:ダニー・ボイル 脚本:リチャード・カーティス
ま、ビートルズの名曲がちりばめられたB級映画ですわ。
それのどこが悪い!
主役のオーラなさ過ぎ。
そういう設定でしょうが!
とにかくもう、懐かしくて、切なくて、細部の矛盾なんかどうでも良い。
今気づくチャチな歌詞もそれはそれ、若いってのはそういうもの。
長生きしたジョンの丸メガネに思わず涙。
監督:ダニー・ボイル 脚本:リチャード・カーティス
ま、ビートルズの名曲がちりばめられたB級映画ですわ。
それのどこが悪い!
主役のオーラなさ過ぎ。
そういう設定でしょうが!
とにかくもう、懐かしくて、切なくて、細部の矛盾なんかどうでも良い。
今気づくチャチな歌詞もそれはそれ、若いってのはそういうもの。
長生きしたジョンの丸メガネに思わず涙。
2019年10月14日
伊佐山紫文412
『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』
大木毅著 岩波新書
ちょっと話題になっているから読んでみた。
とかいう、そんなレベルの本じゃなかった。
第二次世界大戦の主戦場は決してアジアではなかったことが、まずは具体的な数字を持って示される。
死者の数である。
日本の戦死者は「二一〇万ないし二三〇万名(中略)充分に悲惨な数字だ。けれども、独ソ両国、なかんずくソ連の損害は桁が違う」。
戦死だけで一千万以上の命が失われ、虐殺された民間人も一千万、疫病や飢餓で亡くなった民間人が九〇〇万。
ドイツも五〇〇万以上が戦死し、民間人も三〇〇万人が死んだ。
まさに著者の言う「人類史上最大の惨戦」である。
何でこんなことになったのか?
それは、著者によれば、これが通常の戦争ではなく、ドイツにとっては「世界観戦争」、ソ連にとっては「大祖国戦争」であったからだ。
当時のドイツはヒトラー、ソ連はスターリンという、最悪の独裁者を戴いている。
今から思えば、独ソ戦は起こるべくして起きたし、最悪の経過をたどり最悪に近い結末を迎えたのは当然だろう。
それでも著者は、この戦争を、国家社会主義(ナチズム)と共産主義(スターリニズム)のイデオロギー衝突としては描かない。
また、ヒトラー個人の愚行とスターリン個人の悪意に帰すこともない。
あくまでも淡々と、事実だけを積み上げていく。
まあ、とにかく、読んでみようよ、としか言えない。
大木毅著 岩波新書
ちょっと話題になっているから読んでみた。
とかいう、そんなレベルの本じゃなかった。
第二次世界大戦の主戦場は決してアジアではなかったことが、まずは具体的な数字を持って示される。
死者の数である。
日本の戦死者は「二一〇万ないし二三〇万名(中略)充分に悲惨な数字だ。けれども、独ソ両国、なかんずくソ連の損害は桁が違う」。
戦死だけで一千万以上の命が失われ、虐殺された民間人も一千万、疫病や飢餓で亡くなった民間人が九〇〇万。
ドイツも五〇〇万以上が戦死し、民間人も三〇〇万人が死んだ。
まさに著者の言う「人類史上最大の惨戦」である。
何でこんなことになったのか?
それは、著者によれば、これが通常の戦争ではなく、ドイツにとっては「世界観戦争」、ソ連にとっては「大祖国戦争」であったからだ。
当時のドイツはヒトラー、ソ連はスターリンという、最悪の独裁者を戴いている。
今から思えば、独ソ戦は起こるべくして起きたし、最悪の経過をたどり最悪に近い結末を迎えたのは当然だろう。
それでも著者は、この戦争を、国家社会主義(ナチズム)と共産主義(スターリニズム)のイデオロギー衝突としては描かない。
また、ヒトラー個人の愚行とスターリン個人の悪意に帰すこともない。
あくまでも淡々と、事実だけを積み上げていく。
まあ、とにかく、読んでみようよ、としか言えない。
2019年10月14日
伊佐山紫文412
『狂気の科学者たち』
アレックス・バーザ著 プレシ南日子訳
新潮文庫
邦題には少し問題がある。
本書で紹介されている科学者たちのほとんどは「狂気」にとりつかれるどころか、むしろ「正気」に過ぎるからだ。
「本気」でおかしなことに取り組んだり、まともなことをやってるはずがおかしな結果を招いたりといった、世間の常識を逸脱した科学者たちの生態が生き生きと描かれている。
また、周辺知識も楽しい。
たとえば、支配と服従の心理学の世界で二大実験と言われる「エール大学(ミルグラム)服従実験」と「スタンフォード大学(ジンバルドー)監獄実験」のミルグラムとジンバルドーが同じ高校の同級生だったり。
このミルグラムが『450ボルト』というCDを出しているなど、笑えないが思わず笑ってしまう。
450ページ近い文庫も楽しく一気読み!
中学生くらいからお薦めです。
アレックス・バーザ著 プレシ南日子訳
新潮文庫
邦題には少し問題がある。
本書で紹介されている科学者たちのほとんどは「狂気」にとりつかれるどころか、むしろ「正気」に過ぎるからだ。
「本気」でおかしなことに取り組んだり、まともなことをやってるはずがおかしな結果を招いたりといった、世間の常識を逸脱した科学者たちの生態が生き生きと描かれている。
また、周辺知識も楽しい。
たとえば、支配と服従の心理学の世界で二大実験と言われる「エール大学(ミルグラム)服従実験」と「スタンフォード大学(ジンバルドー)監獄実験」のミルグラムとジンバルドーが同じ高校の同級生だったり。
このミルグラムが『450ボルト』というCDを出しているなど、笑えないが思わず笑ってしまう。
450ページ近い文庫も楽しく一気読み!
中学生くらいからお薦めです。
2019年10月12日
伊佐山紫文411
大学の何年生のことだったか、ふと思いついて、帰省のついでに父の畏友の家に寄ってみたことがある。
この人は当時の社会党の県会議員で、議員になる前には県の教育委員会のエライさんも務め、小学生の私が昆虫に興味を示していると知るや、当時としては信じられない程の高級な捕虫網を買ってくれた。
その後、県会議員になっても、高校生の私が水生昆虫の研究で新聞に載るや、その新聞を買い占めてあちこちに配ってくれたりもした。
とにかく「この子はとんでもない人物になる」と言って、なにくれと世話を焼いてくれたのだった。
今は何学部になるのかは分からないが、戦前の京大で文学を学び、学問としてではない、ナマの「文学」を生きる私の父の(トンデモナイ)生き様に圧倒され、崇拝者の一人になった。
小学生の私は夏休みにはこの人の家に預けられ、政治家としての処世を学ばされた。
とにかく「この子はとんでもない人物になる」と言われ、県のエライさんの前に出された。
まあ、確かに「とんでもない人物」にはなったが。
で、久しぶりに会ったこの人が、このとき、なぜかノーベル平和賞を取るべきだと言いつのっていたのが同志太田薫で、当時の総評委員長にして、今の春闘を作った人物である。
その業績が評価され「レーニン平和賞」をとってもいる。
レーニン平和賞……
人が人を見る目ってのは……
ちなみに、ヒトラーもノーベル平和賞の候補だったことがある。
やれやれ……
この人は当時の社会党の県会議員で、議員になる前には県の教育委員会のエライさんも務め、小学生の私が昆虫に興味を示していると知るや、当時としては信じられない程の高級な捕虫網を買ってくれた。
その後、県会議員になっても、高校生の私が水生昆虫の研究で新聞に載るや、その新聞を買い占めてあちこちに配ってくれたりもした。
とにかく「この子はとんでもない人物になる」と言って、なにくれと世話を焼いてくれたのだった。
今は何学部になるのかは分からないが、戦前の京大で文学を学び、学問としてではない、ナマの「文学」を生きる私の父の(トンデモナイ)生き様に圧倒され、崇拝者の一人になった。
小学生の私は夏休みにはこの人の家に預けられ、政治家としての処世を学ばされた。
とにかく「この子はとんでもない人物になる」と言われ、県のエライさんの前に出された。
まあ、確かに「とんでもない人物」にはなったが。
で、久しぶりに会ったこの人が、このとき、なぜかノーベル平和賞を取るべきだと言いつのっていたのが同志太田薫で、当時の総評委員長にして、今の春闘を作った人物である。
その業績が評価され「レーニン平和賞」をとってもいる。
レーニン平和賞……
人が人を見る目ってのは……
ちなみに、ヒトラーもノーベル平和賞の候補だったことがある。
やれやれ……
2019年10月11日
伊佐山紫文410
好みや趣味でしかない「文学」に序列や賞など意味がない。
とまでは言わない。
若い才能がこの世知辛い世に出て行くためには、どうしても「賞」という武器が必要だ。
そう思って菊池寛が始めたのが芥川賞や直木賞だった。
この意義は認めるし、私がもし若い頃、芥川か直木か、どちらかの賞を捕っていれば人生はまた違うものになっていただろうとは思う(笑)。
で、ところで、ノーベル文学賞の意義は?
私は全くないと思う。
そもそもトルストイを蹴るような選考委員だし、各国のペンクラブの推薦が重視されるとなれば、内容よりもその国における権威、あるいは反権威が候補になりやすい。
普通のベストセラー作家など、まず推薦されることはあるまい。
そして、最後までナチスの友好国だったスウェーデンには、イスラエルに対する負い目がある。
エルサレムで薄っぺらなイスラエル批判を口にした村上春樹の受賞がまずあるまいと思う理由でもある。
とまでは言わない。
若い才能がこの世知辛い世に出て行くためには、どうしても「賞」という武器が必要だ。
そう思って菊池寛が始めたのが芥川賞や直木賞だった。
この意義は認めるし、私がもし若い頃、芥川か直木か、どちらかの賞を捕っていれば人生はまた違うものになっていただろうとは思う(笑)。
で、ところで、ノーベル文学賞の意義は?
私は全くないと思う。
そもそもトルストイを蹴るような選考委員だし、各国のペンクラブの推薦が重視されるとなれば、内容よりもその国における権威、あるいは反権威が候補になりやすい。
普通のベストセラー作家など、まず推薦されることはあるまい。
そして、最後までナチスの友好国だったスウェーデンには、イスラエルに対する負い目がある。
エルサレムで薄っぺらなイスラエル批判を口にした村上春樹の受賞がまずあるまいと思う理由でもある。
2019年10月10日
伊佐山紫文409
ノーベル賞をとる条件として、最も重要なのは何か。
そりゃ、長生きでしょう。
とにかく、選考委員としては「誤報」だけは避けたい。
「間違いでした」では済まないし、後々論争の種になるようなこともしたくない。
だから確定した業績、だれもケチをつけてこない仕事にだけ与えるようになる。
何十年も前の、今では学会の常識となった仕事を探して、恭しく授与する。
結果、とっくに盛りを過ぎた、ハッキリ言って「元」研究者ばかりが莫大な賞金を手にすることになる。
逆に、若く、この、たった今、資金が必要な研究者は置き去りである。
これでいいのか?
良くないから、受賞者は賞金を寄付したりするのだが、それっておかしくはないか、と思う。
私がこの時期、いつも思うのは、DNAである。
DNAの二重らせん構造を解明したのはワトソン、クリック、ウィルキンスの三人であり、当然、ノーベル賞が与えられたのだが、実はこの三人、DNA構造の解析に繋がる写真を撮った訳ではない。
有名な、あのボーッとしたX線写真、このどこが二重らせんなんですか、と言いたくなる電子顕微鏡写真を撮ったのは、この三人ではなく、ロザリンド・フランクリンという、三人の同僚の女性科学者だった。
とにかく頑張り屋さんで、今で言えばおそらく発達障害の、人付き合いの苦手な、のちのワトソンから「ダークレディ」と呼ばれるような研究者である。
当時、放射線への知識は貧弱で、放射性物質に関わる研究者が若くしてバタバタとガンで亡くなっていっても、その原因など考えてみようともしない。
あのキューリー夫人など、素手でラジウムを触っていたというのだ。
それと死因であるガンを結びつけるのは早計だと言われもするが、そういう誰も素手でラジウムを触ろうとはしない。
ロザリンドの時代も、X線を無防備にガンガン使う当時の電子顕微鏡に張り付いていれば若い女性の体に何が起こるか、今では誰もが心配するだろう。
私も学生時代、電子顕微鏡は何度も使ったから分かるのだが、DNAの写真を撮ると一言で言うが、そう簡単なことではない。
そもそも細胞の中のどれがDNAであるか特定しないといけないし、それを分離しないといけないし、そしてそれがきちんと写るように配置しなければならない。
構造解析の元となる写真を撮ることが、そもそも至難の業なのである。
しかも失敗か成功かは写真を撮ってからでなければ分からない。
ロザリンドの時代、何年もの間、毎日毎日毎日毎日、何度も何度も何度も何度も、強烈な放射線を浴びながら、周囲からは「ダークレディ」などと罵声を浴びせられながらの作業である。
その結果、会心の一枚が撮れた。
けれど、その画像が何を意味するのか、そこまでは分からない。
で、同僚のウィルキンスに見せて相談した。
ウィルキンスはワトソンとクリックにも見せて検討した。
電子顕微鏡のあの画像はデータを可視化しただけであって、実際にはすべて数値である。
電子がどのようにぶつかり、跳ね返り、あるいは吸収されたかという、膨大なデータがそこにある。
ワトソンとクリックはそれに取り組み、DNAは二重らせん構造であるという結論を出した。
今ではこの業績は生物学の「セントラルドグマ」と呼ばれるほどの偉大な仕事だとされているが、発表された当時は何の反響も呼ばなかった。
ところが次第にこの仕事の重要さが知られるようになり、ダーウィンの進化論、メンデルの遺伝学、そしてDNAの二重らせん構造とが結びついて、現代の生物学の基礎が築かれることになる。
当然、ワトソン、クリック、ウィルキンスの三人には1962年(昭和37年、私の生まれた年である)ノーベル生理学・医学賞が与えられた。
あれ?
ロザリンドは?
実は、彼女は1958年に卵巣ガンで、37歳の若さで亡くなっていたのである。
もちろん、電子顕微鏡との関連など分からない。
ただ、彼女の撮ったDNAの写真がなければこの三人のノーベル賞受賞はなかったし、生物学の歩みも少し違ったものになっていただろう。
とにかくこの世は、長生きしたもの勝ちである。
ノーベル賞も例外ではないということだ。
そりゃ、長生きでしょう。
とにかく、選考委員としては「誤報」だけは避けたい。
「間違いでした」では済まないし、後々論争の種になるようなこともしたくない。
だから確定した業績、だれもケチをつけてこない仕事にだけ与えるようになる。
何十年も前の、今では学会の常識となった仕事を探して、恭しく授与する。
結果、とっくに盛りを過ぎた、ハッキリ言って「元」研究者ばかりが莫大な賞金を手にすることになる。
逆に、若く、この、たった今、資金が必要な研究者は置き去りである。
これでいいのか?
良くないから、受賞者は賞金を寄付したりするのだが、それっておかしくはないか、と思う。
私がこの時期、いつも思うのは、DNAである。
DNAの二重らせん構造を解明したのはワトソン、クリック、ウィルキンスの三人であり、当然、ノーベル賞が与えられたのだが、実はこの三人、DNA構造の解析に繋がる写真を撮った訳ではない。
有名な、あのボーッとしたX線写真、このどこが二重らせんなんですか、と言いたくなる電子顕微鏡写真を撮ったのは、この三人ではなく、ロザリンド・フランクリンという、三人の同僚の女性科学者だった。
とにかく頑張り屋さんで、今で言えばおそらく発達障害の、人付き合いの苦手な、のちのワトソンから「ダークレディ」と呼ばれるような研究者である。
当時、放射線への知識は貧弱で、放射性物質に関わる研究者が若くしてバタバタとガンで亡くなっていっても、その原因など考えてみようともしない。
あのキューリー夫人など、素手でラジウムを触っていたというのだ。
それと死因であるガンを結びつけるのは早計だと言われもするが、そういう誰も素手でラジウムを触ろうとはしない。
ロザリンドの時代も、X線を無防備にガンガン使う当時の電子顕微鏡に張り付いていれば若い女性の体に何が起こるか、今では誰もが心配するだろう。
私も学生時代、電子顕微鏡は何度も使ったから分かるのだが、DNAの写真を撮ると一言で言うが、そう簡単なことではない。
そもそも細胞の中のどれがDNAであるか特定しないといけないし、それを分離しないといけないし、そしてそれがきちんと写るように配置しなければならない。
構造解析の元となる写真を撮ることが、そもそも至難の業なのである。
しかも失敗か成功かは写真を撮ってからでなければ分からない。
ロザリンドの時代、何年もの間、毎日毎日毎日毎日、何度も何度も何度も何度も、強烈な放射線を浴びながら、周囲からは「ダークレディ」などと罵声を浴びせられながらの作業である。
その結果、会心の一枚が撮れた。
けれど、その画像が何を意味するのか、そこまでは分からない。
で、同僚のウィルキンスに見せて相談した。
ウィルキンスはワトソンとクリックにも見せて検討した。
電子顕微鏡のあの画像はデータを可視化しただけであって、実際にはすべて数値である。
電子がどのようにぶつかり、跳ね返り、あるいは吸収されたかという、膨大なデータがそこにある。
ワトソンとクリックはそれに取り組み、DNAは二重らせん構造であるという結論を出した。
今ではこの業績は生物学の「セントラルドグマ」と呼ばれるほどの偉大な仕事だとされているが、発表された当時は何の反響も呼ばなかった。
ところが次第にこの仕事の重要さが知られるようになり、ダーウィンの進化論、メンデルの遺伝学、そしてDNAの二重らせん構造とが結びついて、現代の生物学の基礎が築かれることになる。
当然、ワトソン、クリック、ウィルキンスの三人には1962年(昭和37年、私の生まれた年である)ノーベル生理学・医学賞が与えられた。
あれ?
ロザリンドは?
実は、彼女は1958年に卵巣ガンで、37歳の若さで亡くなっていたのである。
もちろん、電子顕微鏡との関連など分からない。
ただ、彼女の撮ったDNAの写真がなければこの三人のノーベル賞受賞はなかったし、生物学の歩みも少し違ったものになっていただろう。
とにかくこの世は、長生きしたもの勝ちである。
ノーベル賞も例外ではないということだ。
2019年10月03日
伊佐山紫文408
『種の起源(上下)』
ダーウィン著 渡辺政隆訳
光文社古典新訳文庫
ベンヤミンの『ドイツ悲劇(悲哀劇)の根源』でもそうだが、書誌的に正確な訳(ちくま学芸文庫)と読みやすい訳(講談社文芸文庫)とは明らかに違う。
研究者には大事だろうが、一般人にとっては初版と最終版の違いなどどうでも良いし、とにかく何が書いてあるのかが伝わらなければ翻訳する意義などない。
ベンヤミンの『ドイツ悲劇(悲哀劇)の根源』を読むなら、絶対に講談社文芸文庫の版をお薦めする。
どれだけ書誌的に正確であっても、読み通せなければ無意味なのだ。
その意味で、八杉竜一訳岩波文庫版のダーウィン『種の起源』は最悪だった。
そもそものダーウィンの英語のくどさ・わかりにくさをそのまま写し取った本文に、しかも「初版ではどうの」「この言葉は第何版から云々」という注がやたらと入り込んでいて、著書としての主張の流れが見えず、読み通すのが非常に困難な難物だった。
今回、古典新訳文庫版の新訳で『種の起源』を読んでみると、透明な文体を通してダーウィンの主張が全き姿で現前に現れ、あまりのインパクトに、正直、震え上がった。
世界を変えた本というものがあるとするなら、これ以上のものはないと断言する。
とにかく「世界」というものの見方が一変するのである。
生き物は自身よりも多くの子孫を残し、子孫の中で適応したものが生き残る。
そのようなせめぎ合い(自然淘汰)のなかで進化が起こり、現存の「種」が生まれた。「種」の「起源」に「神」など必要ないのである。
自然淘汰という単純なアルゴリズムの無限の繰り返しによってこの「世界」は出来上がったのだし、この、たった今も出来上がりつつある。
この世界が出来上がるのに「目的」や「意思」など必要ないし、「神」など不要だと言うことだ。
しかも、つまり人間は「神」の似姿などではなく、サルと祖先を共有する動物の一種でしかない。
だとしたら……
人生の目的は、ただ子孫を残すことだけなのか?
弱者は滅んで当然なのか?
慈愛などそもそも無意味で、むしろ社会「進化」の妨げになるのではないか?
資本主義が伝統的な倫理観を侵食していた時代、この『種の起源』は伝統の全てを土台から掘り崩し、むしろ近代の思想的基盤を築いた。
「社会ダーウィニズム」という思想的怪物が、これ以後、世界を席巻することになる。
障害者が、少数民族が、有色人種が、まさにダーウィンの名において差別され、収容され、去勢され、抹殺されることになるだろう。
そういう思想的インパクトを全て理解した上での新訳であり、ジャンケンの後出しのような狡さはあるが、それでも見事な仕事である。
ダーウィン著 渡辺政隆訳
光文社古典新訳文庫
ベンヤミンの『ドイツ悲劇(悲哀劇)の根源』でもそうだが、書誌的に正確な訳(ちくま学芸文庫)と読みやすい訳(講談社文芸文庫)とは明らかに違う。
研究者には大事だろうが、一般人にとっては初版と最終版の違いなどどうでも良いし、とにかく何が書いてあるのかが伝わらなければ翻訳する意義などない。
ベンヤミンの『ドイツ悲劇(悲哀劇)の根源』を読むなら、絶対に講談社文芸文庫の版をお薦めする。
どれだけ書誌的に正確であっても、読み通せなければ無意味なのだ。
その意味で、八杉竜一訳岩波文庫版のダーウィン『種の起源』は最悪だった。
そもそものダーウィンの英語のくどさ・わかりにくさをそのまま写し取った本文に、しかも「初版ではどうの」「この言葉は第何版から云々」という注がやたらと入り込んでいて、著書としての主張の流れが見えず、読み通すのが非常に困難な難物だった。
今回、古典新訳文庫版の新訳で『種の起源』を読んでみると、透明な文体を通してダーウィンの主張が全き姿で現前に現れ、あまりのインパクトに、正直、震え上がった。
世界を変えた本というものがあるとするなら、これ以上のものはないと断言する。
とにかく「世界」というものの見方が一変するのである。
生き物は自身よりも多くの子孫を残し、子孫の中で適応したものが生き残る。
そのようなせめぎ合い(自然淘汰)のなかで進化が起こり、現存の「種」が生まれた。「種」の「起源」に「神」など必要ないのである。
自然淘汰という単純なアルゴリズムの無限の繰り返しによってこの「世界」は出来上がったのだし、この、たった今も出来上がりつつある。
この世界が出来上がるのに「目的」や「意思」など必要ないし、「神」など不要だと言うことだ。
しかも、つまり人間は「神」の似姿などではなく、サルと祖先を共有する動物の一種でしかない。
だとしたら……
人生の目的は、ただ子孫を残すことだけなのか?
弱者は滅んで当然なのか?
慈愛などそもそも無意味で、むしろ社会「進化」の妨げになるのではないか?
資本主義が伝統的な倫理観を侵食していた時代、この『種の起源』は伝統の全てを土台から掘り崩し、むしろ近代の思想的基盤を築いた。
「社会ダーウィニズム」という思想的怪物が、これ以後、世界を席巻することになる。
障害者が、少数民族が、有色人種が、まさにダーウィンの名において差別され、収容され、去勢され、抹殺されることになるだろう。
そういう思想的インパクトを全て理解した上での新訳であり、ジャンケンの後出しのような狡さはあるが、それでも見事な仕事である。
2019年10月03日
伊佐山紫文407
「だったら、これ、この白いの牛乳じゃねえのかよ」
と、息子が言う。
「前から言うてるやろ、お前が味噌のツブツブが嫌やって言うから、ツブのない豆乳で味噌を造って味噌汁にしとるんやって」
「だったら、これ、味噌汁か!」
「当たり前や。ホワイトシチューとでも思とったんか」
「知らんかったわ」
「ゴボウの入ったホワイトシチューがどこにある」
子どもは味覚に敏感だから、と、色々気を遣ってきた。
味噌汁の大豆や米のツブが気になると言うから、ツブの全くない豆乳で味噌を造って……と、そんな感じで。
そんな手品のタネが、最近、次々と暴かれている。
息子本人が知恵をつけてきたのもあるし、むしろ私が、積極的にタネ明かしをしている。
どんだけ気を遣ってきたか、思い知らせてやろうと。
豆乳味噌のタネはこんな感じ。
材料:豆乳1リットル、塩100グラム、米麹100グラム
これを混ぜ合わせ、ヨーグルトメーカーで60度12時間、あとはミキサーで米麹の残骸をすりつぶせば出来上がりである。
実になめらかな白味噌で、これはペットボトルに入れて冷蔵庫へ。
野菜を煮た出汁に適量流し込めば、それだけで白い味噌汁が出来上がる。
味噌こしで解く必要もない。
これを、息子は、何年もの間、牛乳を使った何かのスープだと思い込んでいたらしい。
まあ、そう思い込ませていたんだけどね。
と、息子が言う。
「前から言うてるやろ、お前が味噌のツブツブが嫌やって言うから、ツブのない豆乳で味噌を造って味噌汁にしとるんやって」
「だったら、これ、味噌汁か!」
「当たり前や。ホワイトシチューとでも思とったんか」
「知らんかったわ」
「ゴボウの入ったホワイトシチューがどこにある」
子どもは味覚に敏感だから、と、色々気を遣ってきた。
味噌汁の大豆や米のツブが気になると言うから、ツブの全くない豆乳で味噌を造って……と、そんな感じで。
そんな手品のタネが、最近、次々と暴かれている。
息子本人が知恵をつけてきたのもあるし、むしろ私が、積極的にタネ明かしをしている。
どんだけ気を遣ってきたか、思い知らせてやろうと。
豆乳味噌のタネはこんな感じ。
材料:豆乳1リットル、塩100グラム、米麹100グラム
これを混ぜ合わせ、ヨーグルトメーカーで60度12時間、あとはミキサーで米麹の残骸をすりつぶせば出来上がりである。
実になめらかな白味噌で、これはペットボトルに入れて冷蔵庫へ。
野菜を煮た出汁に適量流し込めば、それだけで白い味噌汁が出来上がる。
味噌こしで解く必要もない。
これを、息子は、何年もの間、牛乳を使った何かのスープだと思い込んでいたらしい。
まあ、そう思い込ませていたんだけどね。
2019年10月03日
伊佐山紫文406
「OSAKAもの・ことづくりオープンフォーラム」
という催しに参加してきた。
内容は検索すれば出てくるので他に譲るが、興味深いことが幾つかあった。
なかでも、パネリストの皆さんが皆「歴史」を自らの財産として語り、議論を深めていったことには「さもありなん」と膝を打った(実際には打たなかったが)。
この場合の「歴史」とは「ストーリー」としての「ヒストリー」であり、言ってみれば「由来話」、端的には「物語」である。
思うに、人間の歴史は「物語」と「反物語」を波打つように反復し、反復し、飽くことなく反復してきた。
平成の30年は「反物語」のポストモダンの時代であり、無歴史、無故郷、グローバリズムとコスモポリタニズムの、無色透明でサラサラなモノゴトが価値とされた。
そこでの歴史は単なる「事実」であって、「事実」と「事実」を繋ぐ試みは、客観性を欠く、単なる「物語」だとして排斥された。
実存主義はおどろおどろしいだけだし、マルクス主義はソ連と一緒に滅んだし、故郷は捨てて懐かしむものでしかないし、家族など社会的構築物でしかない。
全ては「物語」でしかないのだ。
「物語」など、「神話」と一緒、我々を縛る鎖でしかない。
さあ、「物語」や「神話」を解体し、自らを縛る鎖を解いて自由になろう!
てなわけで、これはもう人類の歴史が繰り返してきた思想史的波の一方の際だとしか言い様がない。
で、それが行き詰まって、令和の時代、再び「物語」が復活してきた。
それを「ナショナリズム」だとか「ポピュリズム」だとか、ある種の人々は言いつのるのだろうが、まあ、勝手にすれば良い。
時代の波は変えられない。
しかも、最新の脳科学の知見によれば、私たちの脳は「物語」を欲しており、「物語」を通してしか事物を認識することは出来ない。
とすれば、人が、人に、何かを伝えようとすれば、「物語」(つまり歴史)を利用するのが手っ取り早いし、確実だと言うことだ。
もちろん、この「物語」も次第に陳腐化して、いつかは再び「反物語」の時代が始まるのだが、それはまた将来の話である。
今の令和の新時代、「物語」の時代が始まった。
そこで夙川座の出番である。
となれば、良いなあ。
という催しに参加してきた。
内容は検索すれば出てくるので他に譲るが、興味深いことが幾つかあった。
なかでも、パネリストの皆さんが皆「歴史」を自らの財産として語り、議論を深めていったことには「さもありなん」と膝を打った(実際には打たなかったが)。
この場合の「歴史」とは「ストーリー」としての「ヒストリー」であり、言ってみれば「由来話」、端的には「物語」である。
思うに、人間の歴史は「物語」と「反物語」を波打つように反復し、反復し、飽くことなく反復してきた。
平成の30年は「反物語」のポストモダンの時代であり、無歴史、無故郷、グローバリズムとコスモポリタニズムの、無色透明でサラサラなモノゴトが価値とされた。
そこでの歴史は単なる「事実」であって、「事実」と「事実」を繋ぐ試みは、客観性を欠く、単なる「物語」だとして排斥された。
実存主義はおどろおどろしいだけだし、マルクス主義はソ連と一緒に滅んだし、故郷は捨てて懐かしむものでしかないし、家族など社会的構築物でしかない。
全ては「物語」でしかないのだ。
「物語」など、「神話」と一緒、我々を縛る鎖でしかない。
さあ、「物語」や「神話」を解体し、自らを縛る鎖を解いて自由になろう!
てなわけで、これはもう人類の歴史が繰り返してきた思想史的波の一方の際だとしか言い様がない。
で、それが行き詰まって、令和の時代、再び「物語」が復活してきた。
それを「ナショナリズム」だとか「ポピュリズム」だとか、ある種の人々は言いつのるのだろうが、まあ、勝手にすれば良い。
時代の波は変えられない。
しかも、最新の脳科学の知見によれば、私たちの脳は「物語」を欲しており、「物語」を通してしか事物を認識することは出来ない。
とすれば、人が、人に、何かを伝えようとすれば、「物語」(つまり歴史)を利用するのが手っ取り早いし、確実だと言うことだ。
もちろん、この「物語」も次第に陳腐化して、いつかは再び「反物語」の時代が始まるのだが、それはまた将来の話である。
今の令和の新時代、「物語」の時代が始まった。
そこで夙川座の出番である。
となれば、良いなあ。
2019年10月03日
伊佐山紫文405
ショスタコーヴィチの第五交響曲を聴いてきた。
オーケストラ・アンサンブル・フォルツァの演奏で、八尾市文化会館プリズムホール。
この曲は別名「宇宙戦艦ポチョムキン」とも言われ、終楽章のブラスの大迫力で知られている。
実際、フォルツァの皆さんも、この楽章を演奏したくて選曲したんだろうな、と分かる熱演で、感動いたしました。
第一楽章展開部冒頭の不気味なピアノを、我が夙川座ゆかりの白藤望さんで聴けたのも良かった。
同じく白藤さんのチェレスタも印象的でした。
また、この曲はフルートが命なのですが、これも素晴らしかった。
と、簡単に言うが、この曲、単に「聴きました、感動しました」では済まない背景があって、それを言い出すともう、演奏も鑑賞も不可能になってしまう。
実は第五交響曲の前に、ショスタコーヴィチは第四交響曲を書いていたのだが、もしこの第四交響曲を発表していたら、確実に殺されていた。
時代はソ連、それもスターリン時代である。
多くの芸術家が「ブルジョア臭い」とのレッテルを貼られ、次々と投獄、殺戮されていた。
ショスタコーヴィチもオペラやバレーが共産党からの批判を受け、投獄寸前だった。
ここで、ブルジョア音楽として批判されていたマーラーの影響が明らかな第四交響曲を発表したら。
間違いなく、投獄され、飢え死にさせられていただろう。
「ブルジョア臭い」芸術家には最も苦しい死を与えるのがプロレタリア的正義である、とされていたのだ。
こんな世で生き残るためには、共産党の歓心を得なければならない。
そこで起死回生の一手として作曲したのがこの交響曲第五番なのである。
帝政ロシア時代の暗黒の苦悩から共産革命を経て歓喜にいたる(と解釈できる)この曲は、共産党を含む大衆に、大受けに受けた。
人気作曲家となったショスタコーヴィチを、共産党は生かしておくしかなかった。
未だに偽書かどうか確定しないヴォルコフ著『ショスタコーヴィチの証言』では、この終楽章は「強制された歓喜」(水野忠夫訳)とされ、手放しの快演、たとえばバーンスタインのものなどは薄っぺらいとさえ言われる。
いやいや、そもそもバーンスタインごときに何を求めるんだと言いたくもなるが、やはり、『証言』を踏まえたハイティンクら西側と、ムラヴィンスキー(初演者でもある)やロジェストヴェンスキーらソ連派では表現が微妙に異なることは否めない。
ショスタコーヴィチのその後の展開を考えれば、私は『証言』の側に立つ。
つまり、終楽章は「強制された歓喜」だろうと思う。
けれど、強制されていようがいまいが、「歓喜」は「歓喜」なのだとも思う。
試みに心の中で「梅干し、レモン、梅干し、レモン」と十数回唱えてみたまえ、自然と唾液が口を満たすだろう。
これは強制的に「梅干し、レモン」を聞かされても同じで、人間の生理反応である。
音楽も同じ、感動するように書かれていれば、安っぽいと思いつつも感動する。
これはもう、人間の生理反応なのであって、誰もそれを否定できない。
だから、堪能しましたよ。
フォルツァの皆さん、ご苦労様でした。
ちなみになんでこの曲がマニアの間で「宇宙戦艦ポチョムキン」と呼ばれるのかと言えば、エイゼンシュテインの名作映画『戦艦ポチョムキン』に使われているから。
戦前に作られたサイレント映画に、戦後になって第二楽章の音楽が後付けされたもので、私など、しばらくは、この映画のためにショスタコーヴィチが書いたのだと思っていた。
そのくらい、合ってる。
今回の演奏でも、あの、揚々とした戦艦シーンが頭に浮かびましたよ。
ちなみに、クラシック曲のアンソロジーで『交響戦艦ショスタコーヴィチ ~ ヒーロー風クラシック名曲集 』というCDが、なんとナクソスレーベルから出ていて、曲目を見ただけで笑えます。
『交響戦艦ショスタコーヴィチ ~ ヒーロー風クラシック名曲集 』で検索っ!
オーケストラ・アンサンブル・フォルツァの演奏で、八尾市文化会館プリズムホール。
この曲は別名「宇宙戦艦ポチョムキン」とも言われ、終楽章のブラスの大迫力で知られている。
実際、フォルツァの皆さんも、この楽章を演奏したくて選曲したんだろうな、と分かる熱演で、感動いたしました。
第一楽章展開部冒頭の不気味なピアノを、我が夙川座ゆかりの白藤望さんで聴けたのも良かった。
同じく白藤さんのチェレスタも印象的でした。
また、この曲はフルートが命なのですが、これも素晴らしかった。
と、簡単に言うが、この曲、単に「聴きました、感動しました」では済まない背景があって、それを言い出すともう、演奏も鑑賞も不可能になってしまう。
実は第五交響曲の前に、ショスタコーヴィチは第四交響曲を書いていたのだが、もしこの第四交響曲を発表していたら、確実に殺されていた。
時代はソ連、それもスターリン時代である。
多くの芸術家が「ブルジョア臭い」とのレッテルを貼られ、次々と投獄、殺戮されていた。
ショスタコーヴィチもオペラやバレーが共産党からの批判を受け、投獄寸前だった。
ここで、ブルジョア音楽として批判されていたマーラーの影響が明らかな第四交響曲を発表したら。
間違いなく、投獄され、飢え死にさせられていただろう。
「ブルジョア臭い」芸術家には最も苦しい死を与えるのがプロレタリア的正義である、とされていたのだ。
こんな世で生き残るためには、共産党の歓心を得なければならない。
そこで起死回生の一手として作曲したのがこの交響曲第五番なのである。
帝政ロシア時代の暗黒の苦悩から共産革命を経て歓喜にいたる(と解釈できる)この曲は、共産党を含む大衆に、大受けに受けた。
人気作曲家となったショスタコーヴィチを、共産党は生かしておくしかなかった。
未だに偽書かどうか確定しないヴォルコフ著『ショスタコーヴィチの証言』では、この終楽章は「強制された歓喜」(水野忠夫訳)とされ、手放しの快演、たとえばバーンスタインのものなどは薄っぺらいとさえ言われる。
いやいや、そもそもバーンスタインごときに何を求めるんだと言いたくもなるが、やはり、『証言』を踏まえたハイティンクら西側と、ムラヴィンスキー(初演者でもある)やロジェストヴェンスキーらソ連派では表現が微妙に異なることは否めない。
ショスタコーヴィチのその後の展開を考えれば、私は『証言』の側に立つ。
つまり、終楽章は「強制された歓喜」だろうと思う。
けれど、強制されていようがいまいが、「歓喜」は「歓喜」なのだとも思う。
試みに心の中で「梅干し、レモン、梅干し、レモン」と十数回唱えてみたまえ、自然と唾液が口を満たすだろう。
これは強制的に「梅干し、レモン」を聞かされても同じで、人間の生理反応である。
音楽も同じ、感動するように書かれていれば、安っぽいと思いつつも感動する。
これはもう、人間の生理反応なのであって、誰もそれを否定できない。
だから、堪能しましたよ。
フォルツァの皆さん、ご苦労様でした。
ちなみになんでこの曲がマニアの間で「宇宙戦艦ポチョムキン」と呼ばれるのかと言えば、エイゼンシュテインの名作映画『戦艦ポチョムキン』に使われているから。
戦前に作られたサイレント映画に、戦後になって第二楽章の音楽が後付けされたもので、私など、しばらくは、この映画のためにショスタコーヴィチが書いたのだと思っていた。
そのくらい、合ってる。
今回の演奏でも、あの、揚々とした戦艦シーンが頭に浮かびましたよ。
ちなみに、クラシック曲のアンソロジーで『交響戦艦ショスタコーヴィチ ~ ヒーロー風クラシック名曲集 』というCDが、なんとナクソスレーベルから出ていて、曲目を見ただけで笑えます。
『交響戦艦ショスタコーヴィチ ~ ヒーロー風クラシック名曲集 』で検索っ!
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
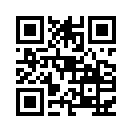
アクセスカウンタ
読者登録
