2019年10月10日
伊佐山紫文409
ノーベル賞をとる条件として、最も重要なのは何か。
そりゃ、長生きでしょう。
とにかく、選考委員としては「誤報」だけは避けたい。
「間違いでした」では済まないし、後々論争の種になるようなこともしたくない。
だから確定した業績、だれもケチをつけてこない仕事にだけ与えるようになる。
何十年も前の、今では学会の常識となった仕事を探して、恭しく授与する。
結果、とっくに盛りを過ぎた、ハッキリ言って「元」研究者ばかりが莫大な賞金を手にすることになる。
逆に、若く、この、たった今、資金が必要な研究者は置き去りである。
これでいいのか?
良くないから、受賞者は賞金を寄付したりするのだが、それっておかしくはないか、と思う。
私がこの時期、いつも思うのは、DNAである。
DNAの二重らせん構造を解明したのはワトソン、クリック、ウィルキンスの三人であり、当然、ノーベル賞が与えられたのだが、実はこの三人、DNA構造の解析に繋がる写真を撮った訳ではない。
有名な、あのボーッとしたX線写真、このどこが二重らせんなんですか、と言いたくなる電子顕微鏡写真を撮ったのは、この三人ではなく、ロザリンド・フランクリンという、三人の同僚の女性科学者だった。
とにかく頑張り屋さんで、今で言えばおそらく発達障害の、人付き合いの苦手な、のちのワトソンから「ダークレディ」と呼ばれるような研究者である。
当時、放射線への知識は貧弱で、放射性物質に関わる研究者が若くしてバタバタとガンで亡くなっていっても、その原因など考えてみようともしない。
あのキューリー夫人など、素手でラジウムを触っていたというのだ。
それと死因であるガンを結びつけるのは早計だと言われもするが、そういう誰も素手でラジウムを触ろうとはしない。
ロザリンドの時代も、X線を無防備にガンガン使う当時の電子顕微鏡に張り付いていれば若い女性の体に何が起こるか、今では誰もが心配するだろう。
私も学生時代、電子顕微鏡は何度も使ったから分かるのだが、DNAの写真を撮ると一言で言うが、そう簡単なことではない。
そもそも細胞の中のどれがDNAであるか特定しないといけないし、それを分離しないといけないし、そしてそれがきちんと写るように配置しなければならない。
構造解析の元となる写真を撮ることが、そもそも至難の業なのである。
しかも失敗か成功かは写真を撮ってからでなければ分からない。
ロザリンドの時代、何年もの間、毎日毎日毎日毎日、何度も何度も何度も何度も、強烈な放射線を浴びながら、周囲からは「ダークレディ」などと罵声を浴びせられながらの作業である。
その結果、会心の一枚が撮れた。
けれど、その画像が何を意味するのか、そこまでは分からない。
で、同僚のウィルキンスに見せて相談した。
ウィルキンスはワトソンとクリックにも見せて検討した。
電子顕微鏡のあの画像はデータを可視化しただけであって、実際にはすべて数値である。
電子がどのようにぶつかり、跳ね返り、あるいは吸収されたかという、膨大なデータがそこにある。
ワトソンとクリックはそれに取り組み、DNAは二重らせん構造であるという結論を出した。
今ではこの業績は生物学の「セントラルドグマ」と呼ばれるほどの偉大な仕事だとされているが、発表された当時は何の反響も呼ばなかった。
ところが次第にこの仕事の重要さが知られるようになり、ダーウィンの進化論、メンデルの遺伝学、そしてDNAの二重らせん構造とが結びついて、現代の生物学の基礎が築かれることになる。
当然、ワトソン、クリック、ウィルキンスの三人には1962年(昭和37年、私の生まれた年である)ノーベル生理学・医学賞が与えられた。
あれ?
ロザリンドは?
実は、彼女は1958年に卵巣ガンで、37歳の若さで亡くなっていたのである。
もちろん、電子顕微鏡との関連など分からない。
ただ、彼女の撮ったDNAの写真がなければこの三人のノーベル賞受賞はなかったし、生物学の歩みも少し違ったものになっていただろう。
とにかくこの世は、長生きしたもの勝ちである。
ノーベル賞も例外ではないということだ。
そりゃ、長生きでしょう。
とにかく、選考委員としては「誤報」だけは避けたい。
「間違いでした」では済まないし、後々論争の種になるようなこともしたくない。
だから確定した業績、だれもケチをつけてこない仕事にだけ与えるようになる。
何十年も前の、今では学会の常識となった仕事を探して、恭しく授与する。
結果、とっくに盛りを過ぎた、ハッキリ言って「元」研究者ばかりが莫大な賞金を手にすることになる。
逆に、若く、この、たった今、資金が必要な研究者は置き去りである。
これでいいのか?
良くないから、受賞者は賞金を寄付したりするのだが、それっておかしくはないか、と思う。
私がこの時期、いつも思うのは、DNAである。
DNAの二重らせん構造を解明したのはワトソン、クリック、ウィルキンスの三人であり、当然、ノーベル賞が与えられたのだが、実はこの三人、DNA構造の解析に繋がる写真を撮った訳ではない。
有名な、あのボーッとしたX線写真、このどこが二重らせんなんですか、と言いたくなる電子顕微鏡写真を撮ったのは、この三人ではなく、ロザリンド・フランクリンという、三人の同僚の女性科学者だった。
とにかく頑張り屋さんで、今で言えばおそらく発達障害の、人付き合いの苦手な、のちのワトソンから「ダークレディ」と呼ばれるような研究者である。
当時、放射線への知識は貧弱で、放射性物質に関わる研究者が若くしてバタバタとガンで亡くなっていっても、その原因など考えてみようともしない。
あのキューリー夫人など、素手でラジウムを触っていたというのだ。
それと死因であるガンを結びつけるのは早計だと言われもするが、そういう誰も素手でラジウムを触ろうとはしない。
ロザリンドの時代も、X線を無防備にガンガン使う当時の電子顕微鏡に張り付いていれば若い女性の体に何が起こるか、今では誰もが心配するだろう。
私も学生時代、電子顕微鏡は何度も使ったから分かるのだが、DNAの写真を撮ると一言で言うが、そう簡単なことではない。
そもそも細胞の中のどれがDNAであるか特定しないといけないし、それを分離しないといけないし、そしてそれがきちんと写るように配置しなければならない。
構造解析の元となる写真を撮ることが、そもそも至難の業なのである。
しかも失敗か成功かは写真を撮ってからでなければ分からない。
ロザリンドの時代、何年もの間、毎日毎日毎日毎日、何度も何度も何度も何度も、強烈な放射線を浴びながら、周囲からは「ダークレディ」などと罵声を浴びせられながらの作業である。
その結果、会心の一枚が撮れた。
けれど、その画像が何を意味するのか、そこまでは分からない。
で、同僚のウィルキンスに見せて相談した。
ウィルキンスはワトソンとクリックにも見せて検討した。
電子顕微鏡のあの画像はデータを可視化しただけであって、実際にはすべて数値である。
電子がどのようにぶつかり、跳ね返り、あるいは吸収されたかという、膨大なデータがそこにある。
ワトソンとクリックはそれに取り組み、DNAは二重らせん構造であるという結論を出した。
今ではこの業績は生物学の「セントラルドグマ」と呼ばれるほどの偉大な仕事だとされているが、発表された当時は何の反響も呼ばなかった。
ところが次第にこの仕事の重要さが知られるようになり、ダーウィンの進化論、メンデルの遺伝学、そしてDNAの二重らせん構造とが結びついて、現代の生物学の基礎が築かれることになる。
当然、ワトソン、クリック、ウィルキンスの三人には1962年(昭和37年、私の生まれた年である)ノーベル生理学・医学賞が与えられた。
あれ?
ロザリンドは?
実は、彼女は1958年に卵巣ガンで、37歳の若さで亡くなっていたのである。
もちろん、電子顕微鏡との関連など分からない。
ただ、彼女の撮ったDNAの写真がなければこの三人のノーベル賞受賞はなかったし、生物学の歩みも少し違ったものになっていただろう。
とにかくこの世は、長生きしたもの勝ちである。
ノーベル賞も例外ではないということだ。
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
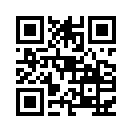
アクセスカウンタ
読者登録




