2019年09月26日
伊佐山紫文403
レイチェル・カーソンについてやるからには、エコロジズムについて最新の情報を得なければならぬとて、関連の書籍を読んでいる。
カーソン当時の環境思想を垂れ流すだけではお話にもならないし、私が生きた前世紀のエコロジズムは今となってはカルトでしかない。
それで、今現在のエコロジズムとはどんなものかと、諸文献を漁っている。
ところが、読めば読むほど、ほとんどの文献が事実の裏付けを欠いた、思い込みだけのものだと分かってきた。
まあ、そりゃそうだ。
地球規模の気候変動など、仮説は立てられるが、検証のしようもない。
そして、検証のしようのない「仮説」がまるで真理としてまかり通っているのがこの世界なのだ。
たとえば地球温暖化などと言うが、これが人間活動の影響かどうかは、はっきり言って分からない。
少なくとも、断言できる人間は科学者ではない。
そもそも、地球の気温は公転軌道によって決まり、それによって氷河期と間氷期を繰り返してきた。
人類の文明など、たまたまの間氷期に生まれた、たった直近数千年のものでしかない。
ましてや化石燃料云々など、数百年のデータでしかない。
これからの地球がさらなる温暖期に向かうか、それとも氷河期に戻るのか、それを決めるのは公転軌道であって、人類ではない。
温暖期に向かえば全ての氷河と南極の氷は溶け、海水面は数十メートル上昇して今の文明は滅ぶ。
氷河期になれば亜寒帯と温帯に集中している今の文明はすべて滅ぶ。
それだけの話。
どちらになるか、すべては公転軌道が決めることであって、人類がどうとか出来るような話では決してない。
それでも、人類そのものが滅ぶことは絶対にない。
この地球の気候変動に耐えて生き延びてきたのが、他ならぬ人類なのだから。
今の文明ではない、他の、私たちが想像も出来ない文明を人類は生み出すだろう。
だから、今は、地球のために私たちが出来ること、などという傲慢を去り、まずは謙虚に、自らの無力を悟ることだ。
そして無力を知りながら、ささやかな、身の回りの環境を考えて楽しく暮らす。
私たちに出来るのは、そんな程度のものでしかないと思う。
地球のため? 人間ごときがふざけるな、と地球は思っているだろう。
カーソン当時の環境思想を垂れ流すだけではお話にもならないし、私が生きた前世紀のエコロジズムは今となってはカルトでしかない。
それで、今現在のエコロジズムとはどんなものかと、諸文献を漁っている。
ところが、読めば読むほど、ほとんどの文献が事実の裏付けを欠いた、思い込みだけのものだと分かってきた。
まあ、そりゃそうだ。
地球規模の気候変動など、仮説は立てられるが、検証のしようもない。
そして、検証のしようのない「仮説」がまるで真理としてまかり通っているのがこの世界なのだ。
たとえば地球温暖化などと言うが、これが人間活動の影響かどうかは、はっきり言って分からない。
少なくとも、断言できる人間は科学者ではない。
そもそも、地球の気温は公転軌道によって決まり、それによって氷河期と間氷期を繰り返してきた。
人類の文明など、たまたまの間氷期に生まれた、たった直近数千年のものでしかない。
ましてや化石燃料云々など、数百年のデータでしかない。
これからの地球がさらなる温暖期に向かうか、それとも氷河期に戻るのか、それを決めるのは公転軌道であって、人類ではない。
温暖期に向かえば全ての氷河と南極の氷は溶け、海水面は数十メートル上昇して今の文明は滅ぶ。
氷河期になれば亜寒帯と温帯に集中している今の文明はすべて滅ぶ。
それだけの話。
どちらになるか、すべては公転軌道が決めることであって、人類がどうとか出来るような話では決してない。
それでも、人類そのものが滅ぶことは絶対にない。
この地球の気候変動に耐えて生き延びてきたのが、他ならぬ人類なのだから。
今の文明ではない、他の、私たちが想像も出来ない文明を人類は生み出すだろう。
だから、今は、地球のために私たちが出来ること、などという傲慢を去り、まずは謙虚に、自らの無力を悟ることだ。
そして無力を知りながら、ささやかな、身の回りの環境を考えて楽しく暮らす。
私たちに出来るのは、そんな程度のものでしかないと思う。
地球のため? 人間ごときがふざけるな、と地球は思っているだろう。
2019年09月26日
伊佐山紫文403
レイチェル・カーソンについてやるからには、エコロジズムについて最新の情報を得なければならぬとて、関連の書籍を読んでいる。
カーソン当時の環境思想を垂れ流すだけではお話にもならないし、私が生きた前世紀のエコロジズムは今となってはカルトでしかない。
それで、今現在のエコロジズムとはどんなものかと、諸文献を漁っている。
ところが、読めば読むほど、ほとんどの文献が事実の裏付けを欠いた、思い込みだけのものだと分かってきた。
まあ、そりゃそうだ。
地球規模の気候変動など、仮説は立てられるが、検証のしようもない。
そして、検証のしようのない「仮説」がまるで真理としてまかり通っているのがこの世界なのだ。
たとえば地球温暖化などと言うが、これが人間活動の影響かどうかは、はっきり言って分からない。
少なくとも、断言できる人間は科学者ではない。
そもそも、地球の気温は公転軌道によって決まり、それによって氷河期と間氷期を繰り返してきた。
人類の文明など、たまたまの間氷期に生まれた、たった直近数千年のものでしかない。
ましてや化石燃料云々など、数百年のデータでしかない。
これからの地球がさらなる温暖期に向かうか、それとも氷河期に戻るのか、それを決めるのは公転軌道であって、人類ではない。
温暖期に向かえば全ての氷河と南極の氷は溶け、海水面は数十メートル上昇して今の文明は滅ぶ。
氷河期になれば亜寒帯と温帯に集中している今の文明はすべて滅ぶ。
それだけの話。
どちらになるか、すべては公転軌道が決めることであって、人類がどうとか出来るような話では決してない。
それでも、人類そのものが滅ぶことは絶対にない。
この地球の気候変動に耐えて生き延びてきたのが、他ならぬ人類なのだから。
今の文明ではない、他の、私たちが想像も出来ない文明を人類は生み出すだろう。
だから、今は、地球のために私たちが出来ること、などという傲慢を去り、まずは謙虚に、自らの無力を悟ることだ。
そして無力を知りながら、ささやかな、身の回りの環境を考えて楽しく暮らす。
私たちに出来るのは、そんな程度のものでしかないと思う。
地球のため? 人間ごときがふざけるな、と地球は思っているだろう。
カーソン当時の環境思想を垂れ流すだけではお話にもならないし、私が生きた前世紀のエコロジズムは今となってはカルトでしかない。
それで、今現在のエコロジズムとはどんなものかと、諸文献を漁っている。
ところが、読めば読むほど、ほとんどの文献が事実の裏付けを欠いた、思い込みだけのものだと分かってきた。
まあ、そりゃそうだ。
地球規模の気候変動など、仮説は立てられるが、検証のしようもない。
そして、検証のしようのない「仮説」がまるで真理としてまかり通っているのがこの世界なのだ。
たとえば地球温暖化などと言うが、これが人間活動の影響かどうかは、はっきり言って分からない。
少なくとも、断言できる人間は科学者ではない。
そもそも、地球の気温は公転軌道によって決まり、それによって氷河期と間氷期を繰り返してきた。
人類の文明など、たまたまの間氷期に生まれた、たった直近数千年のものでしかない。
ましてや化石燃料云々など、数百年のデータでしかない。
これからの地球がさらなる温暖期に向かうか、それとも氷河期に戻るのか、それを決めるのは公転軌道であって、人類ではない。
温暖期に向かえば全ての氷河と南極の氷は溶け、海水面は数十メートル上昇して今の文明は滅ぶ。
氷河期になれば亜寒帯と温帯に集中している今の文明はすべて滅ぶ。
それだけの話。
どちらになるか、すべては公転軌道が決めることであって、人類がどうとか出来るような話では決してない。
それでも、人類そのものが滅ぶことは絶対にない。
この地球の気候変動に耐えて生き延びてきたのが、他ならぬ人類なのだから。
今の文明ではない、他の、私たちが想像も出来ない文明を人類は生み出すだろう。
だから、今は、地球のために私たちが出来ること、などという傲慢を去り、まずは謙虚に、自らの無力を悟ることだ。
そして無力を知りながら、ささやかな、身の回りの環境を考えて楽しく暮らす。
私たちに出来るのは、そんな程度のものでしかないと思う。
地球のため? 人間ごときがふざけるな、と地球は思っているだろう。
2019年09月26日
伊佐山紫文402
『バイオフィリア 人間と生物の絆』
E・O・ウィルソン著 狩野秀之訳
ちくま学芸文庫
大著『社会生物学』を上梓して大論争を巻き起こし、忽然と自らのフィールドであるジャングルに消えた進化生物学者E・O・ウィルソンが、今度は極めて穏やかな口調で、格調高く自然保護思想を説いた小著。
なぜ「自然」は、「種」は、そして「生命多様性」は保護されなければならないのか。
本書のどこにも明確な答えはない。
ただ、人間の本性として、生物への愛「バイオフィリア」というものがあるのではないか、と静かに問いかける。
訳者が「文庫版への訳者あとがき」でも述べられているように、この「バイオフィリア」という語は、最近『愛するということ』の新訳が出て再び注目されている、エーリッヒ・フロムの『悪について』の「バイオフィリア」とは全く意味が違う。
フロムの「バイオフィリア」は「ネクロフィリア(死への志向性)」の対語で、「生への志向性」とでも訳すべきもの、背景には心理学者らしくフロイトの「死の欲動」と「生の欲動」があり、だから単独では意味を成さない。
著者も本文で言うように、ウィルソンの「バイオフィリア」の背景にあるのはイーフー・トゥアンの『トポフィリア』である。
とにかく人間には懐かしくてたまらない場所があり、そのような感情をトゥアンは「トポフィリア(場所への愛)」と呼んだ。
とにかくそのような性向が人間にはあるのだ、と。
これは何かと対になった概念ではない。
ウィルソンの「バイオフィリア」もそうで、例えば犬や猫を眺めて思わず笑みをこぼしてしまうような、どうしようもない性向が人間にはある。
そこをベースに自然保護の倫理を構築すべきだと、困難な道を承知で主張する。
小さな、静かな、そして力強い主張に満ちた一冊である。
E・O・ウィルソン著 狩野秀之訳
ちくま学芸文庫
大著『社会生物学』を上梓して大論争を巻き起こし、忽然と自らのフィールドであるジャングルに消えた進化生物学者E・O・ウィルソンが、今度は極めて穏やかな口調で、格調高く自然保護思想を説いた小著。
なぜ「自然」は、「種」は、そして「生命多様性」は保護されなければならないのか。
本書のどこにも明確な答えはない。
ただ、人間の本性として、生物への愛「バイオフィリア」というものがあるのではないか、と静かに問いかける。
訳者が「文庫版への訳者あとがき」でも述べられているように、この「バイオフィリア」という語は、最近『愛するということ』の新訳が出て再び注目されている、エーリッヒ・フロムの『悪について』の「バイオフィリア」とは全く意味が違う。
フロムの「バイオフィリア」は「ネクロフィリア(死への志向性)」の対語で、「生への志向性」とでも訳すべきもの、背景には心理学者らしくフロイトの「死の欲動」と「生の欲動」があり、だから単独では意味を成さない。
著者も本文で言うように、ウィルソンの「バイオフィリア」の背景にあるのはイーフー・トゥアンの『トポフィリア』である。
とにかく人間には懐かしくてたまらない場所があり、そのような感情をトゥアンは「トポフィリア(場所への愛)」と呼んだ。
とにかくそのような性向が人間にはあるのだ、と。
これは何かと対になった概念ではない。
ウィルソンの「バイオフィリア」もそうで、例えば犬や猫を眺めて思わず笑みをこぼしてしまうような、どうしようもない性向が人間にはある。
そこをベースに自然保護の倫理を構築すべきだと、困難な道を承知で主張する。
小さな、静かな、そして力強い主張に満ちた一冊である。
2019年09月26日
伊佐山紫文401
私が学生時代だから、もう1980年代のいつかだと思うが『西暦2000年の地球』という二巻本のいかつい本が出て、それも発行者が「アメリカ合衆国政府」で、その「特別調査報告」とあっては、信頼性も抜群、このままではこの世は確実に滅ぶ、と、若かった私はノストラダムス級の衝撃を受けた。
それ以前にも、「ローマクラブ」の『成長の限界』という恐ろしい本も出ていて、これと『西暦2000年の地球』の衝撃とで、若かった私は、この世は確実にエコロジカルな問題で滅ぶと確信したものだった。
40半ばまで子どもを作らなかったのも、この確信があったからで、一体誰が、滅ぶと分かっている世に我が子を送り出したいか。
まあ、全ては夢かまぼろしで、この時代の環境問題など、鎌倉時代に蔓延した末法思想のようなもの。
「公害」はもはや一時代前の死語になっていたし、現実の世はバブルに浮かれ始めていた。
まさに『なんとなく、クリスタル』の時代で、共に浮かれ得ない陰気な連中を捉えたのが、新たな末法思想である「環境問題」だったのだ。
私はそれにドンピシャで捉えられた。
エコロジーこそ真理であり、これに逆らうものは全て滅ぶ。
今思えば狂気でしかない。
が、狂気によってしか変わらぬ世もある。
この世が当時より良くなっているとすれば、と言うより、確実に良くなっているのだが、その動力は狂気である。
そういうことも客観的に見られるような歳になってしまった。
それ以前にも、「ローマクラブ」の『成長の限界』という恐ろしい本も出ていて、これと『西暦2000年の地球』の衝撃とで、若かった私は、この世は確実にエコロジカルな問題で滅ぶと確信したものだった。
40半ばまで子どもを作らなかったのも、この確信があったからで、一体誰が、滅ぶと分かっている世に我が子を送り出したいか。
まあ、全ては夢かまぼろしで、この時代の環境問題など、鎌倉時代に蔓延した末法思想のようなもの。
「公害」はもはや一時代前の死語になっていたし、現実の世はバブルに浮かれ始めていた。
まさに『なんとなく、クリスタル』の時代で、共に浮かれ得ない陰気な連中を捉えたのが、新たな末法思想である「環境問題」だったのだ。
私はそれにドンピシャで捉えられた。
エコロジーこそ真理であり、これに逆らうものは全て滅ぶ。
今思えば狂気でしかない。
が、狂気によってしか変わらぬ世もある。
この世が当時より良くなっているとすれば、と言うより、確実に良くなっているのだが、その動力は狂気である。
そういうことも客観的に見られるような歳になってしまった。
2019年09月26日
伊佐山紫文400
筑後川は日田では三隈川(みくまがわ)と名前を変える。
玖珠川(くすがわ)と大山川の合流点から夜明ダムまでの日田市内では、筑後川は三隈川と呼ばれるのである。
その三隈川の支流に花月川がある。
小野川と有田川が合流し、三隈川に流れ込むまでのほんの数キロの川である。
そんな花月川の中流域に簡単なダムで流れをせき止めた水出淵(すいでぶち)なる瀞(とろ)があって、少年時代、ここが私のもっぱらな釣り場だった。
小学生の頃はフナを釣ったし、秋には鯉も上がった。
中学生になりルアー釣りを覚えてからはナマズをガシュガシュ釣った。
不思議なことに、三隈川には普通にいたイダ(ウグイ)が花月川では見られなかった。
鮎もそう。
花月川にはいなかった。
エノハ(ヤマメ)もそうで、三隈川の他の支流、大山川や高瀬川では普通に釣れたのに、花月川系の支流では全く見られない。
水質が関係しているのか、地形の問題か、何か他に理由があるのか、高校生の頃、どうにか研究する手段はないのか、色々と考えていた。
その後、大学院を中退し、研究生活から遠ざかって二十数年、久しぶりに水出淵に釣り糸を落とすと、なんと、次から次にイダ(ウグイ)がかかるわ、かかるわ。
調べれば、放流した琵琶湖の鮎に紛れてウグイが生息域を広げているのだという。
花月川系の小野川にも放流されたヤマメ釣り場が整備されているという。
これで、ウグイやヤマメや鮎の分布の理由を解明するという、私の研究の機会は永遠に失われた。
これも自然破壊の一種ではないのか。
などと、若い頃の私なら思ったかも知れないが、今はもう、仕方ないと諦念している。
人間と自然の関わりとはこんなものなんだし、と。
最近、レイチェル・カーソンにからんで現代のエコロジズムについて調べつつ、自らの自然との関わりについて内省している。
ちなみに昨年、バスの車窓から眺めた水出淵はなんともモダンな堰に姿を変えていた。
これもまた時代の流れ、仕方ない。
玖珠川(くすがわ)と大山川の合流点から夜明ダムまでの日田市内では、筑後川は三隈川と呼ばれるのである。
その三隈川の支流に花月川がある。
小野川と有田川が合流し、三隈川に流れ込むまでのほんの数キロの川である。
そんな花月川の中流域に簡単なダムで流れをせき止めた水出淵(すいでぶち)なる瀞(とろ)があって、少年時代、ここが私のもっぱらな釣り場だった。
小学生の頃はフナを釣ったし、秋には鯉も上がった。
中学生になりルアー釣りを覚えてからはナマズをガシュガシュ釣った。
不思議なことに、三隈川には普通にいたイダ(ウグイ)が花月川では見られなかった。
鮎もそう。
花月川にはいなかった。
エノハ(ヤマメ)もそうで、三隈川の他の支流、大山川や高瀬川では普通に釣れたのに、花月川系の支流では全く見られない。
水質が関係しているのか、地形の問題か、何か他に理由があるのか、高校生の頃、どうにか研究する手段はないのか、色々と考えていた。
その後、大学院を中退し、研究生活から遠ざかって二十数年、久しぶりに水出淵に釣り糸を落とすと、なんと、次から次にイダ(ウグイ)がかかるわ、かかるわ。
調べれば、放流した琵琶湖の鮎に紛れてウグイが生息域を広げているのだという。
花月川系の小野川にも放流されたヤマメ釣り場が整備されているという。
これで、ウグイやヤマメや鮎の分布の理由を解明するという、私の研究の機会は永遠に失われた。
これも自然破壊の一種ではないのか。
などと、若い頃の私なら思ったかも知れないが、今はもう、仕方ないと諦念している。
人間と自然の関わりとはこんなものなんだし、と。
最近、レイチェル・カーソンにからんで現代のエコロジズムについて調べつつ、自らの自然との関わりについて内省している。
ちなみに昨年、バスの車窓から眺めた水出淵はなんともモダンな堰に姿を変えていた。
これもまた時代の流れ、仕方ない。
2019年09月22日
伊佐山紫文398
『ケーキの切れない非行少年たち』
宮口幸治 新潮新書
昨日紹介した『発達障害と少年犯罪』に触発されて書かれた一冊。
「コグトレ」が具体的に紹介されている。
『発達障害と少年犯罪』が主に「発達障害」に焦点が当てられているのに対し、本書では「知的障害」について詳しく記述されている。
発達障害と同様、知的障害も犯罪とは無縁ではない。
むしろ、支援の必要な知的障害者が放っておかれ、犯罪者になってしまうケースが多いのではないかという。
ダマシオの『デカルトの誤り』やイーグルマンの諸著作と合わせ読めばさらに理解も深まるだろう。
宮口幸治 新潮新書
昨日紹介した『発達障害と少年犯罪』に触発されて書かれた一冊。
「コグトレ」が具体的に紹介されている。
『発達障害と少年犯罪』が主に「発達障害」に焦点が当てられているのに対し、本書では「知的障害」について詳しく記述されている。
発達障害と同様、知的障害も犯罪とは無縁ではない。
むしろ、支援の必要な知的障害者が放っておかれ、犯罪者になってしまうケースが多いのではないかという。
ダマシオの『デカルトの誤り』やイーグルマンの諸著作と合わせ読めばさらに理解も深まるだろう。
2019年09月22日
伊佐山紫文398
『あなたの脳のはなし 神経科学者が解き明かす意識の謎』
デイヴィッド・イーグルマン 大田直子訳
ハヤカワノンフィクション文庫
最近、よく、近未来では脳の情報をコンピューター上にアップロードしシミュレーションによって不死となる、などのお話がしたり顔で語られることが多い。
実際、本書でもその「可能性」について語られてはいるのだが、そして啓蒙的な科学者としてその「可能性」の条件について考察しているのだが、どう考えても無理であり、無意味である。
と言うか、そもそもあなたの脳の中に、あなたの意識という実体的な「何か」は存在しない。
せめぎ合う欲動のごうごうたる流れがあるだけだ。
存在しない「何か」をどこかへ移し替えることは出来ないし、しかも本書で繰り返し説明されるように、意識は身体と不可分であり、しかも社会との相互作用によって成立している。
つまり意識をシミュレーションするためには、身体と同時に社会を丸ごとシミュレーションする必要があり、それはこの世をもう一つ複製すると言うことである。
いかに馬鹿げた話か分かろうものだ。
テレビの啓蒙番組を元に作られただけあって、非常にわかりやすい。
朝に紹介した『発達障害と少年犯罪』と合わせ読めば、双方の理解が深まるだろう。
デイヴィッド・イーグルマン 大田直子訳
ハヤカワノンフィクション文庫
最近、よく、近未来では脳の情報をコンピューター上にアップロードしシミュレーションによって不死となる、などのお話がしたり顔で語られることが多い。
実際、本書でもその「可能性」について語られてはいるのだが、そして啓蒙的な科学者としてその「可能性」の条件について考察しているのだが、どう考えても無理であり、無意味である。
と言うか、そもそもあなたの脳の中に、あなたの意識という実体的な「何か」は存在しない。
せめぎ合う欲動のごうごうたる流れがあるだけだ。
存在しない「何か」をどこかへ移し替えることは出来ないし、しかも本書で繰り返し説明されるように、意識は身体と不可分であり、しかも社会との相互作用によって成立している。
つまり意識をシミュレーションするためには、身体と同時に社会を丸ごとシミュレーションする必要があり、それはこの世をもう一つ複製すると言うことである。
いかに馬鹿げた話か分かろうものだ。
テレビの啓蒙番組を元に作られただけあって、非常にわかりやすい。
朝に紹介した『発達障害と少年犯罪』と合わせ読めば、双方の理解が深まるだろう。
2019年09月22日
伊佐山紫文397
『発達障害と少年犯罪』
田淵俊彦 NNNドキュメント取材班 新潮新書
誰もが気づいていながら、誰も触れたがらない、そして「心の闇」などと、訳の分からない非科学的な修辞に押し込んでしまう現実がある。
それは「障害」と「犯罪」の関連である。
この関連を認めてしまうと、障害者=犯罪者という図式が成立してしまい、差別を助長しかねないという空気が、現在の言論空間を支配している。
ましてや「発達障害」と「少年犯罪」を「と」で繋ぐなど、問題外の外、論外の外である。
絶対にやってはいけないことであって、やろうとするような人間は社会から排除すべきだし、実際、排除されてきた。
しかし、統計は残酷だ。
本書が示すように、「発達障害」と「少年犯罪」は明らかにリンクしている。
実は、我が子が3歳になっても一言も発せず、医師からは自閉症を疑われて、私なりに「発達障害」について調べたことがあった。
そうしたら、日本語で読める文献のなんと貧弱なことよ。
そしてデタラメなこと。
結局はほとんどの文献をアメリカを中心とした英語圏から取り寄せることになった。
本書を批判する人々は取材対象の偏りを云々するが、実際、日本で本気でこの問題に取り組んでいるのは本書に登場する人々くらいのものなのだ。
もちろん、研究者はいる。
けれど、それらの研究者のほとんどは、アメリカの制度には関心があっても、日本の子供たちには何の興味も示さない。
私の相談にも「まずは原因を探りましょう」などと、アホなことを言って返す。
「原因」など分かりきっている。
高濃度テストステロン脳症ですよ。
それに、父親としてのこの私が、妊娠時44歳という高齢だったのも影響していることは確実です。
だから、それより問題は、この子をどう育てるか、と言うことです。
とにかく、誰に聞いても、
「問題が出てから考えましょう」
問題が出てからじゃ遅いんですけど!
本書の著者も、当人がすでに気づいているように、恐らく発達障害を抱えて生きて来た一人である。
そして私も間違いなくそうである。
著者が言うように、そして私もそうであるように、堀の内に落ちなかったのはただの偶然や幸運に過ぎない。
問題は、だから「発達障害」を持つ子供たちが「少年犯罪」に至らないようにするために何が出来るか、である。
本書で紹介されているメソッドはまだ端緒についたばかりで、なんとも評価はしかねるが、試行錯誤として有意義であることは確かであろう。
本書の記述は最新の脳科学の知見にも裏付けられており、デイヴィッド・イーグルマンの諸著作(『あなたの知らない脳』『あなたの脳のはなし』共にハヤカワノンフィクション文庫)と合わせ読めば更に理解も深まるだろう。
田淵俊彦 NNNドキュメント取材班 新潮新書
誰もが気づいていながら、誰も触れたがらない、そして「心の闇」などと、訳の分からない非科学的な修辞に押し込んでしまう現実がある。
それは「障害」と「犯罪」の関連である。
この関連を認めてしまうと、障害者=犯罪者という図式が成立してしまい、差別を助長しかねないという空気が、現在の言論空間を支配している。
ましてや「発達障害」と「少年犯罪」を「と」で繋ぐなど、問題外の外、論外の外である。
絶対にやってはいけないことであって、やろうとするような人間は社会から排除すべきだし、実際、排除されてきた。
しかし、統計は残酷だ。
本書が示すように、「発達障害」と「少年犯罪」は明らかにリンクしている。
実は、我が子が3歳になっても一言も発せず、医師からは自閉症を疑われて、私なりに「発達障害」について調べたことがあった。
そうしたら、日本語で読める文献のなんと貧弱なことよ。
そしてデタラメなこと。
結局はほとんどの文献をアメリカを中心とした英語圏から取り寄せることになった。
本書を批判する人々は取材対象の偏りを云々するが、実際、日本で本気でこの問題に取り組んでいるのは本書に登場する人々くらいのものなのだ。
もちろん、研究者はいる。
けれど、それらの研究者のほとんどは、アメリカの制度には関心があっても、日本の子供たちには何の興味も示さない。
私の相談にも「まずは原因を探りましょう」などと、アホなことを言って返す。
「原因」など分かりきっている。
高濃度テストステロン脳症ですよ。
それに、父親としてのこの私が、妊娠時44歳という高齢だったのも影響していることは確実です。
だから、それより問題は、この子をどう育てるか、と言うことです。
とにかく、誰に聞いても、
「問題が出てから考えましょう」
問題が出てからじゃ遅いんですけど!
本書の著者も、当人がすでに気づいているように、恐らく発達障害を抱えて生きて来た一人である。
そして私も間違いなくそうである。
著者が言うように、そして私もそうであるように、堀の内に落ちなかったのはただの偶然や幸運に過ぎない。
問題は、だから「発達障害」を持つ子供たちが「少年犯罪」に至らないようにするために何が出来るか、である。
本書で紹介されているメソッドはまだ端緒についたばかりで、なんとも評価はしかねるが、試行錯誤として有意義であることは確かであろう。
本書の記述は最新の脳科学の知見にも裏付けられており、デイヴィッド・イーグルマンの諸著作(『あなたの知らない脳』『あなたの脳のはなし』共にハヤカワノンフィクション文庫)と合わせ読めば更に理解も深まるだろう。
2019年09月22日
伊佐山紫文396
高度経済成長期の列島改造を自然破壊と呼ぶかどうかはその人の価値判断によるのだろうし、そもそも人間にとって「自然」って何? って話でもある。
日田の私の家の前を流れていた小川・中城川は、そもそも材木を運ぶための運河で、自然でも何でもない、人間の人間による人間のための構築物にすぎない。
だが、そこに住むオイカワやタナゴやカワニナはどうなのか。
私にとっては紛れもない「自然」だったし、味噌汁の出汁となるカワニナなど、もはや体の一部だった。
それが高度経済成長で一変した。
まだ小川の体を成していた運河は、三面がコンクリートで貼られ、まさに水を流すだけの水路となった。
下水道など整備されるのはずっとあとのこと。
清流はただのドブになった。
確かに小川だった頃は、大雨のたびに溢れて玄関に下駄を浮かべたり、酷いときは便所と井戸が繋がって赤痢や疫痢が蔓延したりした。
保健所から来た白い服のおじさんたちが消毒薬を撒く光景は日常でもあった。
あの頃になど、決して戻れるものではない。
もちろん今では下水道も整備され、水質は改善してユスリカの大量発生などはなくなったし、コンクリートの三面張りも、若い人たちにはこれはこれで風情なのかも知れない。
そもそも、全てが「自然」ではないのだから、どのような光景に情緒を感じるのかは個人的な主観でしかない。
のだろうか?
という疑問を最近抱くようになった。
人間の、と言って大げさなら、日本人の原風景とでも言うべき「自然」があるのではないか。
近代的な「個人」の主観に還元されない「自然」というものが、私たちの心の根っこにはあるのではないか。
今では、そんなことを考えている。
日田の私の家の前を流れていた小川・中城川は、そもそも材木を運ぶための運河で、自然でも何でもない、人間の人間による人間のための構築物にすぎない。
だが、そこに住むオイカワやタナゴやカワニナはどうなのか。
私にとっては紛れもない「自然」だったし、味噌汁の出汁となるカワニナなど、もはや体の一部だった。
それが高度経済成長で一変した。
まだ小川の体を成していた運河は、三面がコンクリートで貼られ、まさに水を流すだけの水路となった。
下水道など整備されるのはずっとあとのこと。
清流はただのドブになった。
確かに小川だった頃は、大雨のたびに溢れて玄関に下駄を浮かべたり、酷いときは便所と井戸が繋がって赤痢や疫痢が蔓延したりした。
保健所から来た白い服のおじさんたちが消毒薬を撒く光景は日常でもあった。
あの頃になど、決して戻れるものではない。
もちろん今では下水道も整備され、水質は改善してユスリカの大量発生などはなくなったし、コンクリートの三面張りも、若い人たちにはこれはこれで風情なのかも知れない。
そもそも、全てが「自然」ではないのだから、どのような光景に情緒を感じるのかは個人的な主観でしかない。
のだろうか?
という疑問を最近抱くようになった。
人間の、と言って大げさなら、日本人の原風景とでも言うべき「自然」があるのではないか。
近代的な「個人」の主観に還元されない「自然」というものが、私たちの心の根っこにはあるのではないか。
今では、そんなことを考えている。
2019年09月22日
伊佐山紫文395
私が理学部出身で、専攻が魚類学だと聞くと、たいていの人が驚いた顔をする。
確かに、大学院を中退してからの道行きは、専攻とは全く違うものだったから、意外ととられるかも知れない。
それでも、私の中ではちゃんと一本の筋が通っていた。
それは「エコロジー」である。
訳せば「生態学」とか、「自然保護」とか、「環境保全」とか、いろいろな言葉になるんだろうが、とにかく、自然の中の人間を意識する、みたいな、ボヤッとした意味である。
私が物心つき始めた頃は、高度経済成長、日本列島改造の真っ最中で、エコロジーなど完全無視のエコノミー(経済)優先、家の前の小川が化けた3面コンクリート張りの運河からは合成洗剤の泡が立ちのぼり、清流のカゲロウに代わり、汚水に強いユスリカが大量発生したりした。
改造前の小川に親しんでいた私は、この世の流れに強烈な憤りを感じた。
エコノミーより、エコロジーだろ、と。
そんな私は、高校時代は科学部に入って日田市内の河川の汚染状況を調べ、各種の賞を取ったし、博物館の年報に論文が掲載されたりもした。
その流れで、進学先は愛媛大学の理学部生物学科を選んだ。
当時、淡水の生態学ではここが日本、と言うか、世界でもトップを走っていたから。
しかも、愛媛大学の農学部には環境学科があり、ダイオキシン研究では、ここも世界のトップを走っている。
生態学の原理的な理論を学びながら環境問題を考えるには、理想の大学だと思えたのだった。
若い、と言ってしまえば、それはそれ。
とにかく、エコロジーに明け暮れる学生時代をおくり、そのあげく、原発がらみで大学院を中退、流浪の日々を経て、KADOKAWAの雑誌に環境問題の連載を書かせてもらうことになった。
結局、私の原点はエコロジーだし、その意味で、次回公演
「レイチェル・カーソン やめなはれDDT!」
はその原点を見つめ直すものになるだろうと思っている。
もちろん、難しいものにはならない。
「クララ・シューマン 天才のヨメはん」
と同様、楽しいものにしたいと思っている。
乞うご期待。
確かに、大学院を中退してからの道行きは、専攻とは全く違うものだったから、意外ととられるかも知れない。
それでも、私の中ではちゃんと一本の筋が通っていた。
それは「エコロジー」である。
訳せば「生態学」とか、「自然保護」とか、「環境保全」とか、いろいろな言葉になるんだろうが、とにかく、自然の中の人間を意識する、みたいな、ボヤッとした意味である。
私が物心つき始めた頃は、高度経済成長、日本列島改造の真っ最中で、エコロジーなど完全無視のエコノミー(経済)優先、家の前の小川が化けた3面コンクリート張りの運河からは合成洗剤の泡が立ちのぼり、清流のカゲロウに代わり、汚水に強いユスリカが大量発生したりした。
改造前の小川に親しんでいた私は、この世の流れに強烈な憤りを感じた。
エコノミーより、エコロジーだろ、と。
そんな私は、高校時代は科学部に入って日田市内の河川の汚染状況を調べ、各種の賞を取ったし、博物館の年報に論文が掲載されたりもした。
その流れで、進学先は愛媛大学の理学部生物学科を選んだ。
当時、淡水の生態学ではここが日本、と言うか、世界でもトップを走っていたから。
しかも、愛媛大学の農学部には環境学科があり、ダイオキシン研究では、ここも世界のトップを走っている。
生態学の原理的な理論を学びながら環境問題を考えるには、理想の大学だと思えたのだった。
若い、と言ってしまえば、それはそれ。
とにかく、エコロジーに明け暮れる学生時代をおくり、そのあげく、原発がらみで大学院を中退、流浪の日々を経て、KADOKAWAの雑誌に環境問題の連載を書かせてもらうことになった。
結局、私の原点はエコロジーだし、その意味で、次回公演
「レイチェル・カーソン やめなはれDDT!」
はその原点を見つめ直すものになるだろうと思っている。
もちろん、難しいものにはならない。
「クララ・シューマン 天才のヨメはん」
と同様、楽しいものにしたいと思っている。
乞うご期待。
2019年09月22日
伊佐山紫文395
私が理学部出身で、専攻が魚類学だと聞くと、たいていの人が驚いた顔をする。
確かに、大学院を中退してからの道行きは、専攻とは全く違うものだったから、意外ととられるかも知れない。
それでも、私の中ではちゃんと一本の筋が通っていた。
それは「エコロジー」である。
訳せば「生態学」とか、「自然保護」とか、「環境保全」とか、いろいろな言葉になるんだろうが、とにかく、自然の中の人間を意識する、みたいな、ボヤッとした意味である。
私が物心つき始めた頃は、高度経済成長、日本列島改造の真っ最中で、エコロジーなど完全無視のエコノミー(経済)優先、家の前の小川が化けた3面コンクリート張りの運河からは合成洗剤の泡が立ちのぼり、清流のカゲロウに代わり、汚水に強いユスリカが大量発生したりした。
改造前の小川に親しんでいた私は、この世の流れに強烈な憤りを感じた。
エコノミーより、エコロジーだろ、と。
そんな私は、高校時代は科学部に入って日田市内の河川の汚染状況を調べ、各種の賞を取ったし、博物館の年報に論文が掲載されたりもした。
その流れで、進学先は愛媛大学の理学部生物学科を選んだ。
当時、淡水の生態学ではここが日本、と言うか、世界でもトップを走っていたから。
しかも、愛媛大学の農学部には環境学科があり、ダイオキシン研究では、ここも世界のトップを走っている。
生態学の原理的な理論を学びながら環境問題を考えるには、理想の大学だと思えたのだった。
若い、と言ってしまえば、それはそれ。
とにかく、エコロジーに明け暮れる学生時代をおくり、そのあげく、原発がらみで大学院を中退、流浪の日々を経て、KADOKAWAの雑誌に環境問題の連載を書かせてもらうことになった。
結局、私の原点はエコロジーだし、その意味で、次回公演
「レイチェル・カーソン やめなはれDDT!」
はその原点を見つめ直すものになるだろうと思っている。
もちろん、難しいものにはならない。
「クララ・シューマン 天才のヨメはん」
と同様、楽しいものにしたいと思っている。
乞うご期待。
確かに、大学院を中退してからの道行きは、専攻とは全く違うものだったから、意外ととられるかも知れない。
それでも、私の中ではちゃんと一本の筋が通っていた。
それは「エコロジー」である。
訳せば「生態学」とか、「自然保護」とか、「環境保全」とか、いろいろな言葉になるんだろうが、とにかく、自然の中の人間を意識する、みたいな、ボヤッとした意味である。
私が物心つき始めた頃は、高度経済成長、日本列島改造の真っ最中で、エコロジーなど完全無視のエコノミー(経済)優先、家の前の小川が化けた3面コンクリート張りの運河からは合成洗剤の泡が立ちのぼり、清流のカゲロウに代わり、汚水に強いユスリカが大量発生したりした。
改造前の小川に親しんでいた私は、この世の流れに強烈な憤りを感じた。
エコノミーより、エコロジーだろ、と。
そんな私は、高校時代は科学部に入って日田市内の河川の汚染状況を調べ、各種の賞を取ったし、博物館の年報に論文が掲載されたりもした。
その流れで、進学先は愛媛大学の理学部生物学科を選んだ。
当時、淡水の生態学ではここが日本、と言うか、世界でもトップを走っていたから。
しかも、愛媛大学の農学部には環境学科があり、ダイオキシン研究では、ここも世界のトップを走っている。
生態学の原理的な理論を学びながら環境問題を考えるには、理想の大学だと思えたのだった。
若い、と言ってしまえば、それはそれ。
とにかく、エコロジーに明け暮れる学生時代をおくり、そのあげく、原発がらみで大学院を中退、流浪の日々を経て、KADOKAWAの雑誌に環境問題の連載を書かせてもらうことになった。
結局、私の原点はエコロジーだし、その意味で、次回公演
「レイチェル・カーソン やめなはれDDT!」
はその原点を見つめ直すものになるだろうと思っている。
もちろん、難しいものにはならない。
「クララ・シューマン 天才のヨメはん」
と同様、楽しいものにしたいと思っている。
乞うご期待。
2019年09月22日
伊佐山紫文394
子育てをしていると、どうしても、息子と自分の少年時代とを重ねてしまう。
それは良いのだが、自分がして欲しかったことを息子にやろうとしてしまう。
ピアノ、書道、英語……
そりゃ、やっていれば、将来、なんかの役に立つだろうが、その「将来」とやらが、親にどれほど見通せているのかって話。
私は基本、放任の野放しだった。
親は悪しき戦後教育の産物で、子どもの自主性だの自由だのを奉じて、結局は無責任にほったらかした。
と言うより、まず父親は、この資本主義の世の中があと十年も続くとは思っていないものだから、子どもの教育よりもこの世の変革に情熱を注いだ。
「将来」の見通しがそもそも狂っていたのだ。
母親は、女学校始まって以来の才女と言われ、自分から勉強をする子だったので、まさか我が子が、言われなければ宿題もやらないとは思いもしなかった。
勝手にやってるだろうとチェックもしない。
で、学校に言われてキレる。
その繰り返し。
現実には、学校の宿題を家でやったことなど一度もなく、すべて居残りだった。
その頃(小4~小6)の担任は教員だった母の元同僚で、なまじ私の家庭事情を知っているものだから、敢えて介入することはなかった。
小3で、すでに教員を一人辞めさせた、前科のある子どもである。
しかも、親も親である。
とにかく関わるのも面倒くさい。
放っておけ。
今では、この人たちの気持ちが手に取るように分かる。
実は、息子が3歳になっても一言も発せず、これはおかしいと文献を漁りはじめ「ギフテッド」という存在にたどり着いた。
一言で言えば「才能を与えられた(ギフテッド)子」ということなのだが、この「才能」と言うのがやっかいで、決してこれを持たされた子に幸福をもたらすようなものではない。
息子の場合、パズルを解いたり、ものを組み立てたりするのは、同世代の子よりも圧倒的に勝っていたのだが、言葉が無い。
アインシュタインやファインマン、日本では湯川秀樹など、ノーベル賞をとるような物理学者が幼少期、言葉が遅かったことを心配されたことはよく知られていて、そこから調べて、おそらくは理系の「ギフテッド」だろうと当たりをつけた。
で、その過程で、我がことに思い至った。
私はルービックキューブを自力で6面揃えることが出来る。
別になんてことの無いアルゴリズムで、時間はかかるが、単なる物理的な作業である。
これが実は大変なことだと、妻が1面も整えられないのを見て、初めて気づいた。
私は常人ではない。
私も「ギフテッド」の一人なのだ。
それも、育て方を間違えられた。
父も、母も、常人ではなく「ギフテッド」だったのだ。
それも、戦争と戦後という時代の中で、育て方を間違えられた「ギフテッド」。
これに気づいたとき、スーッと、自分の人生の来し方が見通せたような気がした。
そして、我が子の行く末もスーッと見えてきた、ような気がした。
実は悲しいことに、ほとんどの「ギフテッド」には悲惨な将来しか待っていない。
実際、私の父母は二人ともアル中で亡くなったし、何より「バカと天才は紙一重」などという格言もあるくらいだ。
この世は「ギフテッド」のために出来てはいない。
だから「ギフテッド」はどの時点かで必ずドロップアウトする。
私は小3で学校と全面戦争してドロップアウトしたし、少年院の子どもたちは平均よりもIQが高いという調査結果もある。
これは大変だと、息子が幼稚園の年中さんの頃から、市の教育委員会や入学予定の小学校に話をして、何とかドロップアウトだけは避けようとしてきた。
今では小6にもなって、クラスではほとんど一言も発せずにいるから、もしかしたらドロップアウトしてるかも知れないが、それでも妙な軋轢はないようだ。
立志伝中の天才の多くが悲惨な末路を迎えているのは他人事ではない。
だからこそ、ピアノ、書道、英語……となるのだが、人の言うことを聞かないのが「ギフテッド」の常で、どうしたもんか。
それは良いのだが、自分がして欲しかったことを息子にやろうとしてしまう。
ピアノ、書道、英語……
そりゃ、やっていれば、将来、なんかの役に立つだろうが、その「将来」とやらが、親にどれほど見通せているのかって話。
私は基本、放任の野放しだった。
親は悪しき戦後教育の産物で、子どもの自主性だの自由だのを奉じて、結局は無責任にほったらかした。
と言うより、まず父親は、この資本主義の世の中があと十年も続くとは思っていないものだから、子どもの教育よりもこの世の変革に情熱を注いだ。
「将来」の見通しがそもそも狂っていたのだ。
母親は、女学校始まって以来の才女と言われ、自分から勉強をする子だったので、まさか我が子が、言われなければ宿題もやらないとは思いもしなかった。
勝手にやってるだろうとチェックもしない。
で、学校に言われてキレる。
その繰り返し。
現実には、学校の宿題を家でやったことなど一度もなく、すべて居残りだった。
その頃(小4~小6)の担任は教員だった母の元同僚で、なまじ私の家庭事情を知っているものだから、敢えて介入することはなかった。
小3で、すでに教員を一人辞めさせた、前科のある子どもである。
しかも、親も親である。
とにかく関わるのも面倒くさい。
放っておけ。
今では、この人たちの気持ちが手に取るように分かる。
実は、息子が3歳になっても一言も発せず、これはおかしいと文献を漁りはじめ「ギフテッド」という存在にたどり着いた。
一言で言えば「才能を与えられた(ギフテッド)子」ということなのだが、この「才能」と言うのがやっかいで、決してこれを持たされた子に幸福をもたらすようなものではない。
息子の場合、パズルを解いたり、ものを組み立てたりするのは、同世代の子よりも圧倒的に勝っていたのだが、言葉が無い。
アインシュタインやファインマン、日本では湯川秀樹など、ノーベル賞をとるような物理学者が幼少期、言葉が遅かったことを心配されたことはよく知られていて、そこから調べて、おそらくは理系の「ギフテッド」だろうと当たりをつけた。
で、その過程で、我がことに思い至った。
私はルービックキューブを自力で6面揃えることが出来る。
別になんてことの無いアルゴリズムで、時間はかかるが、単なる物理的な作業である。
これが実は大変なことだと、妻が1面も整えられないのを見て、初めて気づいた。
私は常人ではない。
私も「ギフテッド」の一人なのだ。
それも、育て方を間違えられた。
父も、母も、常人ではなく「ギフテッド」だったのだ。
それも、戦争と戦後という時代の中で、育て方を間違えられた「ギフテッド」。
これに気づいたとき、スーッと、自分の人生の来し方が見通せたような気がした。
そして、我が子の行く末もスーッと見えてきた、ような気がした。
実は悲しいことに、ほとんどの「ギフテッド」には悲惨な将来しか待っていない。
実際、私の父母は二人ともアル中で亡くなったし、何より「バカと天才は紙一重」などという格言もあるくらいだ。
この世は「ギフテッド」のために出来てはいない。
だから「ギフテッド」はどの時点かで必ずドロップアウトする。
私は小3で学校と全面戦争してドロップアウトしたし、少年院の子どもたちは平均よりもIQが高いという調査結果もある。
これは大変だと、息子が幼稚園の年中さんの頃から、市の教育委員会や入学予定の小学校に話をして、何とかドロップアウトだけは避けようとしてきた。
今では小6にもなって、クラスではほとんど一言も発せずにいるから、もしかしたらドロップアウトしてるかも知れないが、それでも妙な軋轢はないようだ。
立志伝中の天才の多くが悲惨な末路を迎えているのは他人事ではない。
だからこそ、ピアノ、書道、英語……となるのだが、人の言うことを聞かないのが「ギフテッド」の常で、どうしたもんか。
2019年09月20日
伊佐山紫文393
息子が小六になり、もうすぐ中学、同じ頃の我が身を振り返れば、なんとまあ、奇矯な歩みであったことよ。
1972年、私が10歳の頃だから、小五の時に日中国交正常化で、マスコミは文革の中国礼賛一色だった。
それでも、なんで、そこで中国にハマるのか。
それが奇矯な子の奇矯たる所以であり、まあ、仕方ない。
小五にして、日中友好協会を通じて『毛沢東語録』を取り寄せ、緑の公人帽を被り、紅衛兵を気取っていた。
もう、アホ丸出しとしか言い様がない。
それに引きくらべ、我が子の健全なこと、逆に驚嘆する。
宿題はちゃんとやるし、順法精神というか、規範意識の高さがどこから来るのか、カントではないが、星空を見上げ「Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir」(我が天空の輝き、そして内面の道徳律『実践理性批判』)と賛嘆したくなる。
もちろん、カントはダーウィンを知るよしも無かったから、道徳の進化的な起源へと思索を深めることは出来なかったし、なにより、この内面的道徳律への賛嘆は神への信仰に直接繋がっていた。
道徳律の起源を知ることは出来ない。
だから、神を信じるしかないのだ、と。
先日、息子が、自転車で二人乗りをしている若いカップルを見て、
「二人乗りって犯罪でしょ。なんであんなことをするんだろ」
「さあね、なんでだと思う?」
「ロマンス、かなぁ」
おお!
まさにそう。
世の掟や内なる道徳律に逆らうことからロマンスは生まれる。
いろいろ分かってんじゃん。
お父さんにとってのロマンスは中国だったからね。
毛沢東と二人乗りしてたようなもん。
ああ、恥ずかし。
1972年、私が10歳の頃だから、小五の時に日中国交正常化で、マスコミは文革の中国礼賛一色だった。
それでも、なんで、そこで中国にハマるのか。
それが奇矯な子の奇矯たる所以であり、まあ、仕方ない。
小五にして、日中友好協会を通じて『毛沢東語録』を取り寄せ、緑の公人帽を被り、紅衛兵を気取っていた。
もう、アホ丸出しとしか言い様がない。
それに引きくらべ、我が子の健全なこと、逆に驚嘆する。
宿題はちゃんとやるし、順法精神というか、規範意識の高さがどこから来るのか、カントではないが、星空を見上げ「Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir」(我が天空の輝き、そして内面の道徳律『実践理性批判』)と賛嘆したくなる。
もちろん、カントはダーウィンを知るよしも無かったから、道徳の進化的な起源へと思索を深めることは出来なかったし、なにより、この内面的道徳律への賛嘆は神への信仰に直接繋がっていた。
道徳律の起源を知ることは出来ない。
だから、神を信じるしかないのだ、と。
先日、息子が、自転車で二人乗りをしている若いカップルを見て、
「二人乗りって犯罪でしょ。なんであんなことをするんだろ」
「さあね、なんでだと思う?」
「ロマンス、かなぁ」
おお!
まさにそう。
世の掟や内なる道徳律に逆らうことからロマンスは生まれる。
いろいろ分かってんじゃん。
お父さんにとってのロマンスは中国だったからね。
毛沢東と二人乗りしてたようなもん。
ああ、恥ずかし。
2019年09月20日
伊佐山紫文392
関西に来たばかりの頃、様々な受け答えに戸惑うことばかりだった。
駅の売店で、
「120分テープありますか?」
と聞けば、
「売るほどありまっせ」
どう答えて良いのか分からない。
八百屋のおっちゃんが、おつりを渡してくれながら、
「300万円」
子どもじゃあるまいし、どう返して良いのやら。
あと、女子の猥談、と言うか、あっけらかんとした下ネタ。
何もかもが初めてで、ああ、自分は関西にいるんだ、と、しみじみ思ったものだった。
あれから30年。
KADOKAWAのデスクを務め、フリーになってからは連載も持ち、憧れだった大阪の創元社から処女作を上梓したのが、関西に来て4年目、28歳の頃。
30代になり、これまた学生時代からの夢だった東京の勁草書房から立て続けに2冊、出版した。
どれも売れなかったけど。
舞台の方は、仕事が入ってくれば仕方なく、という感じで、最初のうちは演出もしたが、本物の演出家を見て怖じ気づいてしまい、台本提供だけするようになった。
考えたら、その演出家の持っていた劇団は結構歴史があって、あちこちの仕事先に関係者がいるのだった。
ただ、歴史があるというのはくせ者で、あるとき、その劇団の話題が出て、芝居関係の知人は、
「長くやってりゃ良いってもんでもない。連中、全然ステップアップしてない」
確かに。
ただ、今思えば、関西の劇団にとってのステップアップって、基本、東京進出だから、それも善し悪しだと思う。
関西にきちんと根ざすというのも大事なんじゃなかろうか。
などと、部屋を片付けていたらいろんなものが出てきて、ちょっと感傷的になった。
ただの二日酔い?
かもね。
駅の売店で、
「120分テープありますか?」
と聞けば、
「売るほどありまっせ」
どう答えて良いのか分からない。
八百屋のおっちゃんが、おつりを渡してくれながら、
「300万円」
子どもじゃあるまいし、どう返して良いのやら。
あと、女子の猥談、と言うか、あっけらかんとした下ネタ。
何もかもが初めてで、ああ、自分は関西にいるんだ、と、しみじみ思ったものだった。
あれから30年。
KADOKAWAのデスクを務め、フリーになってからは連載も持ち、憧れだった大阪の創元社から処女作を上梓したのが、関西に来て4年目、28歳の頃。
30代になり、これまた学生時代からの夢だった東京の勁草書房から立て続けに2冊、出版した。
どれも売れなかったけど。
舞台の方は、仕事が入ってくれば仕方なく、という感じで、最初のうちは演出もしたが、本物の演出家を見て怖じ気づいてしまい、台本提供だけするようになった。
考えたら、その演出家の持っていた劇団は結構歴史があって、あちこちの仕事先に関係者がいるのだった。
ただ、歴史があるというのはくせ者で、あるとき、その劇団の話題が出て、芝居関係の知人は、
「長くやってりゃ良いってもんでもない。連中、全然ステップアップしてない」
確かに。
ただ、今思えば、関西の劇団にとってのステップアップって、基本、東京進出だから、それも善し悪しだと思う。
関西にきちんと根ざすというのも大事なんじゃなかろうか。
などと、部屋を片付けていたらいろんなものが出てきて、ちょっと感傷的になった。
ただの二日酔い?
かもね。
2019年09月15日
伊佐山紫文391
納豆を手作っている。
冬場にこたつに入れて発酵させていたのだが、ヨーグルトメーカーを買ってからはこれで夏場も大丈夫。
なにせ市販の納豆とは別物の旨さがある。
まず、豆から選べる。
お気に入りはコープこうべで売っている「秘伝豆」。
茹でて塩を振れば立派なおつまみになるし、冷たい出汁に浸せば上品な一品である。
この秘伝豆を一昼夜、たっぷりの水に浸す。
呼吸して泡が出るくらい(これで噂のGABAが出来てくる)。
これを戻し水ごと茹でる。
うちでは圧力鍋(朝日軽金属)の重いほう(h)で10分ほど。
冷めたら、ざるで水を切って、市販の納豆1パックと混ぜ合わせる。
そのままヨーグルトメーカーへ。
蓋はせずに、キッチンペーパーをかけるなどして(納豆菌の発酵には酸素が必要)、45度、24時間。
強い風味が好みの方は48時間でもOK(と言うか、うちはこれ)。
密閉できる容器に移し替えて、冷蔵庫へ。
うちでは鯖缶の身に梅酢、国産の粉辛子を混ぜて、焼き海苔に載せて食う。
その他、ナンプラーなども合う。
納豆が体に良いことは証明済み、特に女性にはお勧めだそうです。
冬場にこたつに入れて発酵させていたのだが、ヨーグルトメーカーを買ってからはこれで夏場も大丈夫。
なにせ市販の納豆とは別物の旨さがある。
まず、豆から選べる。
お気に入りはコープこうべで売っている「秘伝豆」。
茹でて塩を振れば立派なおつまみになるし、冷たい出汁に浸せば上品な一品である。
この秘伝豆を一昼夜、たっぷりの水に浸す。
呼吸して泡が出るくらい(これで噂のGABAが出来てくる)。
これを戻し水ごと茹でる。
うちでは圧力鍋(朝日軽金属)の重いほう(h)で10分ほど。
冷めたら、ざるで水を切って、市販の納豆1パックと混ぜ合わせる。
そのままヨーグルトメーカーへ。
蓋はせずに、キッチンペーパーをかけるなどして(納豆菌の発酵には酸素が必要)、45度、24時間。
強い風味が好みの方は48時間でもOK(と言うか、うちはこれ)。
密閉できる容器に移し替えて、冷蔵庫へ。
うちでは鯖缶の身に梅酢、国産の粉辛子を混ぜて、焼き海苔に載せて食う。
その他、ナンプラーなども合う。
納豆が体に良いことは証明済み、特に女性にはお勧めだそうです。
2019年09月15日
伊佐山紫文390
息子が最近、よくキレる。
「黙れ、だまれ、ダマレ!」
などと叫びながら、殴る蹴る。
体重が知れてるから、なんてこともないが、もうすぐ手に負えなくなるだろう。
その前に、中学校程度の学力はつけておこうと思っていたのだが、少し間に合わなかったかもしれぬ。
ただ救いなのは、息子はなぜこんなにキレやすくなったのか、自分でも不思議らしく、昨日、風呂で、
「最近、毎日ボク『ダマレ』って言ってるよね。なんでだろ」
などと聞いてきた。
よくぞ聞いた。
哺乳類の雄はやっかいなもので、まともな大人になるために、誰でも、思春期には男性ホルモンの猛烈な攻撃を経験せねばならぬ。
やたら反抗したり、けんかしたり、同世代とつるんでバカなことを繰り返す。
親から観たら、もう、ボンクラとしか言えないのだが、哺乳類の雄として、この時期に猛烈に増えてくる男性ホルモン(テストステロン)に突き動かされ、どうしようもなくそうするしかないのだ。
ただ、やっかいなのが、現代では、この生物学的な時期と高校や大学受験とがピッタリと重なっていることで、つまり、テストステロンをきちんと受容し、きちんと反抗した男子は、低学歴に甘んじる可能性が高くなる。
逆に、テストステロンを押さえ込み、従順に受験を勝ち抜いた男子は高学歴を勝ち取るということだ。
テストステロンは攻撃性と同時に社会性のホルモンでもあり、思春期の反抗は社会とのバランスを身につけていく訓練の場でもある。
もし、そういう訓練を経ずに、テストステロンとの戦いを抑えてただひたすら受験に邁進し、高学歴を得たとしたら。
反抗によって社会とのバランスを身につけず、ガキのままで世に出たら。
そう。
テレビでよく見るあんな連中ってことだ。
だから、今は、
「黙れ、だまれ、ダマレ!」
とかって、適度に叫んでろ。
「黙れ、だまれ、ダマレ!」
などと叫びながら、殴る蹴る。
体重が知れてるから、なんてこともないが、もうすぐ手に負えなくなるだろう。
その前に、中学校程度の学力はつけておこうと思っていたのだが、少し間に合わなかったかもしれぬ。
ただ救いなのは、息子はなぜこんなにキレやすくなったのか、自分でも不思議らしく、昨日、風呂で、
「最近、毎日ボク『ダマレ』って言ってるよね。なんでだろ」
などと聞いてきた。
よくぞ聞いた。
哺乳類の雄はやっかいなもので、まともな大人になるために、誰でも、思春期には男性ホルモンの猛烈な攻撃を経験せねばならぬ。
やたら反抗したり、けんかしたり、同世代とつるんでバカなことを繰り返す。
親から観たら、もう、ボンクラとしか言えないのだが、哺乳類の雄として、この時期に猛烈に増えてくる男性ホルモン(テストステロン)に突き動かされ、どうしようもなくそうするしかないのだ。
ただ、やっかいなのが、現代では、この生物学的な時期と高校や大学受験とがピッタリと重なっていることで、つまり、テストステロンをきちんと受容し、きちんと反抗した男子は、低学歴に甘んじる可能性が高くなる。
逆に、テストステロンを押さえ込み、従順に受験を勝ち抜いた男子は高学歴を勝ち取るということだ。
テストステロンは攻撃性と同時に社会性のホルモンでもあり、思春期の反抗は社会とのバランスを身につけていく訓練の場でもある。
もし、そういう訓練を経ずに、テストステロンとの戦いを抑えてただひたすら受験に邁進し、高学歴を得たとしたら。
反抗によって社会とのバランスを身につけず、ガキのままで世に出たら。
そう。
テレビでよく見るあんな連中ってことだ。
だから、今は、
「黙れ、だまれ、ダマレ!」
とかって、適度に叫んでろ。
2019年09月15日
伊佐山紫文389
息子は年金にも関心があるようで、自分は大丈夫だろうか、などと聞いてくる。
で、息子の祖父にあたる私の父の話をする。
お祖父ちゃんは無年金だったんだ。
「無年金?」
年金の掛け金を払った時期がほんの少し足りなくて、もらえなかったんだよ。
「そんなことがあるの?」
今は足りない分を払えばもらえるようになったけど、昔はそうじゃなかった。
もらえる時期になって、手続きをしたら、いきなり「足りてません」で終わり。
これで無年金確定。
「ひどい話じゃん」
そう。
でも、お祖父ちゃんにも問題があった。
「どんな?」
お祖父ちゃんは若い頃、確信犯的に年金を払ってなかった。
「なんで?」
革命家だったからね。
自分が年金をもらえるような歳になるころには革命が成就して「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」ような世の中になってるはずだったんだ。
年金なんて問題じゃ無い。
そもそも貨幣が廃止されてるはずなんだから。
今、年金を払うなんて、自民党政権に協力するようなもの。
むしろ犯罪だ。
そう言って、年金の掛け金を払わなかった。
で、無年金になった。
結果、お祖母ちゃんの年金で食わしてもらった。
「クズじゃねえか、それ」
まさに、そう。
お父さんも年金の掛け金をきちんと払った時期なんて数年だから。
あとはお母さんの扶養家族。
だから、心せよ、我が息子よ。
イサヤマ家の男にはクズの血が連綿と受け継がれておるのだよ。
お前は年金の掛け金くらいちゃんと稼いで払えよ。
で、息子の祖父にあたる私の父の話をする。
お祖父ちゃんは無年金だったんだ。
「無年金?」
年金の掛け金を払った時期がほんの少し足りなくて、もらえなかったんだよ。
「そんなことがあるの?」
今は足りない分を払えばもらえるようになったけど、昔はそうじゃなかった。
もらえる時期になって、手続きをしたら、いきなり「足りてません」で終わり。
これで無年金確定。
「ひどい話じゃん」
そう。
でも、お祖父ちゃんにも問題があった。
「どんな?」
お祖父ちゃんは若い頃、確信犯的に年金を払ってなかった。
「なんで?」
革命家だったからね。
自分が年金をもらえるような歳になるころには革命が成就して「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」ような世の中になってるはずだったんだ。
年金なんて問題じゃ無い。
そもそも貨幣が廃止されてるはずなんだから。
今、年金を払うなんて、自民党政権に協力するようなもの。
むしろ犯罪だ。
そう言って、年金の掛け金を払わなかった。
で、無年金になった。
結果、お祖母ちゃんの年金で食わしてもらった。
「クズじゃねえか、それ」
まさに、そう。
お父さんも年金の掛け金をきちんと払った時期なんて数年だから。
あとはお母さんの扶養家族。
だから、心せよ、我が息子よ。
イサヤマ家の男にはクズの血が連綿と受け継がれておるのだよ。
お前は年金の掛け金くらいちゃんと稼いで払えよ。
2019年09月11日
伊佐山紫文388
息子の人権授業とやらを参観してきた。
「LGBT」だの、「性的マイノリティ」だの、言葉は踊っているが、恐ろしいほど中身が無い。
去年の人権授業もひどかったが、今年もまたパワーアップしてひどい。
配られたプリントがまずひどい。
男子児童三人が帰宅途中に好きな人の話をしていて、ある男の子が、そこにいない別の男の子の名前を挙げる。
これに対して、どんな言葉をかけるべきか。
授業の結論としては、
「それもありなんじゃね」
みたいな。
「違いを認めあいましょうね」
みたいな。
そりゃまあ、結論としてはそうなるんだろうが、これはあくまでも傍観者の立場。
もしそこで挙がった名前が「君」だったどうする?
「俺はお前が好きなんだ、性的に」
と、告られたらどうする?
「それもありなんじゃね」
と言えるか?
「性」、つまり、誰を好きになり、誰と性行為に至るかは、人倫の根本である。
しかもそこには男女の厳然たる非対称がある。
男は社会的に上り詰めれば、理論的には何千人もの子どもを持つことが出来る。
ニートで終わればゼロである。。
女性はいくら頑張ったところで子ども二十人が限度だろう。
こちらももちろん、ゼロの可能性はある。
だが、その差はたかが二十である。
数千と二十。
これは残せる遺伝子の数に正確に合致する。
つまり次世代にできるだけ多くの遺伝子を残すという生命の根幹から観た場合、「性」の意味が(数学的に)男女ではまるで違ってくるのだ。
大雑把に言えば「男は数、女は質」。
男はドンドンやろうとし、女は慎重に選ぼうとする。
これは生物学的に、そして数学的に仕方のないことである。
だからこそ人倫が必要なのであり、そこに男女間の非対称が生じる。
「性」がなぜ人倫の根本を成すかと言えば、それは、それが男女それぞれの遺伝子を混ぜ合わす行為に他ならないからだ。
もちろん、遺伝子の混交を伴わない「性」もある。
そのような「性」は、キリスト教以前では純粋な「愛」と捉えられることもあった。
レズボス島の女たちや戦士たちの愛など。
が、今は違う。
キリスト教ではアダムとイブを単位とした一夫一婦間での閉じられた「性」が人倫の根幹を成す。
近代以降、日本でも「性」は人間「性」の問題として、一夫一婦間の閉じられた「性」が人倫の根本を成している。
「LGBT」が忌まれる背景としての、生物学的根拠とキリスト教的人倫の構造が、この世には厳然として、ある。
そういうことを教えずに、いきなり「LGBT」もないだろうと思って帰ってきた。
「LGBT」だの、「性的マイノリティ」だの、言葉は踊っているが、恐ろしいほど中身が無い。
去年の人権授業もひどかったが、今年もまたパワーアップしてひどい。
配られたプリントがまずひどい。
男子児童三人が帰宅途中に好きな人の話をしていて、ある男の子が、そこにいない別の男の子の名前を挙げる。
これに対して、どんな言葉をかけるべきか。
授業の結論としては、
「それもありなんじゃね」
みたいな。
「違いを認めあいましょうね」
みたいな。
そりゃまあ、結論としてはそうなるんだろうが、これはあくまでも傍観者の立場。
もしそこで挙がった名前が「君」だったどうする?
「俺はお前が好きなんだ、性的に」
と、告られたらどうする?
「それもありなんじゃね」
と言えるか?
「性」、つまり、誰を好きになり、誰と性行為に至るかは、人倫の根本である。
しかもそこには男女の厳然たる非対称がある。
男は社会的に上り詰めれば、理論的には何千人もの子どもを持つことが出来る。
ニートで終わればゼロである。。
女性はいくら頑張ったところで子ども二十人が限度だろう。
こちらももちろん、ゼロの可能性はある。
だが、その差はたかが二十である。
数千と二十。
これは残せる遺伝子の数に正確に合致する。
つまり次世代にできるだけ多くの遺伝子を残すという生命の根幹から観た場合、「性」の意味が(数学的に)男女ではまるで違ってくるのだ。
大雑把に言えば「男は数、女は質」。
男はドンドンやろうとし、女は慎重に選ぼうとする。
これは生物学的に、そして数学的に仕方のないことである。
だからこそ人倫が必要なのであり、そこに男女間の非対称が生じる。
「性」がなぜ人倫の根本を成すかと言えば、それは、それが男女それぞれの遺伝子を混ぜ合わす行為に他ならないからだ。
もちろん、遺伝子の混交を伴わない「性」もある。
そのような「性」は、キリスト教以前では純粋な「愛」と捉えられることもあった。
レズボス島の女たちや戦士たちの愛など。
が、今は違う。
キリスト教ではアダムとイブを単位とした一夫一婦間での閉じられた「性」が人倫の根幹を成す。
近代以降、日本でも「性」は人間「性」の問題として、一夫一婦間の閉じられた「性」が人倫の根本を成している。
「LGBT」が忌まれる背景としての、生物学的根拠とキリスト教的人倫の構造が、この世には厳然として、ある。
そういうことを教えずに、いきなり「LGBT」もないだろうと思って帰ってきた。
2019年09月11日
伊佐山紫文386
ビデオ『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』平成30年2018年日本
監督:前田哲 脚本:橋本裕志
筋ジストロフィーの主人公のワガママ放題。
大泉洋の演技と北海道の景色が素晴らしい。
それはそれとして、実はこの主人公と同じくらいワガママな障害者を一人知っている。
Mさんとしておこう。
もう35年くらい前、学生運動の中で知り合った脳性マヒの障害者だった。
Mさん、とにかく弁が立つ。
「あなたの言う障害者解放って何なんですか?」
と聞かれれば、
「ワシの24時間完全介護や!」
と言い放つ。
この人は一体どんな生活をしてんのか。
で、どういういきさつかは忘れたが、おそらく何かの用事でMさんのアパートを訪ねることになった。
集会とかデモとか、公的な場所以外で会うのは初めてである。
で、Mさん、こたつで真っ昼間から酒と麻雀である。
他のメンバーは公的な場では観たことのない顔である。
いつも引き連れているボランティアたちではない。
明らかに悪友然とした言葉遣い、下品な笑い。
突然、
「おう、○○、小便介助して」
座ったまま、隣に座った男に手伝ってもらいながら尿瓶にとる。
公的な場では「こんなトイレで障害者の尊厳が守れるか!」
とかって声高に叫んでいるのに、酒と麻雀で「めんどくせえ」とばかりに尿瓶である。
これ以外にも、Mさん、とにかく人を使う、使う。
使われる方も、当然とばかりに動く、動く。
麻雀をやりながら、である。
用事を済ませてさっさと帰ってきたが、その後、公的な場であったとき、ちょっと気まずそうにしていたのを憶えている。
私が関西に出てきてすぐ、亡くなったことを風の噂で聞いた。
で、数年後、縁あって(考えたら、この「縁」というのが、今のクレオ大阪中央、大阪市中央婦人会館での講演会だった)、ある障害者支援の団体主催の講演会に講師として呼ばれたとき、Mさんの話をした。
講演の後の懇親会で、皆さん、
「あの話、Mさんのことでしょう?」
と口々に言う。
「そうです、そうです。でも、なぜ?」
「あの方、もの凄く有名なんですよ。私たちが機関誌を出すとき、文章を書いてもらおうって言ってたところでした」
「そうだったんですか」
「イサヤマさん、Mさんと麻雀したでしょう?」
「いや、実は僕、ギャンブル断ちしてるんで。絶対に依存症になることがわかってますから」
「そうでしたか、それにしてもMさん、破天荒な方でしたよね……」
確かに、Mさんを主人公にしてもかなり面白い映画が出来たろう。
★★★★☆
監督:前田哲 脚本:橋本裕志
筋ジストロフィーの主人公のワガママ放題。
大泉洋の演技と北海道の景色が素晴らしい。
それはそれとして、実はこの主人公と同じくらいワガママな障害者を一人知っている。
Mさんとしておこう。
もう35年くらい前、学生運動の中で知り合った脳性マヒの障害者だった。
Mさん、とにかく弁が立つ。
「あなたの言う障害者解放って何なんですか?」
と聞かれれば、
「ワシの24時間完全介護や!」
と言い放つ。
この人は一体どんな生活をしてんのか。
で、どういういきさつかは忘れたが、おそらく何かの用事でMさんのアパートを訪ねることになった。
集会とかデモとか、公的な場所以外で会うのは初めてである。
で、Mさん、こたつで真っ昼間から酒と麻雀である。
他のメンバーは公的な場では観たことのない顔である。
いつも引き連れているボランティアたちではない。
明らかに悪友然とした言葉遣い、下品な笑い。
突然、
「おう、○○、小便介助して」
座ったまま、隣に座った男に手伝ってもらいながら尿瓶にとる。
公的な場では「こんなトイレで障害者の尊厳が守れるか!」
とかって声高に叫んでいるのに、酒と麻雀で「めんどくせえ」とばかりに尿瓶である。
これ以外にも、Mさん、とにかく人を使う、使う。
使われる方も、当然とばかりに動く、動く。
麻雀をやりながら、である。
用事を済ませてさっさと帰ってきたが、その後、公的な場であったとき、ちょっと気まずそうにしていたのを憶えている。
私が関西に出てきてすぐ、亡くなったことを風の噂で聞いた。
で、数年後、縁あって(考えたら、この「縁」というのが、今のクレオ大阪中央、大阪市中央婦人会館での講演会だった)、ある障害者支援の団体主催の講演会に講師として呼ばれたとき、Mさんの話をした。
講演の後の懇親会で、皆さん、
「あの話、Mさんのことでしょう?」
と口々に言う。
「そうです、そうです。でも、なぜ?」
「あの方、もの凄く有名なんですよ。私たちが機関誌を出すとき、文章を書いてもらおうって言ってたところでした」
「そうだったんですか」
「イサヤマさん、Mさんと麻雀したでしょう?」
「いや、実は僕、ギャンブル断ちしてるんで。絶対に依存症になることがわかってますから」
「そうでしたか、それにしてもMさん、破天荒な方でしたよね……」
確かに、Mさんを主人公にしてもかなり面白い映画が出来たろう。
★★★★☆
2019年09月11日
伊佐山紫文386
ビデオ『フレーム 危険動画サイト』平成29年2017年スペイン
監督・脚本:マーク・マルチネス・ジョーダン
アプリなのかサイトなのか、動画同時配信の「フレーム」が大流行。
何も規制がないものだから、ついに殺人までもが配信される。
で、若者たちのパーティに狂人たちが乱入。
拷問殺人の様子が同時配信され、視聴者数は伸びに伸び……
まあ、それ以上でも以下でもない。
ただ、話の進め方というか、プロットの配置が素晴らしく、実に勉強になる。
それからベートーヴェンの『第九』の使い方も絶妙。
一体、こんな映画に、どこが音源を提供したんだろうかと、エンドロールを目を皿のようにして眺めたが、どこにもなかった。
パブリックドメインを使ったんだろうか。
★★★☆☆
監督・脚本:マーク・マルチネス・ジョーダン
アプリなのかサイトなのか、動画同時配信の「フレーム」が大流行。
何も規制がないものだから、ついに殺人までもが配信される。
で、若者たちのパーティに狂人たちが乱入。
拷問殺人の様子が同時配信され、視聴者数は伸びに伸び……
まあ、それ以上でも以下でもない。
ただ、話の進め方というか、プロットの配置が素晴らしく、実に勉強になる。
それからベートーヴェンの『第九』の使い方も絶妙。
一体、こんな映画に、どこが音源を提供したんだろうかと、エンドロールを目を皿のようにして眺めたが、どこにもなかった。
パブリックドメインを使ったんだろうか。
★★★☆☆
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
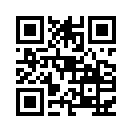
アクセスカウンタ
読者登録
