2019年09月26日
伊佐山紫文403
レイチェル・カーソンについてやるからには、エコロジズムについて最新の情報を得なければならぬとて、関連の書籍を読んでいる。
カーソン当時の環境思想を垂れ流すだけではお話にもならないし、私が生きた前世紀のエコロジズムは今となってはカルトでしかない。
それで、今現在のエコロジズムとはどんなものかと、諸文献を漁っている。
ところが、読めば読むほど、ほとんどの文献が事実の裏付けを欠いた、思い込みだけのものだと分かってきた。
まあ、そりゃそうだ。
地球規模の気候変動など、仮説は立てられるが、検証のしようもない。
そして、検証のしようのない「仮説」がまるで真理としてまかり通っているのがこの世界なのだ。
たとえば地球温暖化などと言うが、これが人間活動の影響かどうかは、はっきり言って分からない。
少なくとも、断言できる人間は科学者ではない。
そもそも、地球の気温は公転軌道によって決まり、それによって氷河期と間氷期を繰り返してきた。
人類の文明など、たまたまの間氷期に生まれた、たった直近数千年のものでしかない。
ましてや化石燃料云々など、数百年のデータでしかない。
これからの地球がさらなる温暖期に向かうか、それとも氷河期に戻るのか、それを決めるのは公転軌道であって、人類ではない。
温暖期に向かえば全ての氷河と南極の氷は溶け、海水面は数十メートル上昇して今の文明は滅ぶ。
氷河期になれば亜寒帯と温帯に集中している今の文明はすべて滅ぶ。
それだけの話。
どちらになるか、すべては公転軌道が決めることであって、人類がどうとか出来るような話では決してない。
それでも、人類そのものが滅ぶことは絶対にない。
この地球の気候変動に耐えて生き延びてきたのが、他ならぬ人類なのだから。
今の文明ではない、他の、私たちが想像も出来ない文明を人類は生み出すだろう。
だから、今は、地球のために私たちが出来ること、などという傲慢を去り、まずは謙虚に、自らの無力を悟ることだ。
そして無力を知りながら、ささやかな、身の回りの環境を考えて楽しく暮らす。
私たちに出来るのは、そんな程度のものでしかないと思う。
地球のため? 人間ごときがふざけるな、と地球は思っているだろう。
カーソン当時の環境思想を垂れ流すだけではお話にもならないし、私が生きた前世紀のエコロジズムは今となってはカルトでしかない。
それで、今現在のエコロジズムとはどんなものかと、諸文献を漁っている。
ところが、読めば読むほど、ほとんどの文献が事実の裏付けを欠いた、思い込みだけのものだと分かってきた。
まあ、そりゃそうだ。
地球規模の気候変動など、仮説は立てられるが、検証のしようもない。
そして、検証のしようのない「仮説」がまるで真理としてまかり通っているのがこの世界なのだ。
たとえば地球温暖化などと言うが、これが人間活動の影響かどうかは、はっきり言って分からない。
少なくとも、断言できる人間は科学者ではない。
そもそも、地球の気温は公転軌道によって決まり、それによって氷河期と間氷期を繰り返してきた。
人類の文明など、たまたまの間氷期に生まれた、たった直近数千年のものでしかない。
ましてや化石燃料云々など、数百年のデータでしかない。
これからの地球がさらなる温暖期に向かうか、それとも氷河期に戻るのか、それを決めるのは公転軌道であって、人類ではない。
温暖期に向かえば全ての氷河と南極の氷は溶け、海水面は数十メートル上昇して今の文明は滅ぶ。
氷河期になれば亜寒帯と温帯に集中している今の文明はすべて滅ぶ。
それだけの話。
どちらになるか、すべては公転軌道が決めることであって、人類がどうとか出来るような話では決してない。
それでも、人類そのものが滅ぶことは絶対にない。
この地球の気候変動に耐えて生き延びてきたのが、他ならぬ人類なのだから。
今の文明ではない、他の、私たちが想像も出来ない文明を人類は生み出すだろう。
だから、今は、地球のために私たちが出来ること、などという傲慢を去り、まずは謙虚に、自らの無力を悟ることだ。
そして無力を知りながら、ささやかな、身の回りの環境を考えて楽しく暮らす。
私たちに出来るのは、そんな程度のものでしかないと思う。
地球のため? 人間ごときがふざけるな、と地球は思っているだろう。
2019年09月26日
伊佐山紫文403
レイチェル・カーソンについてやるからには、エコロジズムについて最新の情報を得なければならぬとて、関連の書籍を読んでいる。
カーソン当時の環境思想を垂れ流すだけではお話にもならないし、私が生きた前世紀のエコロジズムは今となってはカルトでしかない。
それで、今現在のエコロジズムとはどんなものかと、諸文献を漁っている。
ところが、読めば読むほど、ほとんどの文献が事実の裏付けを欠いた、思い込みだけのものだと分かってきた。
まあ、そりゃそうだ。
地球規模の気候変動など、仮説は立てられるが、検証のしようもない。
そして、検証のしようのない「仮説」がまるで真理としてまかり通っているのがこの世界なのだ。
たとえば地球温暖化などと言うが、これが人間活動の影響かどうかは、はっきり言って分からない。
少なくとも、断言できる人間は科学者ではない。
そもそも、地球の気温は公転軌道によって決まり、それによって氷河期と間氷期を繰り返してきた。
人類の文明など、たまたまの間氷期に生まれた、たった直近数千年のものでしかない。
ましてや化石燃料云々など、数百年のデータでしかない。
これからの地球がさらなる温暖期に向かうか、それとも氷河期に戻るのか、それを決めるのは公転軌道であって、人類ではない。
温暖期に向かえば全ての氷河と南極の氷は溶け、海水面は数十メートル上昇して今の文明は滅ぶ。
氷河期になれば亜寒帯と温帯に集中している今の文明はすべて滅ぶ。
それだけの話。
どちらになるか、すべては公転軌道が決めることであって、人類がどうとか出来るような話では決してない。
それでも、人類そのものが滅ぶことは絶対にない。
この地球の気候変動に耐えて生き延びてきたのが、他ならぬ人類なのだから。
今の文明ではない、他の、私たちが想像も出来ない文明を人類は生み出すだろう。
だから、今は、地球のために私たちが出来ること、などという傲慢を去り、まずは謙虚に、自らの無力を悟ることだ。
そして無力を知りながら、ささやかな、身の回りの環境を考えて楽しく暮らす。
私たちに出来るのは、そんな程度のものでしかないと思う。
地球のため? 人間ごときがふざけるな、と地球は思っているだろう。
カーソン当時の環境思想を垂れ流すだけではお話にもならないし、私が生きた前世紀のエコロジズムは今となってはカルトでしかない。
それで、今現在のエコロジズムとはどんなものかと、諸文献を漁っている。
ところが、読めば読むほど、ほとんどの文献が事実の裏付けを欠いた、思い込みだけのものだと分かってきた。
まあ、そりゃそうだ。
地球規模の気候変動など、仮説は立てられるが、検証のしようもない。
そして、検証のしようのない「仮説」がまるで真理としてまかり通っているのがこの世界なのだ。
たとえば地球温暖化などと言うが、これが人間活動の影響かどうかは、はっきり言って分からない。
少なくとも、断言できる人間は科学者ではない。
そもそも、地球の気温は公転軌道によって決まり、それによって氷河期と間氷期を繰り返してきた。
人類の文明など、たまたまの間氷期に生まれた、たった直近数千年のものでしかない。
ましてや化石燃料云々など、数百年のデータでしかない。
これからの地球がさらなる温暖期に向かうか、それとも氷河期に戻るのか、それを決めるのは公転軌道であって、人類ではない。
温暖期に向かえば全ての氷河と南極の氷は溶け、海水面は数十メートル上昇して今の文明は滅ぶ。
氷河期になれば亜寒帯と温帯に集中している今の文明はすべて滅ぶ。
それだけの話。
どちらになるか、すべては公転軌道が決めることであって、人類がどうとか出来るような話では決してない。
それでも、人類そのものが滅ぶことは絶対にない。
この地球の気候変動に耐えて生き延びてきたのが、他ならぬ人類なのだから。
今の文明ではない、他の、私たちが想像も出来ない文明を人類は生み出すだろう。
だから、今は、地球のために私たちが出来ること、などという傲慢を去り、まずは謙虚に、自らの無力を悟ることだ。
そして無力を知りながら、ささやかな、身の回りの環境を考えて楽しく暮らす。
私たちに出来るのは、そんな程度のものでしかないと思う。
地球のため? 人間ごときがふざけるな、と地球は思っているだろう。
2019年09月26日
伊佐山紫文402
『バイオフィリア 人間と生物の絆』
E・O・ウィルソン著 狩野秀之訳
ちくま学芸文庫
大著『社会生物学』を上梓して大論争を巻き起こし、忽然と自らのフィールドであるジャングルに消えた進化生物学者E・O・ウィルソンが、今度は極めて穏やかな口調で、格調高く自然保護思想を説いた小著。
なぜ「自然」は、「種」は、そして「生命多様性」は保護されなければならないのか。
本書のどこにも明確な答えはない。
ただ、人間の本性として、生物への愛「バイオフィリア」というものがあるのではないか、と静かに問いかける。
訳者が「文庫版への訳者あとがき」でも述べられているように、この「バイオフィリア」という語は、最近『愛するということ』の新訳が出て再び注目されている、エーリッヒ・フロムの『悪について』の「バイオフィリア」とは全く意味が違う。
フロムの「バイオフィリア」は「ネクロフィリア(死への志向性)」の対語で、「生への志向性」とでも訳すべきもの、背景には心理学者らしくフロイトの「死の欲動」と「生の欲動」があり、だから単独では意味を成さない。
著者も本文で言うように、ウィルソンの「バイオフィリア」の背景にあるのはイーフー・トゥアンの『トポフィリア』である。
とにかく人間には懐かしくてたまらない場所があり、そのような感情をトゥアンは「トポフィリア(場所への愛)」と呼んだ。
とにかくそのような性向が人間にはあるのだ、と。
これは何かと対になった概念ではない。
ウィルソンの「バイオフィリア」もそうで、例えば犬や猫を眺めて思わず笑みをこぼしてしまうような、どうしようもない性向が人間にはある。
そこをベースに自然保護の倫理を構築すべきだと、困難な道を承知で主張する。
小さな、静かな、そして力強い主張に満ちた一冊である。
E・O・ウィルソン著 狩野秀之訳
ちくま学芸文庫
大著『社会生物学』を上梓して大論争を巻き起こし、忽然と自らのフィールドであるジャングルに消えた進化生物学者E・O・ウィルソンが、今度は極めて穏やかな口調で、格調高く自然保護思想を説いた小著。
なぜ「自然」は、「種」は、そして「生命多様性」は保護されなければならないのか。
本書のどこにも明確な答えはない。
ただ、人間の本性として、生物への愛「バイオフィリア」というものがあるのではないか、と静かに問いかける。
訳者が「文庫版への訳者あとがき」でも述べられているように、この「バイオフィリア」という語は、最近『愛するということ』の新訳が出て再び注目されている、エーリッヒ・フロムの『悪について』の「バイオフィリア」とは全く意味が違う。
フロムの「バイオフィリア」は「ネクロフィリア(死への志向性)」の対語で、「生への志向性」とでも訳すべきもの、背景には心理学者らしくフロイトの「死の欲動」と「生の欲動」があり、だから単独では意味を成さない。
著者も本文で言うように、ウィルソンの「バイオフィリア」の背景にあるのはイーフー・トゥアンの『トポフィリア』である。
とにかく人間には懐かしくてたまらない場所があり、そのような感情をトゥアンは「トポフィリア(場所への愛)」と呼んだ。
とにかくそのような性向が人間にはあるのだ、と。
これは何かと対になった概念ではない。
ウィルソンの「バイオフィリア」もそうで、例えば犬や猫を眺めて思わず笑みをこぼしてしまうような、どうしようもない性向が人間にはある。
そこをベースに自然保護の倫理を構築すべきだと、困難な道を承知で主張する。
小さな、静かな、そして力強い主張に満ちた一冊である。
2019年09月26日
伊佐山紫文401
私が学生時代だから、もう1980年代のいつかだと思うが『西暦2000年の地球』という二巻本のいかつい本が出て、それも発行者が「アメリカ合衆国政府」で、その「特別調査報告」とあっては、信頼性も抜群、このままではこの世は確実に滅ぶ、と、若かった私はノストラダムス級の衝撃を受けた。
それ以前にも、「ローマクラブ」の『成長の限界』という恐ろしい本も出ていて、これと『西暦2000年の地球』の衝撃とで、若かった私は、この世は確実にエコロジカルな問題で滅ぶと確信したものだった。
40半ばまで子どもを作らなかったのも、この確信があったからで、一体誰が、滅ぶと分かっている世に我が子を送り出したいか。
まあ、全ては夢かまぼろしで、この時代の環境問題など、鎌倉時代に蔓延した末法思想のようなもの。
「公害」はもはや一時代前の死語になっていたし、現実の世はバブルに浮かれ始めていた。
まさに『なんとなく、クリスタル』の時代で、共に浮かれ得ない陰気な連中を捉えたのが、新たな末法思想である「環境問題」だったのだ。
私はそれにドンピシャで捉えられた。
エコロジーこそ真理であり、これに逆らうものは全て滅ぶ。
今思えば狂気でしかない。
が、狂気によってしか変わらぬ世もある。
この世が当時より良くなっているとすれば、と言うより、確実に良くなっているのだが、その動力は狂気である。
そういうことも客観的に見られるような歳になってしまった。
それ以前にも、「ローマクラブ」の『成長の限界』という恐ろしい本も出ていて、これと『西暦2000年の地球』の衝撃とで、若かった私は、この世は確実にエコロジカルな問題で滅ぶと確信したものだった。
40半ばまで子どもを作らなかったのも、この確信があったからで、一体誰が、滅ぶと分かっている世に我が子を送り出したいか。
まあ、全ては夢かまぼろしで、この時代の環境問題など、鎌倉時代に蔓延した末法思想のようなもの。
「公害」はもはや一時代前の死語になっていたし、現実の世はバブルに浮かれ始めていた。
まさに『なんとなく、クリスタル』の時代で、共に浮かれ得ない陰気な連中を捉えたのが、新たな末法思想である「環境問題」だったのだ。
私はそれにドンピシャで捉えられた。
エコロジーこそ真理であり、これに逆らうものは全て滅ぶ。
今思えば狂気でしかない。
が、狂気によってしか変わらぬ世もある。
この世が当時より良くなっているとすれば、と言うより、確実に良くなっているのだが、その動力は狂気である。
そういうことも客観的に見られるような歳になってしまった。
2019年09月26日
伊佐山紫文400
筑後川は日田では三隈川(みくまがわ)と名前を変える。
玖珠川(くすがわ)と大山川の合流点から夜明ダムまでの日田市内では、筑後川は三隈川と呼ばれるのである。
その三隈川の支流に花月川がある。
小野川と有田川が合流し、三隈川に流れ込むまでのほんの数キロの川である。
そんな花月川の中流域に簡単なダムで流れをせき止めた水出淵(すいでぶち)なる瀞(とろ)があって、少年時代、ここが私のもっぱらな釣り場だった。
小学生の頃はフナを釣ったし、秋には鯉も上がった。
中学生になりルアー釣りを覚えてからはナマズをガシュガシュ釣った。
不思議なことに、三隈川には普通にいたイダ(ウグイ)が花月川では見られなかった。
鮎もそう。
花月川にはいなかった。
エノハ(ヤマメ)もそうで、三隈川の他の支流、大山川や高瀬川では普通に釣れたのに、花月川系の支流では全く見られない。
水質が関係しているのか、地形の問題か、何か他に理由があるのか、高校生の頃、どうにか研究する手段はないのか、色々と考えていた。
その後、大学院を中退し、研究生活から遠ざかって二十数年、久しぶりに水出淵に釣り糸を落とすと、なんと、次から次にイダ(ウグイ)がかかるわ、かかるわ。
調べれば、放流した琵琶湖の鮎に紛れてウグイが生息域を広げているのだという。
花月川系の小野川にも放流されたヤマメ釣り場が整備されているという。
これで、ウグイやヤマメや鮎の分布の理由を解明するという、私の研究の機会は永遠に失われた。
これも自然破壊の一種ではないのか。
などと、若い頃の私なら思ったかも知れないが、今はもう、仕方ないと諦念している。
人間と自然の関わりとはこんなものなんだし、と。
最近、レイチェル・カーソンにからんで現代のエコロジズムについて調べつつ、自らの自然との関わりについて内省している。
ちなみに昨年、バスの車窓から眺めた水出淵はなんともモダンな堰に姿を変えていた。
これもまた時代の流れ、仕方ない。
玖珠川(くすがわ)と大山川の合流点から夜明ダムまでの日田市内では、筑後川は三隈川と呼ばれるのである。
その三隈川の支流に花月川がある。
小野川と有田川が合流し、三隈川に流れ込むまでのほんの数キロの川である。
そんな花月川の中流域に簡単なダムで流れをせき止めた水出淵(すいでぶち)なる瀞(とろ)があって、少年時代、ここが私のもっぱらな釣り場だった。
小学生の頃はフナを釣ったし、秋には鯉も上がった。
中学生になりルアー釣りを覚えてからはナマズをガシュガシュ釣った。
不思議なことに、三隈川には普通にいたイダ(ウグイ)が花月川では見られなかった。
鮎もそう。
花月川にはいなかった。
エノハ(ヤマメ)もそうで、三隈川の他の支流、大山川や高瀬川では普通に釣れたのに、花月川系の支流では全く見られない。
水質が関係しているのか、地形の問題か、何か他に理由があるのか、高校生の頃、どうにか研究する手段はないのか、色々と考えていた。
その後、大学院を中退し、研究生活から遠ざかって二十数年、久しぶりに水出淵に釣り糸を落とすと、なんと、次から次にイダ(ウグイ)がかかるわ、かかるわ。
調べれば、放流した琵琶湖の鮎に紛れてウグイが生息域を広げているのだという。
花月川系の小野川にも放流されたヤマメ釣り場が整備されているという。
これで、ウグイやヤマメや鮎の分布の理由を解明するという、私の研究の機会は永遠に失われた。
これも自然破壊の一種ではないのか。
などと、若い頃の私なら思ったかも知れないが、今はもう、仕方ないと諦念している。
人間と自然の関わりとはこんなものなんだし、と。
最近、レイチェル・カーソンにからんで現代のエコロジズムについて調べつつ、自らの自然との関わりについて内省している。
ちなみに昨年、バスの車窓から眺めた水出淵はなんともモダンな堰に姿を変えていた。
これもまた時代の流れ、仕方ない。
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
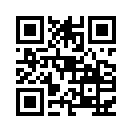
アクセスカウンタ
読者登録
