2019年09月22日
伊佐山紫文398
『ケーキの切れない非行少年たち』
宮口幸治 新潮新書
昨日紹介した『発達障害と少年犯罪』に触発されて書かれた一冊。
「コグトレ」が具体的に紹介されている。
『発達障害と少年犯罪』が主に「発達障害」に焦点が当てられているのに対し、本書では「知的障害」について詳しく記述されている。
発達障害と同様、知的障害も犯罪とは無縁ではない。
むしろ、支援の必要な知的障害者が放っておかれ、犯罪者になってしまうケースが多いのではないかという。
ダマシオの『デカルトの誤り』やイーグルマンの諸著作と合わせ読めばさらに理解も深まるだろう。
宮口幸治 新潮新書
昨日紹介した『発達障害と少年犯罪』に触発されて書かれた一冊。
「コグトレ」が具体的に紹介されている。
『発達障害と少年犯罪』が主に「発達障害」に焦点が当てられているのに対し、本書では「知的障害」について詳しく記述されている。
発達障害と同様、知的障害も犯罪とは無縁ではない。
むしろ、支援の必要な知的障害者が放っておかれ、犯罪者になってしまうケースが多いのではないかという。
ダマシオの『デカルトの誤り』やイーグルマンの諸著作と合わせ読めばさらに理解も深まるだろう。
2019年09月22日
伊佐山紫文398
『あなたの脳のはなし 神経科学者が解き明かす意識の謎』
デイヴィッド・イーグルマン 大田直子訳
ハヤカワノンフィクション文庫
最近、よく、近未来では脳の情報をコンピューター上にアップロードしシミュレーションによって不死となる、などのお話がしたり顔で語られることが多い。
実際、本書でもその「可能性」について語られてはいるのだが、そして啓蒙的な科学者としてその「可能性」の条件について考察しているのだが、どう考えても無理であり、無意味である。
と言うか、そもそもあなたの脳の中に、あなたの意識という実体的な「何か」は存在しない。
せめぎ合う欲動のごうごうたる流れがあるだけだ。
存在しない「何か」をどこかへ移し替えることは出来ないし、しかも本書で繰り返し説明されるように、意識は身体と不可分であり、しかも社会との相互作用によって成立している。
つまり意識をシミュレーションするためには、身体と同時に社会を丸ごとシミュレーションする必要があり、それはこの世をもう一つ複製すると言うことである。
いかに馬鹿げた話か分かろうものだ。
テレビの啓蒙番組を元に作られただけあって、非常にわかりやすい。
朝に紹介した『発達障害と少年犯罪』と合わせ読めば、双方の理解が深まるだろう。
デイヴィッド・イーグルマン 大田直子訳
ハヤカワノンフィクション文庫
最近、よく、近未来では脳の情報をコンピューター上にアップロードしシミュレーションによって不死となる、などのお話がしたり顔で語られることが多い。
実際、本書でもその「可能性」について語られてはいるのだが、そして啓蒙的な科学者としてその「可能性」の条件について考察しているのだが、どう考えても無理であり、無意味である。
と言うか、そもそもあなたの脳の中に、あなたの意識という実体的な「何か」は存在しない。
せめぎ合う欲動のごうごうたる流れがあるだけだ。
存在しない「何か」をどこかへ移し替えることは出来ないし、しかも本書で繰り返し説明されるように、意識は身体と不可分であり、しかも社会との相互作用によって成立している。
つまり意識をシミュレーションするためには、身体と同時に社会を丸ごとシミュレーションする必要があり、それはこの世をもう一つ複製すると言うことである。
いかに馬鹿げた話か分かろうものだ。
テレビの啓蒙番組を元に作られただけあって、非常にわかりやすい。
朝に紹介した『発達障害と少年犯罪』と合わせ読めば、双方の理解が深まるだろう。
2019年09月22日
伊佐山紫文397
『発達障害と少年犯罪』
田淵俊彦 NNNドキュメント取材班 新潮新書
誰もが気づいていながら、誰も触れたがらない、そして「心の闇」などと、訳の分からない非科学的な修辞に押し込んでしまう現実がある。
それは「障害」と「犯罪」の関連である。
この関連を認めてしまうと、障害者=犯罪者という図式が成立してしまい、差別を助長しかねないという空気が、現在の言論空間を支配している。
ましてや「発達障害」と「少年犯罪」を「と」で繋ぐなど、問題外の外、論外の外である。
絶対にやってはいけないことであって、やろうとするような人間は社会から排除すべきだし、実際、排除されてきた。
しかし、統計は残酷だ。
本書が示すように、「発達障害」と「少年犯罪」は明らかにリンクしている。
実は、我が子が3歳になっても一言も発せず、医師からは自閉症を疑われて、私なりに「発達障害」について調べたことがあった。
そうしたら、日本語で読める文献のなんと貧弱なことよ。
そしてデタラメなこと。
結局はほとんどの文献をアメリカを中心とした英語圏から取り寄せることになった。
本書を批判する人々は取材対象の偏りを云々するが、実際、日本で本気でこの問題に取り組んでいるのは本書に登場する人々くらいのものなのだ。
もちろん、研究者はいる。
けれど、それらの研究者のほとんどは、アメリカの制度には関心があっても、日本の子供たちには何の興味も示さない。
私の相談にも「まずは原因を探りましょう」などと、アホなことを言って返す。
「原因」など分かりきっている。
高濃度テストステロン脳症ですよ。
それに、父親としてのこの私が、妊娠時44歳という高齢だったのも影響していることは確実です。
だから、それより問題は、この子をどう育てるか、と言うことです。
とにかく、誰に聞いても、
「問題が出てから考えましょう」
問題が出てからじゃ遅いんですけど!
本書の著者も、当人がすでに気づいているように、恐らく発達障害を抱えて生きて来た一人である。
そして私も間違いなくそうである。
著者が言うように、そして私もそうであるように、堀の内に落ちなかったのはただの偶然や幸運に過ぎない。
問題は、だから「発達障害」を持つ子供たちが「少年犯罪」に至らないようにするために何が出来るか、である。
本書で紹介されているメソッドはまだ端緒についたばかりで、なんとも評価はしかねるが、試行錯誤として有意義であることは確かであろう。
本書の記述は最新の脳科学の知見にも裏付けられており、デイヴィッド・イーグルマンの諸著作(『あなたの知らない脳』『あなたの脳のはなし』共にハヤカワノンフィクション文庫)と合わせ読めば更に理解も深まるだろう。
田淵俊彦 NNNドキュメント取材班 新潮新書
誰もが気づいていながら、誰も触れたがらない、そして「心の闇」などと、訳の分からない非科学的な修辞に押し込んでしまう現実がある。
それは「障害」と「犯罪」の関連である。
この関連を認めてしまうと、障害者=犯罪者という図式が成立してしまい、差別を助長しかねないという空気が、現在の言論空間を支配している。
ましてや「発達障害」と「少年犯罪」を「と」で繋ぐなど、問題外の外、論外の外である。
絶対にやってはいけないことであって、やろうとするような人間は社会から排除すべきだし、実際、排除されてきた。
しかし、統計は残酷だ。
本書が示すように、「発達障害」と「少年犯罪」は明らかにリンクしている。
実は、我が子が3歳になっても一言も発せず、医師からは自閉症を疑われて、私なりに「発達障害」について調べたことがあった。
そうしたら、日本語で読める文献のなんと貧弱なことよ。
そしてデタラメなこと。
結局はほとんどの文献をアメリカを中心とした英語圏から取り寄せることになった。
本書を批判する人々は取材対象の偏りを云々するが、実際、日本で本気でこの問題に取り組んでいるのは本書に登場する人々くらいのものなのだ。
もちろん、研究者はいる。
けれど、それらの研究者のほとんどは、アメリカの制度には関心があっても、日本の子供たちには何の興味も示さない。
私の相談にも「まずは原因を探りましょう」などと、アホなことを言って返す。
「原因」など分かりきっている。
高濃度テストステロン脳症ですよ。
それに、父親としてのこの私が、妊娠時44歳という高齢だったのも影響していることは確実です。
だから、それより問題は、この子をどう育てるか、と言うことです。
とにかく、誰に聞いても、
「問題が出てから考えましょう」
問題が出てからじゃ遅いんですけど!
本書の著者も、当人がすでに気づいているように、恐らく発達障害を抱えて生きて来た一人である。
そして私も間違いなくそうである。
著者が言うように、そして私もそうであるように、堀の内に落ちなかったのはただの偶然や幸運に過ぎない。
問題は、だから「発達障害」を持つ子供たちが「少年犯罪」に至らないようにするために何が出来るか、である。
本書で紹介されているメソッドはまだ端緒についたばかりで、なんとも評価はしかねるが、試行錯誤として有意義であることは確かであろう。
本書の記述は最新の脳科学の知見にも裏付けられており、デイヴィッド・イーグルマンの諸著作(『あなたの知らない脳』『あなたの脳のはなし』共にハヤカワノンフィクション文庫)と合わせ読めば更に理解も深まるだろう。
2019年09月22日
伊佐山紫文396
高度経済成長期の列島改造を自然破壊と呼ぶかどうかはその人の価値判断によるのだろうし、そもそも人間にとって「自然」って何? って話でもある。
日田の私の家の前を流れていた小川・中城川は、そもそも材木を運ぶための運河で、自然でも何でもない、人間の人間による人間のための構築物にすぎない。
だが、そこに住むオイカワやタナゴやカワニナはどうなのか。
私にとっては紛れもない「自然」だったし、味噌汁の出汁となるカワニナなど、もはや体の一部だった。
それが高度経済成長で一変した。
まだ小川の体を成していた運河は、三面がコンクリートで貼られ、まさに水を流すだけの水路となった。
下水道など整備されるのはずっとあとのこと。
清流はただのドブになった。
確かに小川だった頃は、大雨のたびに溢れて玄関に下駄を浮かべたり、酷いときは便所と井戸が繋がって赤痢や疫痢が蔓延したりした。
保健所から来た白い服のおじさんたちが消毒薬を撒く光景は日常でもあった。
あの頃になど、決して戻れるものではない。
もちろん今では下水道も整備され、水質は改善してユスリカの大量発生などはなくなったし、コンクリートの三面張りも、若い人たちにはこれはこれで風情なのかも知れない。
そもそも、全てが「自然」ではないのだから、どのような光景に情緒を感じるのかは個人的な主観でしかない。
のだろうか?
という疑問を最近抱くようになった。
人間の、と言って大げさなら、日本人の原風景とでも言うべき「自然」があるのではないか。
近代的な「個人」の主観に還元されない「自然」というものが、私たちの心の根っこにはあるのではないか。
今では、そんなことを考えている。
日田の私の家の前を流れていた小川・中城川は、そもそも材木を運ぶための運河で、自然でも何でもない、人間の人間による人間のための構築物にすぎない。
だが、そこに住むオイカワやタナゴやカワニナはどうなのか。
私にとっては紛れもない「自然」だったし、味噌汁の出汁となるカワニナなど、もはや体の一部だった。
それが高度経済成長で一変した。
まだ小川の体を成していた運河は、三面がコンクリートで貼られ、まさに水を流すだけの水路となった。
下水道など整備されるのはずっとあとのこと。
清流はただのドブになった。
確かに小川だった頃は、大雨のたびに溢れて玄関に下駄を浮かべたり、酷いときは便所と井戸が繋がって赤痢や疫痢が蔓延したりした。
保健所から来た白い服のおじさんたちが消毒薬を撒く光景は日常でもあった。
あの頃になど、決して戻れるものではない。
もちろん今では下水道も整備され、水質は改善してユスリカの大量発生などはなくなったし、コンクリートの三面張りも、若い人たちにはこれはこれで風情なのかも知れない。
そもそも、全てが「自然」ではないのだから、どのような光景に情緒を感じるのかは個人的な主観でしかない。
のだろうか?
という疑問を最近抱くようになった。
人間の、と言って大げさなら、日本人の原風景とでも言うべき「自然」があるのではないか。
近代的な「個人」の主観に還元されない「自然」というものが、私たちの心の根っこにはあるのではないか。
今では、そんなことを考えている。
2019年09月22日
伊佐山紫文395
私が理学部出身で、専攻が魚類学だと聞くと、たいていの人が驚いた顔をする。
確かに、大学院を中退してからの道行きは、専攻とは全く違うものだったから、意外ととられるかも知れない。
それでも、私の中ではちゃんと一本の筋が通っていた。
それは「エコロジー」である。
訳せば「生態学」とか、「自然保護」とか、「環境保全」とか、いろいろな言葉になるんだろうが、とにかく、自然の中の人間を意識する、みたいな、ボヤッとした意味である。
私が物心つき始めた頃は、高度経済成長、日本列島改造の真っ最中で、エコロジーなど完全無視のエコノミー(経済)優先、家の前の小川が化けた3面コンクリート張りの運河からは合成洗剤の泡が立ちのぼり、清流のカゲロウに代わり、汚水に強いユスリカが大量発生したりした。
改造前の小川に親しんでいた私は、この世の流れに強烈な憤りを感じた。
エコノミーより、エコロジーだろ、と。
そんな私は、高校時代は科学部に入って日田市内の河川の汚染状況を調べ、各種の賞を取ったし、博物館の年報に論文が掲載されたりもした。
その流れで、進学先は愛媛大学の理学部生物学科を選んだ。
当時、淡水の生態学ではここが日本、と言うか、世界でもトップを走っていたから。
しかも、愛媛大学の農学部には環境学科があり、ダイオキシン研究では、ここも世界のトップを走っている。
生態学の原理的な理論を学びながら環境問題を考えるには、理想の大学だと思えたのだった。
若い、と言ってしまえば、それはそれ。
とにかく、エコロジーに明け暮れる学生時代をおくり、そのあげく、原発がらみで大学院を中退、流浪の日々を経て、KADOKAWAの雑誌に環境問題の連載を書かせてもらうことになった。
結局、私の原点はエコロジーだし、その意味で、次回公演
「レイチェル・カーソン やめなはれDDT!」
はその原点を見つめ直すものになるだろうと思っている。
もちろん、難しいものにはならない。
「クララ・シューマン 天才のヨメはん」
と同様、楽しいものにしたいと思っている。
乞うご期待。
確かに、大学院を中退してからの道行きは、専攻とは全く違うものだったから、意外ととられるかも知れない。
それでも、私の中ではちゃんと一本の筋が通っていた。
それは「エコロジー」である。
訳せば「生態学」とか、「自然保護」とか、「環境保全」とか、いろいろな言葉になるんだろうが、とにかく、自然の中の人間を意識する、みたいな、ボヤッとした意味である。
私が物心つき始めた頃は、高度経済成長、日本列島改造の真っ最中で、エコロジーなど完全無視のエコノミー(経済)優先、家の前の小川が化けた3面コンクリート張りの運河からは合成洗剤の泡が立ちのぼり、清流のカゲロウに代わり、汚水に強いユスリカが大量発生したりした。
改造前の小川に親しんでいた私は、この世の流れに強烈な憤りを感じた。
エコノミーより、エコロジーだろ、と。
そんな私は、高校時代は科学部に入って日田市内の河川の汚染状況を調べ、各種の賞を取ったし、博物館の年報に論文が掲載されたりもした。
その流れで、進学先は愛媛大学の理学部生物学科を選んだ。
当時、淡水の生態学ではここが日本、と言うか、世界でもトップを走っていたから。
しかも、愛媛大学の農学部には環境学科があり、ダイオキシン研究では、ここも世界のトップを走っている。
生態学の原理的な理論を学びながら環境問題を考えるには、理想の大学だと思えたのだった。
若い、と言ってしまえば、それはそれ。
とにかく、エコロジーに明け暮れる学生時代をおくり、そのあげく、原発がらみで大学院を中退、流浪の日々を経て、KADOKAWAの雑誌に環境問題の連載を書かせてもらうことになった。
結局、私の原点はエコロジーだし、その意味で、次回公演
「レイチェル・カーソン やめなはれDDT!」
はその原点を見つめ直すものになるだろうと思っている。
もちろん、難しいものにはならない。
「クララ・シューマン 天才のヨメはん」
と同様、楽しいものにしたいと思っている。
乞うご期待。
2019年09月22日
伊佐山紫文395
私が理学部出身で、専攻が魚類学だと聞くと、たいていの人が驚いた顔をする。
確かに、大学院を中退してからの道行きは、専攻とは全く違うものだったから、意外ととられるかも知れない。
それでも、私の中ではちゃんと一本の筋が通っていた。
それは「エコロジー」である。
訳せば「生態学」とか、「自然保護」とか、「環境保全」とか、いろいろな言葉になるんだろうが、とにかく、自然の中の人間を意識する、みたいな、ボヤッとした意味である。
私が物心つき始めた頃は、高度経済成長、日本列島改造の真っ最中で、エコロジーなど完全無視のエコノミー(経済)優先、家の前の小川が化けた3面コンクリート張りの運河からは合成洗剤の泡が立ちのぼり、清流のカゲロウに代わり、汚水に強いユスリカが大量発生したりした。
改造前の小川に親しんでいた私は、この世の流れに強烈な憤りを感じた。
エコノミーより、エコロジーだろ、と。
そんな私は、高校時代は科学部に入って日田市内の河川の汚染状況を調べ、各種の賞を取ったし、博物館の年報に論文が掲載されたりもした。
その流れで、進学先は愛媛大学の理学部生物学科を選んだ。
当時、淡水の生態学ではここが日本、と言うか、世界でもトップを走っていたから。
しかも、愛媛大学の農学部には環境学科があり、ダイオキシン研究では、ここも世界のトップを走っている。
生態学の原理的な理論を学びながら環境問題を考えるには、理想の大学だと思えたのだった。
若い、と言ってしまえば、それはそれ。
とにかく、エコロジーに明け暮れる学生時代をおくり、そのあげく、原発がらみで大学院を中退、流浪の日々を経て、KADOKAWAの雑誌に環境問題の連載を書かせてもらうことになった。
結局、私の原点はエコロジーだし、その意味で、次回公演
「レイチェル・カーソン やめなはれDDT!」
はその原点を見つめ直すものになるだろうと思っている。
もちろん、難しいものにはならない。
「クララ・シューマン 天才のヨメはん」
と同様、楽しいものにしたいと思っている。
乞うご期待。
確かに、大学院を中退してからの道行きは、専攻とは全く違うものだったから、意外ととられるかも知れない。
それでも、私の中ではちゃんと一本の筋が通っていた。
それは「エコロジー」である。
訳せば「生態学」とか、「自然保護」とか、「環境保全」とか、いろいろな言葉になるんだろうが、とにかく、自然の中の人間を意識する、みたいな、ボヤッとした意味である。
私が物心つき始めた頃は、高度経済成長、日本列島改造の真っ最中で、エコロジーなど完全無視のエコノミー(経済)優先、家の前の小川が化けた3面コンクリート張りの運河からは合成洗剤の泡が立ちのぼり、清流のカゲロウに代わり、汚水に強いユスリカが大量発生したりした。
改造前の小川に親しんでいた私は、この世の流れに強烈な憤りを感じた。
エコノミーより、エコロジーだろ、と。
そんな私は、高校時代は科学部に入って日田市内の河川の汚染状況を調べ、各種の賞を取ったし、博物館の年報に論文が掲載されたりもした。
その流れで、進学先は愛媛大学の理学部生物学科を選んだ。
当時、淡水の生態学ではここが日本、と言うか、世界でもトップを走っていたから。
しかも、愛媛大学の農学部には環境学科があり、ダイオキシン研究では、ここも世界のトップを走っている。
生態学の原理的な理論を学びながら環境問題を考えるには、理想の大学だと思えたのだった。
若い、と言ってしまえば、それはそれ。
とにかく、エコロジーに明け暮れる学生時代をおくり、そのあげく、原発がらみで大学院を中退、流浪の日々を経て、KADOKAWAの雑誌に環境問題の連載を書かせてもらうことになった。
結局、私の原点はエコロジーだし、その意味で、次回公演
「レイチェル・カーソン やめなはれDDT!」
はその原点を見つめ直すものになるだろうと思っている。
もちろん、難しいものにはならない。
「クララ・シューマン 天才のヨメはん」
と同様、楽しいものにしたいと思っている。
乞うご期待。
2019年09月22日
伊佐山紫文394
子育てをしていると、どうしても、息子と自分の少年時代とを重ねてしまう。
それは良いのだが、自分がして欲しかったことを息子にやろうとしてしまう。
ピアノ、書道、英語……
そりゃ、やっていれば、将来、なんかの役に立つだろうが、その「将来」とやらが、親にどれほど見通せているのかって話。
私は基本、放任の野放しだった。
親は悪しき戦後教育の産物で、子どもの自主性だの自由だのを奉じて、結局は無責任にほったらかした。
と言うより、まず父親は、この資本主義の世の中があと十年も続くとは思っていないものだから、子どもの教育よりもこの世の変革に情熱を注いだ。
「将来」の見通しがそもそも狂っていたのだ。
母親は、女学校始まって以来の才女と言われ、自分から勉強をする子だったので、まさか我が子が、言われなければ宿題もやらないとは思いもしなかった。
勝手にやってるだろうとチェックもしない。
で、学校に言われてキレる。
その繰り返し。
現実には、学校の宿題を家でやったことなど一度もなく、すべて居残りだった。
その頃(小4~小6)の担任は教員だった母の元同僚で、なまじ私の家庭事情を知っているものだから、敢えて介入することはなかった。
小3で、すでに教員を一人辞めさせた、前科のある子どもである。
しかも、親も親である。
とにかく関わるのも面倒くさい。
放っておけ。
今では、この人たちの気持ちが手に取るように分かる。
実は、息子が3歳になっても一言も発せず、これはおかしいと文献を漁りはじめ「ギフテッド」という存在にたどり着いた。
一言で言えば「才能を与えられた(ギフテッド)子」ということなのだが、この「才能」と言うのがやっかいで、決してこれを持たされた子に幸福をもたらすようなものではない。
息子の場合、パズルを解いたり、ものを組み立てたりするのは、同世代の子よりも圧倒的に勝っていたのだが、言葉が無い。
アインシュタインやファインマン、日本では湯川秀樹など、ノーベル賞をとるような物理学者が幼少期、言葉が遅かったことを心配されたことはよく知られていて、そこから調べて、おそらくは理系の「ギフテッド」だろうと当たりをつけた。
で、その過程で、我がことに思い至った。
私はルービックキューブを自力で6面揃えることが出来る。
別になんてことの無いアルゴリズムで、時間はかかるが、単なる物理的な作業である。
これが実は大変なことだと、妻が1面も整えられないのを見て、初めて気づいた。
私は常人ではない。
私も「ギフテッド」の一人なのだ。
それも、育て方を間違えられた。
父も、母も、常人ではなく「ギフテッド」だったのだ。
それも、戦争と戦後という時代の中で、育て方を間違えられた「ギフテッド」。
これに気づいたとき、スーッと、自分の人生の来し方が見通せたような気がした。
そして、我が子の行く末もスーッと見えてきた、ような気がした。
実は悲しいことに、ほとんどの「ギフテッド」には悲惨な将来しか待っていない。
実際、私の父母は二人ともアル中で亡くなったし、何より「バカと天才は紙一重」などという格言もあるくらいだ。
この世は「ギフテッド」のために出来てはいない。
だから「ギフテッド」はどの時点かで必ずドロップアウトする。
私は小3で学校と全面戦争してドロップアウトしたし、少年院の子どもたちは平均よりもIQが高いという調査結果もある。
これは大変だと、息子が幼稚園の年中さんの頃から、市の教育委員会や入学予定の小学校に話をして、何とかドロップアウトだけは避けようとしてきた。
今では小6にもなって、クラスではほとんど一言も発せずにいるから、もしかしたらドロップアウトしてるかも知れないが、それでも妙な軋轢はないようだ。
立志伝中の天才の多くが悲惨な末路を迎えているのは他人事ではない。
だからこそ、ピアノ、書道、英語……となるのだが、人の言うことを聞かないのが「ギフテッド」の常で、どうしたもんか。
それは良いのだが、自分がして欲しかったことを息子にやろうとしてしまう。
ピアノ、書道、英語……
そりゃ、やっていれば、将来、なんかの役に立つだろうが、その「将来」とやらが、親にどれほど見通せているのかって話。
私は基本、放任の野放しだった。
親は悪しき戦後教育の産物で、子どもの自主性だの自由だのを奉じて、結局は無責任にほったらかした。
と言うより、まず父親は、この資本主義の世の中があと十年も続くとは思っていないものだから、子どもの教育よりもこの世の変革に情熱を注いだ。
「将来」の見通しがそもそも狂っていたのだ。
母親は、女学校始まって以来の才女と言われ、自分から勉強をする子だったので、まさか我が子が、言われなければ宿題もやらないとは思いもしなかった。
勝手にやってるだろうとチェックもしない。
で、学校に言われてキレる。
その繰り返し。
現実には、学校の宿題を家でやったことなど一度もなく、すべて居残りだった。
その頃(小4~小6)の担任は教員だった母の元同僚で、なまじ私の家庭事情を知っているものだから、敢えて介入することはなかった。
小3で、すでに教員を一人辞めさせた、前科のある子どもである。
しかも、親も親である。
とにかく関わるのも面倒くさい。
放っておけ。
今では、この人たちの気持ちが手に取るように分かる。
実は、息子が3歳になっても一言も発せず、これはおかしいと文献を漁りはじめ「ギフテッド」という存在にたどり着いた。
一言で言えば「才能を与えられた(ギフテッド)子」ということなのだが、この「才能」と言うのがやっかいで、決してこれを持たされた子に幸福をもたらすようなものではない。
息子の場合、パズルを解いたり、ものを組み立てたりするのは、同世代の子よりも圧倒的に勝っていたのだが、言葉が無い。
アインシュタインやファインマン、日本では湯川秀樹など、ノーベル賞をとるような物理学者が幼少期、言葉が遅かったことを心配されたことはよく知られていて、そこから調べて、おそらくは理系の「ギフテッド」だろうと当たりをつけた。
で、その過程で、我がことに思い至った。
私はルービックキューブを自力で6面揃えることが出来る。
別になんてことの無いアルゴリズムで、時間はかかるが、単なる物理的な作業である。
これが実は大変なことだと、妻が1面も整えられないのを見て、初めて気づいた。
私は常人ではない。
私も「ギフテッド」の一人なのだ。
それも、育て方を間違えられた。
父も、母も、常人ではなく「ギフテッド」だったのだ。
それも、戦争と戦後という時代の中で、育て方を間違えられた「ギフテッド」。
これに気づいたとき、スーッと、自分の人生の来し方が見通せたような気がした。
そして、我が子の行く末もスーッと見えてきた、ような気がした。
実は悲しいことに、ほとんどの「ギフテッド」には悲惨な将来しか待っていない。
実際、私の父母は二人ともアル中で亡くなったし、何より「バカと天才は紙一重」などという格言もあるくらいだ。
この世は「ギフテッド」のために出来てはいない。
だから「ギフテッド」はどの時点かで必ずドロップアウトする。
私は小3で学校と全面戦争してドロップアウトしたし、少年院の子どもたちは平均よりもIQが高いという調査結果もある。
これは大変だと、息子が幼稚園の年中さんの頃から、市の教育委員会や入学予定の小学校に話をして、何とかドロップアウトだけは避けようとしてきた。
今では小6にもなって、クラスではほとんど一言も発せずにいるから、もしかしたらドロップアウトしてるかも知れないが、それでも妙な軋轢はないようだ。
立志伝中の天才の多くが悲惨な末路を迎えているのは他人事ではない。
だからこそ、ピアノ、書道、英語……となるのだが、人の言うことを聞かないのが「ギフテッド」の常で、どうしたもんか。
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
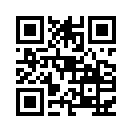
アクセスカウンタ
読者登録
