2019年10月03日
伊佐山紫文408
『種の起源(上下)』
ダーウィン著 渡辺政隆訳
光文社古典新訳文庫
ベンヤミンの『ドイツ悲劇(悲哀劇)の根源』でもそうだが、書誌的に正確な訳(ちくま学芸文庫)と読みやすい訳(講談社文芸文庫)とは明らかに違う。
研究者には大事だろうが、一般人にとっては初版と最終版の違いなどどうでも良いし、とにかく何が書いてあるのかが伝わらなければ翻訳する意義などない。
ベンヤミンの『ドイツ悲劇(悲哀劇)の根源』を読むなら、絶対に講談社文芸文庫の版をお薦めする。
どれだけ書誌的に正確であっても、読み通せなければ無意味なのだ。
その意味で、八杉竜一訳岩波文庫版のダーウィン『種の起源』は最悪だった。
そもそものダーウィンの英語のくどさ・わかりにくさをそのまま写し取った本文に、しかも「初版ではどうの」「この言葉は第何版から云々」という注がやたらと入り込んでいて、著書としての主張の流れが見えず、読み通すのが非常に困難な難物だった。
今回、古典新訳文庫版の新訳で『種の起源』を読んでみると、透明な文体を通してダーウィンの主張が全き姿で現前に現れ、あまりのインパクトに、正直、震え上がった。
世界を変えた本というものがあるとするなら、これ以上のものはないと断言する。
とにかく「世界」というものの見方が一変するのである。
生き物は自身よりも多くの子孫を残し、子孫の中で適応したものが生き残る。
そのようなせめぎ合い(自然淘汰)のなかで進化が起こり、現存の「種」が生まれた。「種」の「起源」に「神」など必要ないのである。
自然淘汰という単純なアルゴリズムの無限の繰り返しによってこの「世界」は出来上がったのだし、この、たった今も出来上がりつつある。
この世界が出来上がるのに「目的」や「意思」など必要ないし、「神」など不要だと言うことだ。
しかも、つまり人間は「神」の似姿などではなく、サルと祖先を共有する動物の一種でしかない。
だとしたら……
人生の目的は、ただ子孫を残すことだけなのか?
弱者は滅んで当然なのか?
慈愛などそもそも無意味で、むしろ社会「進化」の妨げになるのではないか?
資本主義が伝統的な倫理観を侵食していた時代、この『種の起源』は伝統の全てを土台から掘り崩し、むしろ近代の思想的基盤を築いた。
「社会ダーウィニズム」という思想的怪物が、これ以後、世界を席巻することになる。
障害者が、少数民族が、有色人種が、まさにダーウィンの名において差別され、収容され、去勢され、抹殺されることになるだろう。
そういう思想的インパクトを全て理解した上での新訳であり、ジャンケンの後出しのような狡さはあるが、それでも見事な仕事である。
ダーウィン著 渡辺政隆訳
光文社古典新訳文庫
ベンヤミンの『ドイツ悲劇(悲哀劇)の根源』でもそうだが、書誌的に正確な訳(ちくま学芸文庫)と読みやすい訳(講談社文芸文庫)とは明らかに違う。
研究者には大事だろうが、一般人にとっては初版と最終版の違いなどどうでも良いし、とにかく何が書いてあるのかが伝わらなければ翻訳する意義などない。
ベンヤミンの『ドイツ悲劇(悲哀劇)の根源』を読むなら、絶対に講談社文芸文庫の版をお薦めする。
どれだけ書誌的に正確であっても、読み通せなければ無意味なのだ。
その意味で、八杉竜一訳岩波文庫版のダーウィン『種の起源』は最悪だった。
そもそものダーウィンの英語のくどさ・わかりにくさをそのまま写し取った本文に、しかも「初版ではどうの」「この言葉は第何版から云々」という注がやたらと入り込んでいて、著書としての主張の流れが見えず、読み通すのが非常に困難な難物だった。
今回、古典新訳文庫版の新訳で『種の起源』を読んでみると、透明な文体を通してダーウィンの主張が全き姿で現前に現れ、あまりのインパクトに、正直、震え上がった。
世界を変えた本というものがあるとするなら、これ以上のものはないと断言する。
とにかく「世界」というものの見方が一変するのである。
生き物は自身よりも多くの子孫を残し、子孫の中で適応したものが生き残る。
そのようなせめぎ合い(自然淘汰)のなかで進化が起こり、現存の「種」が生まれた。「種」の「起源」に「神」など必要ないのである。
自然淘汰という単純なアルゴリズムの無限の繰り返しによってこの「世界」は出来上がったのだし、この、たった今も出来上がりつつある。
この世界が出来上がるのに「目的」や「意思」など必要ないし、「神」など不要だと言うことだ。
しかも、つまり人間は「神」の似姿などではなく、サルと祖先を共有する動物の一種でしかない。
だとしたら……
人生の目的は、ただ子孫を残すことだけなのか?
弱者は滅んで当然なのか?
慈愛などそもそも無意味で、むしろ社会「進化」の妨げになるのではないか?
資本主義が伝統的な倫理観を侵食していた時代、この『種の起源』は伝統の全てを土台から掘り崩し、むしろ近代の思想的基盤を築いた。
「社会ダーウィニズム」という思想的怪物が、これ以後、世界を席巻することになる。
障害者が、少数民族が、有色人種が、まさにダーウィンの名において差別され、収容され、去勢され、抹殺されることになるだろう。
そういう思想的インパクトを全て理解した上での新訳であり、ジャンケンの後出しのような狡さはあるが、それでも見事な仕事である。
2019年10月03日
伊佐山紫文407
「だったら、これ、この白いの牛乳じゃねえのかよ」
と、息子が言う。
「前から言うてるやろ、お前が味噌のツブツブが嫌やって言うから、ツブのない豆乳で味噌を造って味噌汁にしとるんやって」
「だったら、これ、味噌汁か!」
「当たり前や。ホワイトシチューとでも思とったんか」
「知らんかったわ」
「ゴボウの入ったホワイトシチューがどこにある」
子どもは味覚に敏感だから、と、色々気を遣ってきた。
味噌汁の大豆や米のツブが気になると言うから、ツブの全くない豆乳で味噌を造って……と、そんな感じで。
そんな手品のタネが、最近、次々と暴かれている。
息子本人が知恵をつけてきたのもあるし、むしろ私が、積極的にタネ明かしをしている。
どんだけ気を遣ってきたか、思い知らせてやろうと。
豆乳味噌のタネはこんな感じ。
材料:豆乳1リットル、塩100グラム、米麹100グラム
これを混ぜ合わせ、ヨーグルトメーカーで60度12時間、あとはミキサーで米麹の残骸をすりつぶせば出来上がりである。
実になめらかな白味噌で、これはペットボトルに入れて冷蔵庫へ。
野菜を煮た出汁に適量流し込めば、それだけで白い味噌汁が出来上がる。
味噌こしで解く必要もない。
これを、息子は、何年もの間、牛乳を使った何かのスープだと思い込んでいたらしい。
まあ、そう思い込ませていたんだけどね。
と、息子が言う。
「前から言うてるやろ、お前が味噌のツブツブが嫌やって言うから、ツブのない豆乳で味噌を造って味噌汁にしとるんやって」
「だったら、これ、味噌汁か!」
「当たり前や。ホワイトシチューとでも思とったんか」
「知らんかったわ」
「ゴボウの入ったホワイトシチューがどこにある」
子どもは味覚に敏感だから、と、色々気を遣ってきた。
味噌汁の大豆や米のツブが気になると言うから、ツブの全くない豆乳で味噌を造って……と、そんな感じで。
そんな手品のタネが、最近、次々と暴かれている。
息子本人が知恵をつけてきたのもあるし、むしろ私が、積極的にタネ明かしをしている。
どんだけ気を遣ってきたか、思い知らせてやろうと。
豆乳味噌のタネはこんな感じ。
材料:豆乳1リットル、塩100グラム、米麹100グラム
これを混ぜ合わせ、ヨーグルトメーカーで60度12時間、あとはミキサーで米麹の残骸をすりつぶせば出来上がりである。
実になめらかな白味噌で、これはペットボトルに入れて冷蔵庫へ。
野菜を煮た出汁に適量流し込めば、それだけで白い味噌汁が出来上がる。
味噌こしで解く必要もない。
これを、息子は、何年もの間、牛乳を使った何かのスープだと思い込んでいたらしい。
まあ、そう思い込ませていたんだけどね。
2019年10月03日
伊佐山紫文406
「OSAKAもの・ことづくりオープンフォーラム」
という催しに参加してきた。
内容は検索すれば出てくるので他に譲るが、興味深いことが幾つかあった。
なかでも、パネリストの皆さんが皆「歴史」を自らの財産として語り、議論を深めていったことには「さもありなん」と膝を打った(実際には打たなかったが)。
この場合の「歴史」とは「ストーリー」としての「ヒストリー」であり、言ってみれば「由来話」、端的には「物語」である。
思うに、人間の歴史は「物語」と「反物語」を波打つように反復し、反復し、飽くことなく反復してきた。
平成の30年は「反物語」のポストモダンの時代であり、無歴史、無故郷、グローバリズムとコスモポリタニズムの、無色透明でサラサラなモノゴトが価値とされた。
そこでの歴史は単なる「事実」であって、「事実」と「事実」を繋ぐ試みは、客観性を欠く、単なる「物語」だとして排斥された。
実存主義はおどろおどろしいだけだし、マルクス主義はソ連と一緒に滅んだし、故郷は捨てて懐かしむものでしかないし、家族など社会的構築物でしかない。
全ては「物語」でしかないのだ。
「物語」など、「神話」と一緒、我々を縛る鎖でしかない。
さあ、「物語」や「神話」を解体し、自らを縛る鎖を解いて自由になろう!
てなわけで、これはもう人類の歴史が繰り返してきた思想史的波の一方の際だとしか言い様がない。
で、それが行き詰まって、令和の時代、再び「物語」が復活してきた。
それを「ナショナリズム」だとか「ポピュリズム」だとか、ある種の人々は言いつのるのだろうが、まあ、勝手にすれば良い。
時代の波は変えられない。
しかも、最新の脳科学の知見によれば、私たちの脳は「物語」を欲しており、「物語」を通してしか事物を認識することは出来ない。
とすれば、人が、人に、何かを伝えようとすれば、「物語」(つまり歴史)を利用するのが手っ取り早いし、確実だと言うことだ。
もちろん、この「物語」も次第に陳腐化して、いつかは再び「反物語」の時代が始まるのだが、それはまた将来の話である。
今の令和の新時代、「物語」の時代が始まった。
そこで夙川座の出番である。
となれば、良いなあ。
という催しに参加してきた。
内容は検索すれば出てくるので他に譲るが、興味深いことが幾つかあった。
なかでも、パネリストの皆さんが皆「歴史」を自らの財産として語り、議論を深めていったことには「さもありなん」と膝を打った(実際には打たなかったが)。
この場合の「歴史」とは「ストーリー」としての「ヒストリー」であり、言ってみれば「由来話」、端的には「物語」である。
思うに、人間の歴史は「物語」と「反物語」を波打つように反復し、反復し、飽くことなく反復してきた。
平成の30年は「反物語」のポストモダンの時代であり、無歴史、無故郷、グローバリズムとコスモポリタニズムの、無色透明でサラサラなモノゴトが価値とされた。
そこでの歴史は単なる「事実」であって、「事実」と「事実」を繋ぐ試みは、客観性を欠く、単なる「物語」だとして排斥された。
実存主義はおどろおどろしいだけだし、マルクス主義はソ連と一緒に滅んだし、故郷は捨てて懐かしむものでしかないし、家族など社会的構築物でしかない。
全ては「物語」でしかないのだ。
「物語」など、「神話」と一緒、我々を縛る鎖でしかない。
さあ、「物語」や「神話」を解体し、自らを縛る鎖を解いて自由になろう!
てなわけで、これはもう人類の歴史が繰り返してきた思想史的波の一方の際だとしか言い様がない。
で、それが行き詰まって、令和の時代、再び「物語」が復活してきた。
それを「ナショナリズム」だとか「ポピュリズム」だとか、ある種の人々は言いつのるのだろうが、まあ、勝手にすれば良い。
時代の波は変えられない。
しかも、最新の脳科学の知見によれば、私たちの脳は「物語」を欲しており、「物語」を通してしか事物を認識することは出来ない。
とすれば、人が、人に、何かを伝えようとすれば、「物語」(つまり歴史)を利用するのが手っ取り早いし、確実だと言うことだ。
もちろん、この「物語」も次第に陳腐化して、いつかは再び「反物語」の時代が始まるのだが、それはまた将来の話である。
今の令和の新時代、「物語」の時代が始まった。
そこで夙川座の出番である。
となれば、良いなあ。
2019年10月03日
伊佐山紫文405
ショスタコーヴィチの第五交響曲を聴いてきた。
オーケストラ・アンサンブル・フォルツァの演奏で、八尾市文化会館プリズムホール。
この曲は別名「宇宙戦艦ポチョムキン」とも言われ、終楽章のブラスの大迫力で知られている。
実際、フォルツァの皆さんも、この楽章を演奏したくて選曲したんだろうな、と分かる熱演で、感動いたしました。
第一楽章展開部冒頭の不気味なピアノを、我が夙川座ゆかりの白藤望さんで聴けたのも良かった。
同じく白藤さんのチェレスタも印象的でした。
また、この曲はフルートが命なのですが、これも素晴らしかった。
と、簡単に言うが、この曲、単に「聴きました、感動しました」では済まない背景があって、それを言い出すともう、演奏も鑑賞も不可能になってしまう。
実は第五交響曲の前に、ショスタコーヴィチは第四交響曲を書いていたのだが、もしこの第四交響曲を発表していたら、確実に殺されていた。
時代はソ連、それもスターリン時代である。
多くの芸術家が「ブルジョア臭い」とのレッテルを貼られ、次々と投獄、殺戮されていた。
ショスタコーヴィチもオペラやバレーが共産党からの批判を受け、投獄寸前だった。
ここで、ブルジョア音楽として批判されていたマーラーの影響が明らかな第四交響曲を発表したら。
間違いなく、投獄され、飢え死にさせられていただろう。
「ブルジョア臭い」芸術家には最も苦しい死を与えるのがプロレタリア的正義である、とされていたのだ。
こんな世で生き残るためには、共産党の歓心を得なければならない。
そこで起死回生の一手として作曲したのがこの交響曲第五番なのである。
帝政ロシア時代の暗黒の苦悩から共産革命を経て歓喜にいたる(と解釈できる)この曲は、共産党を含む大衆に、大受けに受けた。
人気作曲家となったショスタコーヴィチを、共産党は生かしておくしかなかった。
未だに偽書かどうか確定しないヴォルコフ著『ショスタコーヴィチの証言』では、この終楽章は「強制された歓喜」(水野忠夫訳)とされ、手放しの快演、たとえばバーンスタインのものなどは薄っぺらいとさえ言われる。
いやいや、そもそもバーンスタインごときに何を求めるんだと言いたくもなるが、やはり、『証言』を踏まえたハイティンクら西側と、ムラヴィンスキー(初演者でもある)やロジェストヴェンスキーらソ連派では表現が微妙に異なることは否めない。
ショスタコーヴィチのその後の展開を考えれば、私は『証言』の側に立つ。
つまり、終楽章は「強制された歓喜」だろうと思う。
けれど、強制されていようがいまいが、「歓喜」は「歓喜」なのだとも思う。
試みに心の中で「梅干し、レモン、梅干し、レモン」と十数回唱えてみたまえ、自然と唾液が口を満たすだろう。
これは強制的に「梅干し、レモン」を聞かされても同じで、人間の生理反応である。
音楽も同じ、感動するように書かれていれば、安っぽいと思いつつも感動する。
これはもう、人間の生理反応なのであって、誰もそれを否定できない。
だから、堪能しましたよ。
フォルツァの皆さん、ご苦労様でした。
ちなみになんでこの曲がマニアの間で「宇宙戦艦ポチョムキン」と呼ばれるのかと言えば、エイゼンシュテインの名作映画『戦艦ポチョムキン』に使われているから。
戦前に作られたサイレント映画に、戦後になって第二楽章の音楽が後付けされたもので、私など、しばらくは、この映画のためにショスタコーヴィチが書いたのだと思っていた。
そのくらい、合ってる。
今回の演奏でも、あの、揚々とした戦艦シーンが頭に浮かびましたよ。
ちなみに、クラシック曲のアンソロジーで『交響戦艦ショスタコーヴィチ ~ ヒーロー風クラシック名曲集 』というCDが、なんとナクソスレーベルから出ていて、曲目を見ただけで笑えます。
『交響戦艦ショスタコーヴィチ ~ ヒーロー風クラシック名曲集 』で検索っ!
オーケストラ・アンサンブル・フォルツァの演奏で、八尾市文化会館プリズムホール。
この曲は別名「宇宙戦艦ポチョムキン」とも言われ、終楽章のブラスの大迫力で知られている。
実際、フォルツァの皆さんも、この楽章を演奏したくて選曲したんだろうな、と分かる熱演で、感動いたしました。
第一楽章展開部冒頭の不気味なピアノを、我が夙川座ゆかりの白藤望さんで聴けたのも良かった。
同じく白藤さんのチェレスタも印象的でした。
また、この曲はフルートが命なのですが、これも素晴らしかった。
と、簡単に言うが、この曲、単に「聴きました、感動しました」では済まない背景があって、それを言い出すともう、演奏も鑑賞も不可能になってしまう。
実は第五交響曲の前に、ショスタコーヴィチは第四交響曲を書いていたのだが、もしこの第四交響曲を発表していたら、確実に殺されていた。
時代はソ連、それもスターリン時代である。
多くの芸術家が「ブルジョア臭い」とのレッテルを貼られ、次々と投獄、殺戮されていた。
ショスタコーヴィチもオペラやバレーが共産党からの批判を受け、投獄寸前だった。
ここで、ブルジョア音楽として批判されていたマーラーの影響が明らかな第四交響曲を発表したら。
間違いなく、投獄され、飢え死にさせられていただろう。
「ブルジョア臭い」芸術家には最も苦しい死を与えるのがプロレタリア的正義である、とされていたのだ。
こんな世で生き残るためには、共産党の歓心を得なければならない。
そこで起死回生の一手として作曲したのがこの交響曲第五番なのである。
帝政ロシア時代の暗黒の苦悩から共産革命を経て歓喜にいたる(と解釈できる)この曲は、共産党を含む大衆に、大受けに受けた。
人気作曲家となったショスタコーヴィチを、共産党は生かしておくしかなかった。
未だに偽書かどうか確定しないヴォルコフ著『ショスタコーヴィチの証言』では、この終楽章は「強制された歓喜」(水野忠夫訳)とされ、手放しの快演、たとえばバーンスタインのものなどは薄っぺらいとさえ言われる。
いやいや、そもそもバーンスタインごときに何を求めるんだと言いたくもなるが、やはり、『証言』を踏まえたハイティンクら西側と、ムラヴィンスキー(初演者でもある)やロジェストヴェンスキーらソ連派では表現が微妙に異なることは否めない。
ショスタコーヴィチのその後の展開を考えれば、私は『証言』の側に立つ。
つまり、終楽章は「強制された歓喜」だろうと思う。
けれど、強制されていようがいまいが、「歓喜」は「歓喜」なのだとも思う。
試みに心の中で「梅干し、レモン、梅干し、レモン」と十数回唱えてみたまえ、自然と唾液が口を満たすだろう。
これは強制的に「梅干し、レモン」を聞かされても同じで、人間の生理反応である。
音楽も同じ、感動するように書かれていれば、安っぽいと思いつつも感動する。
これはもう、人間の生理反応なのであって、誰もそれを否定できない。
だから、堪能しましたよ。
フォルツァの皆さん、ご苦労様でした。
ちなみになんでこの曲がマニアの間で「宇宙戦艦ポチョムキン」と呼ばれるのかと言えば、エイゼンシュテインの名作映画『戦艦ポチョムキン』に使われているから。
戦前に作られたサイレント映画に、戦後になって第二楽章の音楽が後付けされたもので、私など、しばらくは、この映画のためにショスタコーヴィチが書いたのだと思っていた。
そのくらい、合ってる。
今回の演奏でも、あの、揚々とした戦艦シーンが頭に浮かびましたよ。
ちなみに、クラシック曲のアンソロジーで『交響戦艦ショスタコーヴィチ ~ ヒーロー風クラシック名曲集 』というCDが、なんとナクソスレーベルから出ていて、曲目を見ただけで笑えます。
『交響戦艦ショスタコーヴィチ ~ ヒーロー風クラシック名曲集 』で検索っ!
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
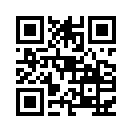
アクセスカウンタ
読者登録
