2018年01月17日
伊佐山紫文135
平成7年(1995年)1月17日、兵庫県西宮市で阪神・淡路大震災の直撃を受けた。
前日まで帰省していた日田で風邪を引き、熱をおして博多で飛行機に乗り、到着は伊丹空港、阪急伊丹駅から電車に乗って仁川に帰ってきた。
阪急伊丹駅はその後倒壊、仁川へと向かう宝塚線の線路の上には新幹線の架橋が落ちた。
私の住んでいた田近野町の隣は段上町、西宮で最も死者の出た地域のひとつである。
当日の朝、私はいつものように5時半に起床し、それでも熱があったので、テレビもつけたまま、一旦布団にもどった。
そこで5時46分のあの揺れである。
最初の揺れはそれほどでもなかった。
「大丈夫」と、隣に寝ていた妻に声をかけたくらい。
けれど、間髪を置かずにやってきたジェットコースターのような揺れには言葉をなくし、布団の中に丸くなった。
妻が悲鳴を上げ、布団の上に本棚が倒れてきた。
揺れがおさまり、せーの、で本棚を元に戻した。
本がバラバラと布団の上に落ちた。
窓の外で話し声がする。
見れば、何人もの人影が歩んでいる。
「きっとカーラジオを聞きにでたんや。状況聞いてみて」
私は風邪を引いて喉が潰れていたので、妻に聞いて貰った。
「何か情報ありませんか?」
「震源淡路島! 震度6!」
暗闇の中うずくまっていると、次第に空が白んできた。
ヴァチッという音と共に電気が復旧し、テレビがついた。
ブラウン管を下に転けていたテレビを台に戻すと……倒れた高速道、液状化した六甲アイランド、長田の火事……
以後、何度も何度も眺めることになる映像が、ナマで次々と流れていたのだった。
もともと散らかっていた部屋は足の踏み場もない惨状で、それは台所も寝室も書斎も同じ。
ただ一つ無事だった本棚は、「世界文学全集」が筑摩書房と集英社と二揃え入ったもので、揺れの向きなど、さまざまな要因はあるだろうが、後になって、その写真を人に見せ、
「やはり、世界文学は安定感が違う」などと冗談を言ったものである。
ちなみに中公の「日本の文学」80巻は本棚ごと崩壊した。
これも写真に撮って人に見せ、
「震災は「日本の文学」を枠組みごと破壊した」などと言ったものである。
これから十数年後、三歳の息子が、息子には煉瓦にしか見えない中公版『哲学の歴史』全十三巻を使って「きかんしゃトーマス」のレールを敷いたとき、
「哲学の歴史を基礎に化石燃料による産業革命が花開いた」などと、撮った写真にキャプションを添えたりした。
話を震災に戻せば、とにかく当時「防災」などという観念は皆無である。
特に関西は地震のない地域だと言われてもいた。
だから何の備えもない。
ガスも電気もすぐに復旧したから、水もじき出るだろうと、貴重なトイレの水もその朝に使い切ってしまった。
このあと数ヶ月の断水が待っているというのに。
職場に行くという妻を何とか押しとどめ、二人でテレビを見ながら部屋を片付ける。
あれもいらない、これもいらない、と惚けたような、興奮したような断捨離である。
たった今、家を出て、自分たちにも何か出来ることがあるかも知れない、などという発想もまた皆無である。
この年がボランティア元年と言われたように、それまで災害ボランティアという発想自体がなかったのだ。
言葉としてはもちろんあったが、それは限りなく自己満足に近いもので、有効な戦力とは考えられていなかった。
うちのほんの近所、段上町では、いや、田近野でも、その時、住民自身による懸命の捜索・救助活動が行われていたというのに、私たちがしていたことと言えばチマチマと部屋の片付けである。
数日経って被害の全容が明らかになるにつれ、近所でも多くの方がなくなったことを知り、猛烈な自責の念に駆られた。
そして、今からでも何か出来るはずだと、呼ばれれば東京にまで行って講演した。
「とにかく被災地に来て現状を見て下さい。将来の東京を心配するより、今の被災地を何とかして下さい」
と。
初めて聞く「被災者」の生の声は圧倒的だったらしく、ボランティア志願者が何人も出た。
しばらくして、家の横の道を自転車で走っていると、再開した学校で習ったのか、子供たちが下校の春風の中、中島みゆきの『時代』を唄いながら歩んでいた。
私は小学生の長い列の脇に自転車を止めて立ち尽くし、泣いた。
この震災という経験をこの子たちが笑って話せる日が来るんだろうか、と、私は本気で嗚咽した。
もうあの時の私と同じ、30過ぎの大人になっただろう、あの子たち、笑顔で震災体験を語れているだろうか。
震災のあと、みんな些細なことで泣いた。
人の話を聞いて泣き、自分で語って自分で泣き、憤って泣き、喜んで泣き、何も出来ない悔しさに泣き、そして生き延びた後ろめたさに泣き、それでもこの今を生きている喜びを微笑みあった。
街の道端のそこここで、
「○○さん、あなた生きてたの! 良かったね!」
と、普段なら滅多にないような挨拶が聞かれ、ひとしきり語り合い、泣き合ったあとで、
「がんばろう」
と笑顔で声を掛け合って別れるのだった。
人間の、日本人の、最も美しい瞬間に何度も立ち会えたこと、それは私の生涯の誇りである。
『時代』の歌詞をここに揚げるのはJASRACが恐ろしくて不可能なので、震災20周年の気持ちも込めて作った私自身の『日本レクイエム』を張り付ける。
合掌。
「日本レクイエム」
『初め』
君は今 眠りに落ちて
大いなる 初めに帰る
ああ! 君は 初めに帰る
幼き日 時の熟しに
身をゆだね ただ走りゆく
大いなる 時の熟しよ
ふと聞けば 風のそよぎに
神わびて その声のする
そこにいる そこにある君
我もまた 初めに帰り
大いなる 眠りに落ちん
ああ! 我も 初めに帰る
ああ! 君と 初めに帰る
大いなる 時の熟しと
『雲』
数尽きぬ 想い出は
心より 溢れ出ぬ
いざさらば 白き雲
青空に 消えゆきぬ
地の底の 同胞(はらから)も
仰ぎ見よ 白き雲
我もまた 去りゆく身
雲送り ただ涙
数尽きぬ 想い出に
雲送り 一人佇む
『幸』
古(いにしえ)の 悲し調べに
人泣きぬ ただ人泣きぬ
現世(うつしよ)の 悲しさだめに
人泣きぬ ただ人泣きぬ
泣きてあれ 悲しみの子よ
今日はただ 悲しみの日ぞ
そしてまた この世の幸を
汲みつつも 在りし日の幸
忘れじや いつの世までも
前日まで帰省していた日田で風邪を引き、熱をおして博多で飛行機に乗り、到着は伊丹空港、阪急伊丹駅から電車に乗って仁川に帰ってきた。
阪急伊丹駅はその後倒壊、仁川へと向かう宝塚線の線路の上には新幹線の架橋が落ちた。
私の住んでいた田近野町の隣は段上町、西宮で最も死者の出た地域のひとつである。
当日の朝、私はいつものように5時半に起床し、それでも熱があったので、テレビもつけたまま、一旦布団にもどった。
そこで5時46分のあの揺れである。
最初の揺れはそれほどでもなかった。
「大丈夫」と、隣に寝ていた妻に声をかけたくらい。
けれど、間髪を置かずにやってきたジェットコースターのような揺れには言葉をなくし、布団の中に丸くなった。
妻が悲鳴を上げ、布団の上に本棚が倒れてきた。
揺れがおさまり、せーの、で本棚を元に戻した。
本がバラバラと布団の上に落ちた。
窓の外で話し声がする。
見れば、何人もの人影が歩んでいる。
「きっとカーラジオを聞きにでたんや。状況聞いてみて」
私は風邪を引いて喉が潰れていたので、妻に聞いて貰った。
「何か情報ありませんか?」
「震源淡路島! 震度6!」
暗闇の中うずくまっていると、次第に空が白んできた。
ヴァチッという音と共に電気が復旧し、テレビがついた。
ブラウン管を下に転けていたテレビを台に戻すと……倒れた高速道、液状化した六甲アイランド、長田の火事……
以後、何度も何度も眺めることになる映像が、ナマで次々と流れていたのだった。
もともと散らかっていた部屋は足の踏み場もない惨状で、それは台所も寝室も書斎も同じ。
ただ一つ無事だった本棚は、「世界文学全集」が筑摩書房と集英社と二揃え入ったもので、揺れの向きなど、さまざまな要因はあるだろうが、後になって、その写真を人に見せ、
「やはり、世界文学は安定感が違う」などと冗談を言ったものである。
ちなみに中公の「日本の文学」80巻は本棚ごと崩壊した。
これも写真に撮って人に見せ、
「震災は「日本の文学」を枠組みごと破壊した」などと言ったものである。
これから十数年後、三歳の息子が、息子には煉瓦にしか見えない中公版『哲学の歴史』全十三巻を使って「きかんしゃトーマス」のレールを敷いたとき、
「哲学の歴史を基礎に化石燃料による産業革命が花開いた」などと、撮った写真にキャプションを添えたりした。
話を震災に戻せば、とにかく当時「防災」などという観念は皆無である。
特に関西は地震のない地域だと言われてもいた。
だから何の備えもない。
ガスも電気もすぐに復旧したから、水もじき出るだろうと、貴重なトイレの水もその朝に使い切ってしまった。
このあと数ヶ月の断水が待っているというのに。
職場に行くという妻を何とか押しとどめ、二人でテレビを見ながら部屋を片付ける。
あれもいらない、これもいらない、と惚けたような、興奮したような断捨離である。
たった今、家を出て、自分たちにも何か出来ることがあるかも知れない、などという発想もまた皆無である。
この年がボランティア元年と言われたように、それまで災害ボランティアという発想自体がなかったのだ。
言葉としてはもちろんあったが、それは限りなく自己満足に近いもので、有効な戦力とは考えられていなかった。
うちのほんの近所、段上町では、いや、田近野でも、その時、住民自身による懸命の捜索・救助活動が行われていたというのに、私たちがしていたことと言えばチマチマと部屋の片付けである。
数日経って被害の全容が明らかになるにつれ、近所でも多くの方がなくなったことを知り、猛烈な自責の念に駆られた。
そして、今からでも何か出来るはずだと、呼ばれれば東京にまで行って講演した。
「とにかく被災地に来て現状を見て下さい。将来の東京を心配するより、今の被災地を何とかして下さい」
と。
初めて聞く「被災者」の生の声は圧倒的だったらしく、ボランティア志願者が何人も出た。
しばらくして、家の横の道を自転車で走っていると、再開した学校で習ったのか、子供たちが下校の春風の中、中島みゆきの『時代』を唄いながら歩んでいた。
私は小学生の長い列の脇に自転車を止めて立ち尽くし、泣いた。
この震災という経験をこの子たちが笑って話せる日が来るんだろうか、と、私は本気で嗚咽した。
もうあの時の私と同じ、30過ぎの大人になっただろう、あの子たち、笑顔で震災体験を語れているだろうか。
震災のあと、みんな些細なことで泣いた。
人の話を聞いて泣き、自分で語って自分で泣き、憤って泣き、喜んで泣き、何も出来ない悔しさに泣き、そして生き延びた後ろめたさに泣き、それでもこの今を生きている喜びを微笑みあった。
街の道端のそこここで、
「○○さん、あなた生きてたの! 良かったね!」
と、普段なら滅多にないような挨拶が聞かれ、ひとしきり語り合い、泣き合ったあとで、
「がんばろう」
と笑顔で声を掛け合って別れるのだった。
人間の、日本人の、最も美しい瞬間に何度も立ち会えたこと、それは私の生涯の誇りである。
『時代』の歌詞をここに揚げるのはJASRACが恐ろしくて不可能なので、震災20周年の気持ちも込めて作った私自身の『日本レクイエム』を張り付ける。
合掌。
「日本レクイエム」
『初め』
君は今 眠りに落ちて
大いなる 初めに帰る
ああ! 君は 初めに帰る
幼き日 時の熟しに
身をゆだね ただ走りゆく
大いなる 時の熟しよ
ふと聞けば 風のそよぎに
神わびて その声のする
そこにいる そこにある君
我もまた 初めに帰り
大いなる 眠りに落ちん
ああ! 我も 初めに帰る
ああ! 君と 初めに帰る
大いなる 時の熟しと
『雲』
数尽きぬ 想い出は
心より 溢れ出ぬ
いざさらば 白き雲
青空に 消えゆきぬ
地の底の 同胞(はらから)も
仰ぎ見よ 白き雲
我もまた 去りゆく身
雲送り ただ涙
数尽きぬ 想い出に
雲送り 一人佇む
『幸』
古(いにしえ)の 悲し調べに
人泣きぬ ただ人泣きぬ
現世(うつしよ)の 悲しさだめに
人泣きぬ ただ人泣きぬ
泣きてあれ 悲しみの子よ
今日はただ 悲しみの日ぞ
そしてまた この世の幸を
汲みつつも 在りし日の幸
忘れじや いつの世までも
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
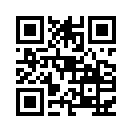
アクセスカウンタ
読者登録
