2018年11月09日
伊佐山紫文221
今日、買い物に行こうとエレベーターに乗り、さっき扉のところに留まっていたのはカゲロウじゃなかったかと思い直し、一階についてもういちど九階まで戻って確かめた。
詳しい種類は分からないけれど、おそらくチラカゲロウの一種である。
周囲を確かめると、脱皮したカラが残っている。
亜成虫のままここまで飛んできて、いや、飛ばされてきて、仕方なくエレベーターのところで脱皮したのだろう。
おいおい、英語でメイ・フライ(五月の虫)って言うくらい、夏の虫だよ。
たいてい世界各地でも儚いものの象徴とされ、確かに成虫になってからは水も食料も取ることなく生殖だけして一日で死んでいく。
不完全変態だから蛹を作ることはない。
ただし、幼虫から亜成虫を経て、成虫に至るという変わった変態の仕方をする。
日本には日記文学の傑作『蜻蛉日記』があるけれど、これは本文を読む限り、カゲロウではなく、クモの子だろうと思われる。
クモの子が自らの糸に載って飛んで行くのが陽の光を浴びて、一瞬、キラリと儚く輝く、その様子のことではないかと、本文を読んだときには思った。
種類は違うが、北杜夫が「薄馬鹿下郎」と呼んだウスバカゲロウというのもいる。
この仲間の幼虫はアリジゴクとして知られている。
また、大分の中津で長くものを書いていらっしゃった故松下竜一さんには、初期のエッセイというか何というか、これも日記文学になるのか『ウドンゲの花』という作品がある。
この「ウドンゲの花」はクサカゲロウの卵である。
若い頃は、松下さんの著作は出るもの全て読んでいたのだが、西宮に越してきて、とある作業所と親しくなり(ここでピンと来る人はピンと来る)、非常に幻滅して読むのを止めたことがある。
その前から、松下さんの取材対象になった人と話す機会が何度かあり、その取材の手法にはかなり疑問を感じていたのではあったけれど。
思えばその一人故伊藤ルイさんのご両親大杉栄と伊藤野枝を殺したのは甘粕正彦と言われており、その甘粕正彦が理事長を勤めた満州映画社の物語『ふたりのヨシコ 李香蘭と男装の麗人』をこの私が作ることになったのだから、まあ、縁と言えば縁である。
カゲロウの幼虫は全て水の中で暮らしており、水質の汚染には敏感なので、淡水の汚染の指標となっている。
私は日田高時代、このカゲロウの研究に没頭していた。
花月川、三隈川、その支流に至るまで、どこの瀬にどんな種類のカゲロウがいるか、日田市内の分布を一夏をかけて調べ上げた。
これは県で賞を取ったし、博物館の紀要にも載ったから、その論文は日田市内を探せばどこかにはあると思う。
現在の分布を誰か調べれば、比較が出来て楽しいと思うよ。
私が調べた頃はまだ下水道がなくて、酷い状態のところが多かったから。
で、買い物から帰って来たら、そのカゲロウ君がまさに私の家の扉に貼り付いている。
ダメだよ。
ちゃんと相手を探しに行かなきゃ。
息を吹きかけると、どこかへ飛んでいった。
見つかると良いね、お相手……無理か、こんな季節になってしまっちゃ。
よく「棲み分け」という言葉を政治学や社会学でも使うことがあるけれど、これは元々はカゲロウの分布のこと。
京都大学の伝説的な生物学者である可児藤吉や今西錦司が京都市内のカゲロウの幼虫の分布を調べ、その様子を「棲み分け」と呼んだのが始まり。
その後、今西錦司は「棲み分け」理論に基づく壮大な今西進化論を提唱するのだが、まあ、今となっては白昼夢みたいなものだ。
カゲロウにキブネンシスとか、京都の地名のついたものがあるのは夢の名残か。
(昆虫は見たくない人もいるから、本文には貼ってません。写真集の中に入ってます)
高校の頃、国語の授業でほとんど即興で書いた詩
蜉蝣
それは石の上にいる
何も言わず
自分の内部の変化に息を殺して
可憐な体は軽くなり
大空を求め
透明な羽は伸びきった。
泡沫の中で過ごした一年
未来を信じ朝を恋して
五月の風に誘われ飛翔する
Danの抜け殻は少年期の墓標となり
若きSpinnerは旅立つ
二四時間の命のために
Dan:カゲロウの亜成虫
Spinner:カゲロウの成虫
詳しい種類は分からないけれど、おそらくチラカゲロウの一種である。
周囲を確かめると、脱皮したカラが残っている。
亜成虫のままここまで飛んできて、いや、飛ばされてきて、仕方なくエレベーターのところで脱皮したのだろう。
おいおい、英語でメイ・フライ(五月の虫)って言うくらい、夏の虫だよ。
たいてい世界各地でも儚いものの象徴とされ、確かに成虫になってからは水も食料も取ることなく生殖だけして一日で死んでいく。
不完全変態だから蛹を作ることはない。
ただし、幼虫から亜成虫を経て、成虫に至るという変わった変態の仕方をする。
日本には日記文学の傑作『蜻蛉日記』があるけれど、これは本文を読む限り、カゲロウではなく、クモの子だろうと思われる。
クモの子が自らの糸に載って飛んで行くのが陽の光を浴びて、一瞬、キラリと儚く輝く、その様子のことではないかと、本文を読んだときには思った。
種類は違うが、北杜夫が「薄馬鹿下郎」と呼んだウスバカゲロウというのもいる。
この仲間の幼虫はアリジゴクとして知られている。
また、大分の中津で長くものを書いていらっしゃった故松下竜一さんには、初期のエッセイというか何というか、これも日記文学になるのか『ウドンゲの花』という作品がある。
この「ウドンゲの花」はクサカゲロウの卵である。
若い頃は、松下さんの著作は出るもの全て読んでいたのだが、西宮に越してきて、とある作業所と親しくなり(ここでピンと来る人はピンと来る)、非常に幻滅して読むのを止めたことがある。
その前から、松下さんの取材対象になった人と話す機会が何度かあり、その取材の手法にはかなり疑問を感じていたのではあったけれど。
思えばその一人故伊藤ルイさんのご両親大杉栄と伊藤野枝を殺したのは甘粕正彦と言われており、その甘粕正彦が理事長を勤めた満州映画社の物語『ふたりのヨシコ 李香蘭と男装の麗人』をこの私が作ることになったのだから、まあ、縁と言えば縁である。
カゲロウの幼虫は全て水の中で暮らしており、水質の汚染には敏感なので、淡水の汚染の指標となっている。
私は日田高時代、このカゲロウの研究に没頭していた。
花月川、三隈川、その支流に至るまで、どこの瀬にどんな種類のカゲロウがいるか、日田市内の分布を一夏をかけて調べ上げた。
これは県で賞を取ったし、博物館の紀要にも載ったから、その論文は日田市内を探せばどこかにはあると思う。
現在の分布を誰か調べれば、比較が出来て楽しいと思うよ。
私が調べた頃はまだ下水道がなくて、酷い状態のところが多かったから。
で、買い物から帰って来たら、そのカゲロウ君がまさに私の家の扉に貼り付いている。
ダメだよ。
ちゃんと相手を探しに行かなきゃ。
息を吹きかけると、どこかへ飛んでいった。
見つかると良いね、お相手……無理か、こんな季節になってしまっちゃ。
よく「棲み分け」という言葉を政治学や社会学でも使うことがあるけれど、これは元々はカゲロウの分布のこと。
京都大学の伝説的な生物学者である可児藤吉や今西錦司が京都市内のカゲロウの幼虫の分布を調べ、その様子を「棲み分け」と呼んだのが始まり。
その後、今西錦司は「棲み分け」理論に基づく壮大な今西進化論を提唱するのだが、まあ、今となっては白昼夢みたいなものだ。
カゲロウにキブネンシスとか、京都の地名のついたものがあるのは夢の名残か。
(昆虫は見たくない人もいるから、本文には貼ってません。写真集の中に入ってます)
高校の頃、国語の授業でほとんど即興で書いた詩
蜉蝣
それは石の上にいる
何も言わず
自分の内部の変化に息を殺して
可憐な体は軽くなり
大空を求め
透明な羽は伸びきった。
泡沫の中で過ごした一年
未来を信じ朝を恋して
五月の風に誘われ飛翔する
Danの抜け殻は少年期の墓標となり
若きSpinnerは旅立つ
二四時間の命のために
Dan:カゲロウの亜成虫
Spinner:カゲロウの成虫
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
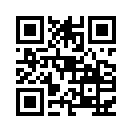
アクセスカウンタ
読者登録
