2018年01月03日
伊佐山紫文123
前に子役二人が歌う「マルマルモリモリ」なんてのが流行って、ちょっとラテン語をかじった耳には正気の沙汰とは思えなかった。
「マル」は「悪」で、「モリ」は「死」。
「悪悪死死」
なんでこんな歌になったのか、誰か教えてやらなかったのかと訝しむが、深読みすれば、これは「メメント・モリ」の一種なのではないか。
「メメント」は英語で言えばリメンバー、「思え」。
「モリ」は「死」。
メメント・モリ、死を思え。
つまり生に限りがあること、言い換えれば自らも死すべき存在であることを常に思い、一瞬一瞬を誠実に精一杯生きよ、ということ。
メメント・モリ。
こんな元気で可愛い子供たちであっても、いつかは死の時を迎えなければならない。
マルマルモリモリ。
ああ、なんて切ない歌なんだ。
こういうメメント・モリの伝統は、実は日本に古来から有って、たとえば、一休禅師の歌とされている、
「門松や 冥土の旅の 一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」
正月になって皆さん浮かれているけれど、それでも死出の旅の途中であることに変わりはないんだぞ、と。
杖にしゃれこうべを付けて、一休さんはこの歌を唄いながら正月の京都を闊歩したという。
これが本当に一休さんの歌なのか、疑問は残っているようだが、それでも江戸時代にはそう信じられ、ある種の「メメント・モリ」として人口に膾炙していたのは事実である。
で、懐かしく思い出すのは、息子の8歳の誕生日、
「お前も8歳になったんだね」と言うと、すかさず、
「また一歩、死に近づいたって話?」
まあ、そういうことではあるけれど……
いや8歳から「メメント・モリ」しなくても……
と言うわけで、「死に太郎」は一休禅師に倣った私なりの「メメント・モリ」でした。
「マル」は「悪」で、「モリ」は「死」。
「悪悪死死」
なんでこんな歌になったのか、誰か教えてやらなかったのかと訝しむが、深読みすれば、これは「メメント・モリ」の一種なのではないか。
「メメント」は英語で言えばリメンバー、「思え」。
「モリ」は「死」。
メメント・モリ、死を思え。
つまり生に限りがあること、言い換えれば自らも死すべき存在であることを常に思い、一瞬一瞬を誠実に精一杯生きよ、ということ。
メメント・モリ。
こんな元気で可愛い子供たちであっても、いつかは死の時を迎えなければならない。
マルマルモリモリ。
ああ、なんて切ない歌なんだ。
こういうメメント・モリの伝統は、実は日本に古来から有って、たとえば、一休禅師の歌とされている、
「門松や 冥土の旅の 一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」
正月になって皆さん浮かれているけれど、それでも死出の旅の途中であることに変わりはないんだぞ、と。
杖にしゃれこうべを付けて、一休さんはこの歌を唄いながら正月の京都を闊歩したという。
これが本当に一休さんの歌なのか、疑問は残っているようだが、それでも江戸時代にはそう信じられ、ある種の「メメント・モリ」として人口に膾炙していたのは事実である。
で、懐かしく思い出すのは、息子の8歳の誕生日、
「お前も8歳になったんだね」と言うと、すかさず、
「また一歩、死に近づいたって話?」
まあ、そういうことではあるけれど……
いや8歳から「メメント・モリ」しなくても……
と言うわけで、「死に太郎」は一休禅師に倣った私なりの「メメント・モリ」でした。
2018年01月03日
伊佐山紫文122
この話をし始めると、息子は「止めろ!」と叫んで襲いかかってくる。
あるところにお爺さんとお婆さんが住んでいました。
ある日、お爺さんは山へ芝刈りに、お婆さんは川へ洗濯へ行きました。
お婆さんが川で洗濯をしていると、上流から、どんぶらこっこ、どんぶらこっこと、腐りかけた死体が流れてきました。
お婆さんはその死体を家に持って帰りました。
「これは立派な死体ではないか」
とお爺さんも大喜びです。
さっそく料理しようと、お婆さんが包丁で皮をむくと、中から、顔色の悪い、気色の悪い男の子が出てきました。
二人はその子を、死体から生まれた「死に太郎」と名付けて、大切に育てました。
と言っても、もともと死んでいる死に太郎ですから、一日ぐったりと寝てばかり、しかも、得も言われぬ臭い臭いが漂っています。
そんなある日、死に太郎が言いました。
「鬼ヶ島の鬼たちが人々を苦しめているそうです。私が行って、奪われた宝を取り戻してきます」
お爺さんとお婆さんは、実は死に太郎をもてあましていたので、良い厄介払いになると、この申し出を歓迎しました。
門出に、死体から作った「死に団子」を持たせました。
死に太郎が鬼ヶ島に向かっていくと、道に犬が死んでいました。
その死体を肩にかけて歩いて行くと、次にはサルが死んでいました。
その死体を肩にかけて歩いてくと、次にはキジが死んでいました。
それもまた肩にかけ、船に乗り、鬼ヶ島へと漕ぎ出しました。
異臭に気づいた鬼たちはざわめき始めました。
「こ、これは、いったい何の臭いじゃ」
「あれを観ろ、犬と、サルと、キジの死体を抱えた死体がこっちに向かってくるぞ!」
死に太郎は叫びました。
「鬼ども! 人々から奪った宝を返せ!」
鬼たちはあまりの気色の悪さに動顛しました。
「あんなのに上陸されちゃ、かなわん。宝どころの騒ぎじゃない」
鬼たちは死に太郎に言いました。
「返す! 返す! だから、今すぐ帰ってくれ!」
鬼たちは宝を死に太郎の船に投げ入れました。
死に太郎は宝を村に持ち帰りましたが、死臭のついた宝など、だれも持ち帰りません。
死に太郎は最初から死んでいるので死ぬこともなく、お爺さんお婆さんが死んだ後も、宝に囲まれて、いつまでもいつまでも、きっと今でも、たった一人で寝ているのでした。
めでたし、めでたし。
あるところにお爺さんとお婆さんが住んでいました。
ある日、お爺さんは山へ芝刈りに、お婆さんは川へ洗濯へ行きました。
お婆さんが川で洗濯をしていると、上流から、どんぶらこっこ、どんぶらこっこと、腐りかけた死体が流れてきました。
お婆さんはその死体を家に持って帰りました。
「これは立派な死体ではないか」
とお爺さんも大喜びです。
さっそく料理しようと、お婆さんが包丁で皮をむくと、中から、顔色の悪い、気色の悪い男の子が出てきました。
二人はその子を、死体から生まれた「死に太郎」と名付けて、大切に育てました。
と言っても、もともと死んでいる死に太郎ですから、一日ぐったりと寝てばかり、しかも、得も言われぬ臭い臭いが漂っています。
そんなある日、死に太郎が言いました。
「鬼ヶ島の鬼たちが人々を苦しめているそうです。私が行って、奪われた宝を取り戻してきます」
お爺さんとお婆さんは、実は死に太郎をもてあましていたので、良い厄介払いになると、この申し出を歓迎しました。
門出に、死体から作った「死に団子」を持たせました。
死に太郎が鬼ヶ島に向かっていくと、道に犬が死んでいました。
その死体を肩にかけて歩いて行くと、次にはサルが死んでいました。
その死体を肩にかけて歩いてくと、次にはキジが死んでいました。
それもまた肩にかけ、船に乗り、鬼ヶ島へと漕ぎ出しました。
異臭に気づいた鬼たちはざわめき始めました。
「こ、これは、いったい何の臭いじゃ」
「あれを観ろ、犬と、サルと、キジの死体を抱えた死体がこっちに向かってくるぞ!」
死に太郎は叫びました。
「鬼ども! 人々から奪った宝を返せ!」
鬼たちはあまりの気色の悪さに動顛しました。
「あんなのに上陸されちゃ、かなわん。宝どころの騒ぎじゃない」
鬼たちは死に太郎に言いました。
「返す! 返す! だから、今すぐ帰ってくれ!」
鬼たちは宝を死に太郎の船に投げ入れました。
死に太郎は宝を村に持ち帰りましたが、死臭のついた宝など、だれも持ち帰りません。
死に太郎は最初から死んでいるので死ぬこともなく、お爺さんお婆さんが死んだ後も、宝に囲まれて、いつまでもいつまでも、きっと今でも、たった一人で寝ているのでした。
めでたし、めでたし。
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
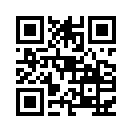
アクセスカウンタ
読者登録
