2017年08月15日
伊佐山紫文26
「フィガロの結婚」の後日談として「フィガロの決戦!」なる大人のコメディを書いたのは、もう4年も前の夏、暑い盛りに冷房のない部屋でベトベトの汗に腕に貼り付く楽譜と格闘しながら書き上げた。
舞台はナポレオンのフランス軍に占領されたセビリア。
ナポレオンに心酔する伯爵と、抗仏ゲリラの頭目になったフィガロ、ゲリラになりたいケルビーノのそれぞれの思惑が絡み合うなか、女たちの平和を求めて逡巡する姿を「フィガロの結婚」の音楽に載せて歌い上げた。
幸い、日本劇作家大会2014豊岡大会での初演は好評で、東京公演も打診されたのだが、これは諸般の事情により実現しなかった。
その後、西宮、大阪と二回の再演を経て、歌と芝居による舞台という、今の夙川座のスタイルを決定する作品となった。
この作品のテーマは「戦争と平和」だが、最初からそうしようと思ったわけではない。
終戦の季節である夏がそうさせたのか、よくわからないが、とにかく、フィナーレは平和を歌い上げるものにしようと思いつき、そこから逆算して物語を創り上げた。
その過程でスペインの歴史を調べ、そのあまりの悲惨さに気が滅入った。
ルネサンスがないというのは、こういうことなのだ、と。
たとえば、当時のヨーロッパで、拷問人にスペイン人が来たと聞くと、罪人は震え上がって自殺したという。
真偽の程はわからないけれど、異端審問が最後まで残っていたスペインならではの逸話だと思う。
そのスペインに「近代」をもたらしたのは、間違いなくナポレオンだった。
だからこそスペインの貴族たちはナポレオンを支持したのだし、そうでなければ占領など出来るわけがない。
ただし「近代」が良いことずくめであるはずもない。
またナポレオンの私利私欲も明らかとなってくる。
ここで「小さな戦争」を意味するスペイン語の「ゲリラ」が登場する。
世界史に「ゲリラ戦」なる戦争が登場した瞬間である。
私の「フィガロの決戦!」では、セビリアのゲリラの頭目となったフィガロと、ゲリラ戦に参加したいケルビーノのそれぞれの思いが二重唱で歌われ、見せ場の一つとなっている。
で、芝居は「平和」を歌い上げるフィナーレで大団円を迎えるのだが、現実は違う。
ナポレオン占領時代がマシだったと思えるような泥沼の内戦へと突入し、血で血を洗う、汚物で汚物を拭うような惨状がスペイン中を覆うことになる。
この惨禍はファシズムと共産主義の対立にまで、つまり、つい最近まで受け継がれ、スペインの近代化を決定的に遅らせることになる。
このような今の視点からすれば、ナポレオンが去ったからと言って、「平和」を言祝いでいられるわけはないのだが、そこはそれ、芝居だから、ホンの一時の幻想として、フィナーレでは高らかに平和を歌い上げた。
モーツァルトの音楽は本当に「平和」にこそふさわしいと、観客の誰もが思ったことだろう。
初演では拍手が鳴り止まず、誰も席を立たず、仕方なく、このような舞台では異例の「アンコール」まで歌うことになった。
終戦の日を記念して、フィナーレの歌詞を張り付けておく。
フィナーレ「平和の鐘を打ち鳴らせ」
伯爵
「空は澄み 風は薫り」
伯爵夫人
「梢鳴く鳥 軽やかに 軽やかに」
全員
平和が来た 争いも、憎しみも
平和な世界が訪れ 平和な世界 いくさ無き
さあ行こう さあ行こう
平和の鐘の音 打ち鳴らし進め 打ち鳴らし行け
平和の鐘を
歌、歌え 踊り、踊れ 平和の鐘、打ち鳴らして
許しの鐘の音 すべてを許し
踊り明かそう
すべてを許し
平和な世界
踊ろう 歌おう 踊ろう
舞台はナポレオンのフランス軍に占領されたセビリア。
ナポレオンに心酔する伯爵と、抗仏ゲリラの頭目になったフィガロ、ゲリラになりたいケルビーノのそれぞれの思惑が絡み合うなか、女たちの平和を求めて逡巡する姿を「フィガロの結婚」の音楽に載せて歌い上げた。
幸い、日本劇作家大会2014豊岡大会での初演は好評で、東京公演も打診されたのだが、これは諸般の事情により実現しなかった。
その後、西宮、大阪と二回の再演を経て、歌と芝居による舞台という、今の夙川座のスタイルを決定する作品となった。
この作品のテーマは「戦争と平和」だが、最初からそうしようと思ったわけではない。
終戦の季節である夏がそうさせたのか、よくわからないが、とにかく、フィナーレは平和を歌い上げるものにしようと思いつき、そこから逆算して物語を創り上げた。
その過程でスペインの歴史を調べ、そのあまりの悲惨さに気が滅入った。
ルネサンスがないというのは、こういうことなのだ、と。
たとえば、当時のヨーロッパで、拷問人にスペイン人が来たと聞くと、罪人は震え上がって自殺したという。
真偽の程はわからないけれど、異端審問が最後まで残っていたスペインならではの逸話だと思う。
そのスペインに「近代」をもたらしたのは、間違いなくナポレオンだった。
だからこそスペインの貴族たちはナポレオンを支持したのだし、そうでなければ占領など出来るわけがない。
ただし「近代」が良いことずくめであるはずもない。
またナポレオンの私利私欲も明らかとなってくる。
ここで「小さな戦争」を意味するスペイン語の「ゲリラ」が登場する。
世界史に「ゲリラ戦」なる戦争が登場した瞬間である。
私の「フィガロの決戦!」では、セビリアのゲリラの頭目となったフィガロと、ゲリラ戦に参加したいケルビーノのそれぞれの思いが二重唱で歌われ、見せ場の一つとなっている。
で、芝居は「平和」を歌い上げるフィナーレで大団円を迎えるのだが、現実は違う。
ナポレオン占領時代がマシだったと思えるような泥沼の内戦へと突入し、血で血を洗う、汚物で汚物を拭うような惨状がスペイン中を覆うことになる。
この惨禍はファシズムと共産主義の対立にまで、つまり、つい最近まで受け継がれ、スペインの近代化を決定的に遅らせることになる。
このような今の視点からすれば、ナポレオンが去ったからと言って、「平和」を言祝いでいられるわけはないのだが、そこはそれ、芝居だから、ホンの一時の幻想として、フィナーレでは高らかに平和を歌い上げた。
モーツァルトの音楽は本当に「平和」にこそふさわしいと、観客の誰もが思ったことだろう。
初演では拍手が鳴り止まず、誰も席を立たず、仕方なく、このような舞台では異例の「アンコール」まで歌うことになった。
終戦の日を記念して、フィナーレの歌詞を張り付けておく。
フィナーレ「平和の鐘を打ち鳴らせ」
伯爵
「空は澄み 風は薫り」
伯爵夫人
「梢鳴く鳥 軽やかに 軽やかに」
全員
平和が来た 争いも、憎しみも
平和な世界が訪れ 平和な世界 いくさ無き
さあ行こう さあ行こう
平和の鐘の音 打ち鳴らし進め 打ち鳴らし行け
平和の鐘を
歌、歌え 踊り、踊れ 平和の鐘、打ち鳴らして
許しの鐘の音 すべてを許し
踊り明かそう
すべてを許し
平和な世界
踊ろう 歌おう 踊ろう
2017年08月15日
伊佐山紫文25
『世界はなぜ「ある」のか? 「究極のなぜ?」を追う哲学の旅』
ジム・ホルト著 寺町朋子訳 ハヤカワ文庫
ハイデッガーの『形而上学入門』は「入門」でも何でもなく、真正面から存在の問い「なぜ何も無いのではなく、何かがあるのか?」を問うた、超難解な哲学書である。
同じ問いを、本書では、まず「宇宙の存在」について、宇宙の始原とは何か、本当に無から有が生じたのかについて、物理学者や天文学者にインタビューして回る。
難解な部分もあるが、数式も出てこず、また、インタビュー前後の食事の様子なども描かれていて、楽しく読める。
後半、「私の存在」へと問いが移ると、こんどは哲学者や作家へのインタビュー。
著者の母親が死に、思い出の場所をあてどなく彷徨うラストには、九年前の母の死を思い出して不覚にも落涙。
哲学書としては荒い。
けれどもきちんとした読後感の残る、人生を少しだけ豊かにしてくれる好著である。
実は30年前、こういう本が書きたくてたまらなかった。
ちょうど浅田彰の『構造と力』が売れてる時期で、こんなのが10万部も売れるのなら、オレ様の書く本は1億部以上売れて当然だと思っていた。
その後、雑誌の仕事に疲れ果て、本が出れば売れるはずだからと執筆に専念した。
で、出した本は売れなかったが、講演の仕事は入って来て、サインを求められることも再々だった。
『ライフステーション』のライバル誌『レタスクラブ』からもインタビューを受け、カラー見開きで写真が載ったこともある。
あの頃はまだ、フォトジェニックだった。
なんてったって、28歳だもの。
そんなこんなで、小金が少し溜まったから、覚悟を決めて長編評論を書こうと思った。
2年かけて書き上げ、『構造と力』と同じ勁草書房に持ち込んだ。
すぐに出版され、専門家からの評価も高く、海外の日本文化研究者の必読書として文化庁が推薦する図書にも選定された。
ただし、売れなかった。
本当に、恥ずかしいくらい。
『ライフステーション』の読者プレゼントに5冊出したが、応募は2通だけ。
編集部でもいらんと言われ、3冊戻って来た。
客観的に見れば、このあたりから時代とズレ始めたのだと思う。
足掻けば足掻くほど泥沼で、そのうち両親は倒れるし、本を出しても売れる当てはないし、日田に帰って法律家にでもなるか、などと司法試験の勉強を始める始末。
こんな私には、ちゃんと一般読者に売れる哲学書を書ける著者が羨ましくてたまらない。
ジム・ホルト著 寺町朋子訳 ハヤカワ文庫
ハイデッガーの『形而上学入門』は「入門」でも何でもなく、真正面から存在の問い「なぜ何も無いのではなく、何かがあるのか?」を問うた、超難解な哲学書である。
同じ問いを、本書では、まず「宇宙の存在」について、宇宙の始原とは何か、本当に無から有が生じたのかについて、物理学者や天文学者にインタビューして回る。
難解な部分もあるが、数式も出てこず、また、インタビュー前後の食事の様子なども描かれていて、楽しく読める。
後半、「私の存在」へと問いが移ると、こんどは哲学者や作家へのインタビュー。
著者の母親が死に、思い出の場所をあてどなく彷徨うラストには、九年前の母の死を思い出して不覚にも落涙。
哲学書としては荒い。
けれどもきちんとした読後感の残る、人生を少しだけ豊かにしてくれる好著である。
実は30年前、こういう本が書きたくてたまらなかった。
ちょうど浅田彰の『構造と力』が売れてる時期で、こんなのが10万部も売れるのなら、オレ様の書く本は1億部以上売れて当然だと思っていた。
その後、雑誌の仕事に疲れ果て、本が出れば売れるはずだからと執筆に専念した。
で、出した本は売れなかったが、講演の仕事は入って来て、サインを求められることも再々だった。
『ライフステーション』のライバル誌『レタスクラブ』からもインタビューを受け、カラー見開きで写真が載ったこともある。
あの頃はまだ、フォトジェニックだった。
なんてったって、28歳だもの。
そんなこんなで、小金が少し溜まったから、覚悟を決めて長編評論を書こうと思った。
2年かけて書き上げ、『構造と力』と同じ勁草書房に持ち込んだ。
すぐに出版され、専門家からの評価も高く、海外の日本文化研究者の必読書として文化庁が推薦する図書にも選定された。
ただし、売れなかった。
本当に、恥ずかしいくらい。
『ライフステーション』の読者プレゼントに5冊出したが、応募は2通だけ。
編集部でもいらんと言われ、3冊戻って来た。
客観的に見れば、このあたりから時代とズレ始めたのだと思う。
足掻けば足掻くほど泥沼で、そのうち両親は倒れるし、本を出しても売れる当てはないし、日田に帰って法律家にでもなるか、などと司法試験の勉強を始める始末。
こんな私には、ちゃんと一般読者に売れる哲学書を書ける著者が羨ましくてたまらない。
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
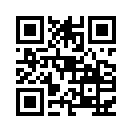
アクセスカウンタ
読者登録
