2017年08月22日
伊佐山紫文35
昨日は9月4日に出演する番組の打ち合わせに関西ラジオに行ってきた。
放送は朝8時10分からという、微妙な時間なのだが、主婦(主夫)が台所で聴いていることを期待しよう。
あるいはドライバーが運転しながら聴いていることを。
それで、いつも不思議に思っているのだが、テレビと違って、普通、ラジオは事前の打ち合わせがない。
少なくともこれまで私が出演したラジオでは全くなかった。
誰がその日のコメンテーターかもわからないものだから、スタジオに入ったらかねての知り合いがいて、その日のテーマそっちのけで雑談にふけったこともあった。
こんなことも、事故ではなく、むしろ即興的なアクシデントとして楽しむ雰囲気が確かにラジオにはある。
けれどそうも言ってはいられない場合もある。
今回の打ち合わせは夙川座から提案したもので、それは、約20分という限られた出演時間の中で、歌も流し、こちらの訴えたいこともしっかりと伝えるには、事前の話し合いが絶対に必要だと判断したからだった。
放送はまだだから何とも言えないが、現時点では、ディレクターと直接会って話が出来て良かったと思う。
あとは夙川座が本番で頑張るだけだ。
ラジオ関西での打ち合わせの後は、兵庫県に神戸事件関係の企画を提案し、その後、記事を載せてくれた『兵庫ジャーナル』にお礼参り。
神戸という街は様々な機能が中心部にギュッとまとまっているから、必要な個所を徒歩で効率よく回ることが出来る。
夙川座のように車のない組織には実にありがたい街である。
思えば30年近く前、まだ20代だった私も神戸の街を歩き回った。
夜は、同業の編集者やライターやデザイナーやイラストレーターやカメラマンや新聞記者と、毎晩のように飲み歩いた。
払いはもちろん会社の金である。
私が使う会社の金など微々たるものだが、東京から編集長が来たときなどはそれこそ豪遊で、当時は一皿数万円もした神戸ビーフのステーキを、飲み会の参加者全員にふるまったりした。
「伊佐山、とにかく(相手に)会いに行け、電話ですまそうとするな」
が編集長の口癖で、この後に、
「電話で女が口説けるか?」
が続く。
シラフの時は繊細、酒を飲めば豪放磊落、酔いつぶれた編集長をホテルや新神戸駅まで送って行くのはいつも私の役目だった。
もうとっくに亡くなったが、その名は今でも関西の編集者の記憶に残っている。
「とにかく会いに行け」
その教えは今でも私の中に生きているし、間違ってはいないと思う。
ただし、時代は変わった。
「テレクラ」なんてものは論外としても、メールで女を口説ける時代にはなった。
それでも編集長は言うんだろうな。
「とにかく会いに行け、メールですまそうとするな」
はい!
これからも神戸の街を歩き回り、とにかく会いに行きます。
放送は朝8時10分からという、微妙な時間なのだが、主婦(主夫)が台所で聴いていることを期待しよう。
あるいはドライバーが運転しながら聴いていることを。
それで、いつも不思議に思っているのだが、テレビと違って、普通、ラジオは事前の打ち合わせがない。
少なくともこれまで私が出演したラジオでは全くなかった。
誰がその日のコメンテーターかもわからないものだから、スタジオに入ったらかねての知り合いがいて、その日のテーマそっちのけで雑談にふけったこともあった。
こんなことも、事故ではなく、むしろ即興的なアクシデントとして楽しむ雰囲気が確かにラジオにはある。
けれどそうも言ってはいられない場合もある。
今回の打ち合わせは夙川座から提案したもので、それは、約20分という限られた出演時間の中で、歌も流し、こちらの訴えたいこともしっかりと伝えるには、事前の話し合いが絶対に必要だと判断したからだった。
放送はまだだから何とも言えないが、現時点では、ディレクターと直接会って話が出来て良かったと思う。
あとは夙川座が本番で頑張るだけだ。
ラジオ関西での打ち合わせの後は、兵庫県に神戸事件関係の企画を提案し、その後、記事を載せてくれた『兵庫ジャーナル』にお礼参り。
神戸という街は様々な機能が中心部にギュッとまとまっているから、必要な個所を徒歩で効率よく回ることが出来る。
夙川座のように車のない組織には実にありがたい街である。
思えば30年近く前、まだ20代だった私も神戸の街を歩き回った。
夜は、同業の編集者やライターやデザイナーやイラストレーターやカメラマンや新聞記者と、毎晩のように飲み歩いた。
払いはもちろん会社の金である。
私が使う会社の金など微々たるものだが、東京から編集長が来たときなどはそれこそ豪遊で、当時は一皿数万円もした神戸ビーフのステーキを、飲み会の参加者全員にふるまったりした。
「伊佐山、とにかく(相手に)会いに行け、電話ですまそうとするな」
が編集長の口癖で、この後に、
「電話で女が口説けるか?」
が続く。
シラフの時は繊細、酒を飲めば豪放磊落、酔いつぶれた編集長をホテルや新神戸駅まで送って行くのはいつも私の役目だった。
もうとっくに亡くなったが、その名は今でも関西の編集者の記憶に残っている。
「とにかく会いに行け」
その教えは今でも私の中に生きているし、間違ってはいないと思う。
ただし、時代は変わった。
「テレクラ」なんてものは論外としても、メールで女を口説ける時代にはなった。
それでも編集長は言うんだろうな。
「とにかく会いに行け、メールですまそうとするな」
はい!
これからも神戸の街を歩き回り、とにかく会いに行きます。
2017年08月22日
伊佐山紫文34
『三文オペラ』ブレヒト作 谷川道子訳 光文社古典新訳文庫
先日亡くなった作詞家の山川啓介先生は、実はご自身でも脚本を書き、ミュージカルを作っておられた。
それで、とあるシンポジウムで音楽劇の名作の条件を挙げられた。
「一つの作品の中に一曲でも良い、名曲が生まれれば、それは名作です」
私はその時、まだ作詞を始めてはおらず、脚本を作る劇作家という立場でパネリストになっていたので、ちょっとカチンと来、それでもその場は憚れ、打ち上げの席で反論した。
やはり、芝居はストーリーだと思います、と。
すると先生は「『キャッツ』ってどんな話だった?」と聞いてこられた。
参った、と思った。
あんなよく分からん話でも「メモリー」一曲で名作になるのがこの世界なのだ。
まさに舞台には魔物が潜んでいる。
で『三文オペラ』である。
一時の日本の左翼演劇界はブレヒトで回っていた時期があって、猫も杓子もブレヒトで、そうでなければ反ブレヒト、異化だかタコだか、教育劇か今日行く劇か、それはそれはウザイものだった(らしい)。
ブレヒトのそもそもの経歴が極めてうさんくさい。
ナチスを逃れてアメリカ亡命まではまあ分かるとして、落ち着く先が東ドイツで、これから年譜で辿るだけでも東ドイツの「芸術アカデミー会員」になり「東西ベルリンのペンクラブの会長」に選ばれ、あげくは「スターリン国際平和賞」まで「受賞」するなんて、どれほどうさんくさい存在なんだよ。
でもこれが日本の左翼にはたまらない輝かしさで、うちの父親は我が神、吾が仏とばかりにあがめ奉っていた。
で、今、新訳で読み返してみると、ハッキリ言ってつまらない。
それでも名作なのは、本書でのタイトル「ドスのメッキーズ殺しのバラード(モリタート)」一曲があるからだろう。
英名は「マック・ザ・ナイフ」、ジャズのスタンダードナンバーにもなった、クルト・ヴァイルの傑作である。
実家にも若いクレンペラー指揮の組曲盤『三文オペラ』があったような気がする。
往年の大指揮者の悠揚たる響きとは違う、もっとセカセカした、退廃音楽を地でいくような演奏だったような。
なんでこれを今読み返したのかと言えば、先日、若い人たちと演出上のことでナイフ使いのことが話題になり「メッキー・メッサーのモリタート」の話をすると、全く知らない、聴いたこともない、と。
私も『三文オペラ』の内容は忘れていたので、どういう話だったのか、読み返したってこと。
まあ、時間の無駄とまでは言わないけれど……
こんなやっつけ仕事が世界的大ヒットになってしまうんだから、まさに舞台には魔物が潜んでいます。
どんな魔物か知らないが、あやかりたいものです。
先日亡くなった作詞家の山川啓介先生は、実はご自身でも脚本を書き、ミュージカルを作っておられた。
それで、とあるシンポジウムで音楽劇の名作の条件を挙げられた。
「一つの作品の中に一曲でも良い、名曲が生まれれば、それは名作です」
私はその時、まだ作詞を始めてはおらず、脚本を作る劇作家という立場でパネリストになっていたので、ちょっとカチンと来、それでもその場は憚れ、打ち上げの席で反論した。
やはり、芝居はストーリーだと思います、と。
すると先生は「『キャッツ』ってどんな話だった?」と聞いてこられた。
参った、と思った。
あんなよく分からん話でも「メモリー」一曲で名作になるのがこの世界なのだ。
まさに舞台には魔物が潜んでいる。
で『三文オペラ』である。
一時の日本の左翼演劇界はブレヒトで回っていた時期があって、猫も杓子もブレヒトで、そうでなければ反ブレヒト、異化だかタコだか、教育劇か今日行く劇か、それはそれはウザイものだった(らしい)。
ブレヒトのそもそもの経歴が極めてうさんくさい。
ナチスを逃れてアメリカ亡命まではまあ分かるとして、落ち着く先が東ドイツで、これから年譜で辿るだけでも東ドイツの「芸術アカデミー会員」になり「東西ベルリンのペンクラブの会長」に選ばれ、あげくは「スターリン国際平和賞」まで「受賞」するなんて、どれほどうさんくさい存在なんだよ。
でもこれが日本の左翼にはたまらない輝かしさで、うちの父親は我が神、吾が仏とばかりにあがめ奉っていた。
で、今、新訳で読み返してみると、ハッキリ言ってつまらない。
それでも名作なのは、本書でのタイトル「ドスのメッキーズ殺しのバラード(モリタート)」一曲があるからだろう。
英名は「マック・ザ・ナイフ」、ジャズのスタンダードナンバーにもなった、クルト・ヴァイルの傑作である。
実家にも若いクレンペラー指揮の組曲盤『三文オペラ』があったような気がする。
往年の大指揮者の悠揚たる響きとは違う、もっとセカセカした、退廃音楽を地でいくような演奏だったような。
なんでこれを今読み返したのかと言えば、先日、若い人たちと演出上のことでナイフ使いのことが話題になり「メッキー・メッサーのモリタート」の話をすると、全く知らない、聴いたこともない、と。
私も『三文オペラ』の内容は忘れていたので、どういう話だったのか、読み返したってこと。
まあ、時間の無駄とまでは言わないけれど……
こんなやっつけ仕事が世界的大ヒットになってしまうんだから、まさに舞台には魔物が潜んでいます。
どんな魔物か知らないが、あやかりたいものです。
2017年08月22日
伊佐山紫文33
三島由紀夫が自決したとき、コメントを求められた評論家の磯田光一が、今後一年間は一切三島について発言しない、と言い、実際、その通り沈黙を守ったのを知って、若い私は痺れるほど感動した。
物書きとはこうでなくてはならない、と。
人の不幸でさえ、と言うより、むしろ人の不幸をエサにしているようなマスコミとは距離を置くべきだ、と。
事態が沈静化した後に、じっくりと自分の考えを発表すれば良い、と。
で、同じことをやってしまった。
今でも悔やまれるが、古い友人に誘われてビートたけしを批判する本を共著で書いた。
共著と言っても、私以外はみんなシロウトの、まあ、下らない本である。
読むにも値しない、出す意味も無い、三流雑誌の記事以下の駄本である。
ところがこれを、当のビートたけしがテレビで褒めた。
私の担当した個所を絶賛した、らしい。
私はその番組を見ていないからなんとも言えないが、とにかくそれで火がついて、本は売れに売れた。
本題はここからである。
本が出た数週間後、ビートたけしが例の事故を起こし、意識不明の重体となる。
私のところには、コメントを求めるマスコミが文字通り殺到した。
なにしろ例の本の、私の担当した文章のタイトルが、
「たけしを成仏さすために」
しかも、まだ事故の前、調子に乗って受けた週刊誌のインタビューで「もう死んでますよ」などとコメントしていたものだから、それこそ予言者扱いされて、ひっきりなしに電話がかかってくる。
今なら考えられないことだが、出版社は平気で連絡先を教える。
と言うより、マスコミ連絡帳、みたいな本はもとより、『朝日年鑑』の別冊にまで、私の連絡先は載っていた。
そういうのに載せれば仕事が来ると思っていたし。
で、ここからが愚かなところ。
磯田光一大先生の真似をしてしまった。
人の不幸で商売はしません、と、コメントを一切断った。
ビートたけしが死んで一年経った頃、また何か書けば良いと思っていた。
ところがたけしは復活したし、私は気難しい物書きという評価が定着して誰も仕事を持ってこなくなった。
私は磯田大先生とは違う、ということに初めて気がついた。
思えば私のようなチンピラにとって、たけしの事故は大きなチャンスだったのだ。
人の不幸だろうがなんだろうが、すべてをチャンスと捉え、食いつくべきだったのだ。
実際、たけしは甦ってきたのだから、どれだけ私がひどいことを言っていようが、後になって笑い話にしてくれただろう、と思う。
チンピラがのし上がるには手段を選んではいられない。
お互い様なんだから、と。
あ~あ、何という失敗。
若さってやつは。
物書きとはこうでなくてはならない、と。
人の不幸でさえ、と言うより、むしろ人の不幸をエサにしているようなマスコミとは距離を置くべきだ、と。
事態が沈静化した後に、じっくりと自分の考えを発表すれば良い、と。
で、同じことをやってしまった。
今でも悔やまれるが、古い友人に誘われてビートたけしを批判する本を共著で書いた。
共著と言っても、私以外はみんなシロウトの、まあ、下らない本である。
読むにも値しない、出す意味も無い、三流雑誌の記事以下の駄本である。
ところがこれを、当のビートたけしがテレビで褒めた。
私の担当した個所を絶賛した、らしい。
私はその番組を見ていないからなんとも言えないが、とにかくそれで火がついて、本は売れに売れた。
本題はここからである。
本が出た数週間後、ビートたけしが例の事故を起こし、意識不明の重体となる。
私のところには、コメントを求めるマスコミが文字通り殺到した。
なにしろ例の本の、私の担当した文章のタイトルが、
「たけしを成仏さすために」
しかも、まだ事故の前、調子に乗って受けた週刊誌のインタビューで「もう死んでますよ」などとコメントしていたものだから、それこそ予言者扱いされて、ひっきりなしに電話がかかってくる。
今なら考えられないことだが、出版社は平気で連絡先を教える。
と言うより、マスコミ連絡帳、みたいな本はもとより、『朝日年鑑』の別冊にまで、私の連絡先は載っていた。
そういうのに載せれば仕事が来ると思っていたし。
で、ここからが愚かなところ。
磯田光一大先生の真似をしてしまった。
人の不幸で商売はしません、と、コメントを一切断った。
ビートたけしが死んで一年経った頃、また何か書けば良いと思っていた。
ところがたけしは復活したし、私は気難しい物書きという評価が定着して誰も仕事を持ってこなくなった。
私は磯田大先生とは違う、ということに初めて気がついた。
思えば私のようなチンピラにとって、たけしの事故は大きなチャンスだったのだ。
人の不幸だろうがなんだろうが、すべてをチャンスと捉え、食いつくべきだったのだ。
実際、たけしは甦ってきたのだから、どれだけ私がひどいことを言っていようが、後になって笑い話にしてくれただろう、と思う。
チンピラがのし上がるには手段を選んではいられない。
お互い様なんだから、と。
あ~あ、何という失敗。
若さってやつは。
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
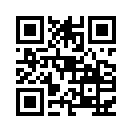
アクセスカウンタ
読者登録
