2017年10月11日
10/21土曜ムラマツリサイタルホール新大阪

セブンイレブン、サークルKサンクスにて購入出来ます。
P337310を入力してください。
10/21土曜
ムラマツリサイタルホール新大阪にて。
15時開演(14時半開場)
クラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」
写真は、初めて出演される和楽器奏者の勝井粧子さん。
遊女役として、地唄を披露します。
どうそお楽しみに!
問い合わせは、夙川座0798558297
shukugawaza@gmail.com
2017年10月11日
伊佐山紫文87
妻がカズオ・イシグロの『わたしを離さないで』を読み終え、
「こんなものなん?」
まあ、順当な感想だと思う。
とにかく、文学文学してないんだよな、カズオ・イシグロの作品は。
それがこの人の魅力なんだし。
そもそもこの人の文学の魅力の9割は繊細な英文にあるから、それは翻訳では伝わらない。
翻訳を一読しても、なんとなく、スラスラ読める、軽い感じの物語にしか感じられない。
物語だけを取り出して比較すれば、日本の少女漫画にはもっと深く深刻なものがゴロゴロある。
萩尾望都とか、竹宮恵子とか。
そういうのと比べると、カズオ・イシグロの文学は、物語として、どうしようもなく軽い。
ナレーションで読者を騙すテクニックも、分かってしまえばそれまでだし。
なのに、なんでノーベル賞かと言えば、これは私の個人的な妄想でしかないが、村上春樹受賞の芽を完全に潰したのだと思う。
ノーベル賞の選考委員にとって、村上春樹はやっかいな存在だった、と思う。
政治的な発言を滅多にしないし、これだけでも左派的な色彩の強い文学賞選考基準からは大きく離れる。
しかも、それじゃあ、と政治的発言をしてみれば、反イスラエル。
講談社が甘かったのだと思うが、これで絶対に受賞はなくなった。
それでも無知なブックメーカーは受賞を予想してくる。
仕方ない、と似たような作風のカズオ・イシグロを受賞させる。
日系だし、これでしばらくは日本人作家の受賞はなくなる。
当然、村上春樹の受賞の芽は完全に消える。
最近のは読んでいないが、村上春樹の初期の短編には佳作が多かった。
日本文学にはない、むしろアメリカ文学の、レイモンド・チャンドラーにつながるような、狭い生活世界のリアリズムと、精神分析をベースにした乾いたペーソス。
かと思えば『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のような重厚なものも書く。
ノーベル賞がなんぼのモノかは知らないが、まあ、取ってもいいんじゃないか。
なにしろ過去にはイギリスのチャーチルなんかも受賞しているんだし。
去年はボブ・ディランだし。
選考基準なんかワケがわからんとしか言いようがない。
もちろん、それは芸術に対して賞を与えて評価しようという、その姿勢そのものの傲慢さから来るものだろうから、仕方ないと言えば仕方ない。
私としては、今回のカズオ・イシグロ受賞が、この人や村上春樹の文学に通底すると思われるヨーゼフ・ロートの再評価につながれば良いなとは思う。
『聖なる酔っ払いの伝説』のような、軽妙な驚きに満ちた、そして暖かい世界。
重くて暗いのだけが文学じゃないし。
「こんなものなん?」
まあ、順当な感想だと思う。
とにかく、文学文学してないんだよな、カズオ・イシグロの作品は。
それがこの人の魅力なんだし。
そもそもこの人の文学の魅力の9割は繊細な英文にあるから、それは翻訳では伝わらない。
翻訳を一読しても、なんとなく、スラスラ読める、軽い感じの物語にしか感じられない。
物語だけを取り出して比較すれば、日本の少女漫画にはもっと深く深刻なものがゴロゴロある。
萩尾望都とか、竹宮恵子とか。
そういうのと比べると、カズオ・イシグロの文学は、物語として、どうしようもなく軽い。
ナレーションで読者を騙すテクニックも、分かってしまえばそれまでだし。
なのに、なんでノーベル賞かと言えば、これは私の個人的な妄想でしかないが、村上春樹受賞の芽を完全に潰したのだと思う。
ノーベル賞の選考委員にとって、村上春樹はやっかいな存在だった、と思う。
政治的な発言を滅多にしないし、これだけでも左派的な色彩の強い文学賞選考基準からは大きく離れる。
しかも、それじゃあ、と政治的発言をしてみれば、反イスラエル。
講談社が甘かったのだと思うが、これで絶対に受賞はなくなった。
それでも無知なブックメーカーは受賞を予想してくる。
仕方ない、と似たような作風のカズオ・イシグロを受賞させる。
日系だし、これでしばらくは日本人作家の受賞はなくなる。
当然、村上春樹の受賞の芽は完全に消える。
最近のは読んでいないが、村上春樹の初期の短編には佳作が多かった。
日本文学にはない、むしろアメリカ文学の、レイモンド・チャンドラーにつながるような、狭い生活世界のリアリズムと、精神分析をベースにした乾いたペーソス。
かと思えば『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のような重厚なものも書く。
ノーベル賞がなんぼのモノかは知らないが、まあ、取ってもいいんじゃないか。
なにしろ過去にはイギリスのチャーチルなんかも受賞しているんだし。
去年はボブ・ディランだし。
選考基準なんかワケがわからんとしか言いようがない。
もちろん、それは芸術に対して賞を与えて評価しようという、その姿勢そのものの傲慢さから来るものだろうから、仕方ないと言えば仕方ない。
私としては、今回のカズオ・イシグロ受賞が、この人や村上春樹の文学に通底すると思われるヨーゼフ・ロートの再評価につながれば良いなとは思う。
『聖なる酔っ払いの伝説』のような、軽妙な驚きに満ちた、そして暖かい世界。
重くて暗いのだけが文学じゃないし。
2017年10月10日
伊佐山紫文86
ニューヨークの中古ピアノ店に初老の男が入ってくる。
黙ってピアノの前に座る。
なにげに弾く。
!!!!!
壁が波打ち、店の空気が裏返る。
モーツァルトのピアノソナタ。
下町のピアノ店が一気にウィーンの宮廷になる。
「ママ! あのピアノ欲しい!」
そこにいた子供まで音に飲まれる。
店員が男にそっと聞く。
「もしかして、アナタは……」
「うん。ホロヴィッツだよ」
この逸話が本当かどうかはどうでもいい。
先日、ホロヴィッツのモーツァルトCDをかけた途端、息子が口でトレースし始めた。
けっこう正確に主旋律を口でなぞり、再現部では自分で別の声部を作り、合わせて歌っている。
初めて聞いたはずなのに、なんで?
巨匠のCDをかけていると、こんなことが結構ある。
本当の名演は子供の心も掴むものなんだと思いつつ、公演への未就学児の入場をどうするかは、主催として悩ましいところである。
私自身、子供を持つまでは、未就学児の入場など絶対に許してはならないと思っていた。
そもそもが親のエゴだし。
自分が聴きたいだけでしょ。
みたいな。
けれど、子供を持ち、自分で、自分の作品を上演するようになって、考え方はまた変わって来た。
預ける場所もないし、仕方がないんだよ。
毎回、騒ぐなよ、声を上げるなよ、と祈るような気持ちでいる。
先日も、10月公演のチラシを見た息子が言うには、
「コイノナザンに僕を連れて行こうとしてるんだろ」
コイノナザン?
いったいそりゃ何だ?
ああ、「恋の名残」か。
そりゃ読めんわな。
「もちろん連れて行くよ」
「嫌だ」
年頃なのか、「恋」だの「愛」だのを極端に嫌がる。
「とにかく行くの」
「なんで?」
「理由はない。お父さんの作品を観とけ」
「え~」
ホロヴィッツほどの名演になるとは思えないが、お前が思わず口ずさむような作品を作りたいとは思っているんだよ。
黙ってピアノの前に座る。
なにげに弾く。
!!!!!
壁が波打ち、店の空気が裏返る。
モーツァルトのピアノソナタ。
下町のピアノ店が一気にウィーンの宮廷になる。
「ママ! あのピアノ欲しい!」
そこにいた子供まで音に飲まれる。
店員が男にそっと聞く。
「もしかして、アナタは……」
「うん。ホロヴィッツだよ」
この逸話が本当かどうかはどうでもいい。
先日、ホロヴィッツのモーツァルトCDをかけた途端、息子が口でトレースし始めた。
けっこう正確に主旋律を口でなぞり、再現部では自分で別の声部を作り、合わせて歌っている。
初めて聞いたはずなのに、なんで?
巨匠のCDをかけていると、こんなことが結構ある。
本当の名演は子供の心も掴むものなんだと思いつつ、公演への未就学児の入場をどうするかは、主催として悩ましいところである。
私自身、子供を持つまでは、未就学児の入場など絶対に許してはならないと思っていた。
そもそもが親のエゴだし。
自分が聴きたいだけでしょ。
みたいな。
けれど、子供を持ち、自分で、自分の作品を上演するようになって、考え方はまた変わって来た。
預ける場所もないし、仕方がないんだよ。
毎回、騒ぐなよ、声を上げるなよ、と祈るような気持ちでいる。
先日も、10月公演のチラシを見た息子が言うには、
「コイノナザンに僕を連れて行こうとしてるんだろ」
コイノナザン?
いったいそりゃ何だ?
ああ、「恋の名残」か。
そりゃ読めんわな。
「もちろん連れて行くよ」
「嫌だ」
年頃なのか、「恋」だの「愛」だのを極端に嫌がる。
「とにかく行くの」
「なんで?」
「理由はない。お父さんの作品を観とけ」
「え~」
ホロヴィッツほどの名演になるとは思えないが、お前が思わず口ずさむような作品を作りたいとは思っているんだよ。
2017年10月09日
伊佐山紫文85
学生時代、ほとんど毎日、私の下宿に通ってきていた友人がいて、そいつがあるとき、
「クラスの連中が、よくあんな、イサヤマみたいな恐ろしい男と付き合っていられるな、なんて言うんだよ。どこが恐ろしいんだ、付き合ってみれば、あれほど面白い男もいないよ、って言ったんだけどな」
まあ、その後の人生を考えると、どちらの言い分もよく分かる。
とにかく、普通の男たちにとって、私はそこにいるだけで恐ろしいらしい。
発言がとか、そういうもんじゃなく、存在自体が恐ろしい、らしい。
こういう不気味な雰囲気は、ある種の才能であって、中学の時の演劇では絶大な効果を発揮した。
文化祭の演し物で、わらしべ長者がだんだんと貧乏になっていくというバカバカしい芝居、貧乏自慢でほのぼのと終わるはずだった。
ところが、そのラストシーン、長者から全てを奪う私の演技に会場は凍り付いた。
セリフの無い無言の自然体の演技だったのだが、会場が恐怖に凍り付いたのが舞台の上からも分かった。
とにかく、私の登場自体が恐ろしかったのだ。
あまりに恐ろしくて長者の台詞が出てこなくなり、終われない。
どうやって芝居を終わらせたのか記憶にないが、後で、
「怖かった」
「恐ろしかった」
「出るべきじゃなかった」
と言われまくったのは憶えている。
それも、そう言ってくれるのは女子ばかりで、男子は何も言ってこない。
そう言えばラストでのクスクス笑いも、すべて女子のものだった。
実は男子こそが怖がっていたのだろうとは、当時の私にも分かった。
とにかく、存在自体が恐ろしいのだ。
今ならその理由もよく分かる。
良い意味でも悪い意味でも、私は常人ではないのだ。
そのことに気づいたのがつい最近、我が子の異常さを探る中で、というのが悲しいが、これもまた現実として受け入れるしかない。
そもそも高校時代、ルービックキューブの6面を自力で完成できたというのがオカシイ。
ルービック6面完成だけでも常人からみれば悪魔的な所行だということに、最近になって気づいたというのも、これもオカシイ。
学力とはほとんど関係のない、IQとも違う、特殊な頭の回転の速さ。
ルービックキューブの6面をそろえるような、実生活では全く役に立たない、むしろ邪魔になる、無駄な頭の回転の速さ。
息子の異常さを探る中で、この世というのは、そういう回転の速い脳を持った男(まれに女)が一定の数、生じてくる仕組みになっているらしいということが分かった。
で、その才能を、社会が生かすか殺すか。
組織的に生かそうという試みも英語圏では始まっているが、効果を上げているかどうかはまだ分かっていない。
日本では、もちろん、手も触れられていない。
ただ、少年院の子らのIQが一般の子らよりも高いことが分かってきて、一部の研究者が2E(ツーイー)とかWE(ダブルイー)とか言い出してはいる。
もしかしたら将来、今でいう「発達障害」などと同じように、社会の関心が向くこともあるのかも知れない。
もちろん、ものすごく遠い将来の話である。
息子の異常さに気付いて日本の児童心理の研究者とメールのやりとりをしていて、この人たちはアメリカの教育制度には強烈な関心があっても、日本の現実の子供には全く興味がないということが分かったから。
しばらくは、そういう子らは怖れられ、むしろ当人の社会的不適応とされて、ドロップアウトしていくしかないのだろう。
そういうことが50過ぎて分かってきたというのも悲しいが、まあ、仕方ない。
反面、こういう男は、男には怖れられるが、むしろ女性には面白がられる傾向にあるらしく、それなりに楽しい前半生ではありましたわ。
人生百年時代、後半生もそれなりに楽しくやっていくつもりなので、どうそ夜露死苦。
「クラスの連中が、よくあんな、イサヤマみたいな恐ろしい男と付き合っていられるな、なんて言うんだよ。どこが恐ろしいんだ、付き合ってみれば、あれほど面白い男もいないよ、って言ったんだけどな」
まあ、その後の人生を考えると、どちらの言い分もよく分かる。
とにかく、普通の男たちにとって、私はそこにいるだけで恐ろしいらしい。
発言がとか、そういうもんじゃなく、存在自体が恐ろしい、らしい。
こういう不気味な雰囲気は、ある種の才能であって、中学の時の演劇では絶大な効果を発揮した。
文化祭の演し物で、わらしべ長者がだんだんと貧乏になっていくというバカバカしい芝居、貧乏自慢でほのぼのと終わるはずだった。
ところが、そのラストシーン、長者から全てを奪う私の演技に会場は凍り付いた。
セリフの無い無言の自然体の演技だったのだが、会場が恐怖に凍り付いたのが舞台の上からも分かった。
とにかく、私の登場自体が恐ろしかったのだ。
あまりに恐ろしくて長者の台詞が出てこなくなり、終われない。
どうやって芝居を終わらせたのか記憶にないが、後で、
「怖かった」
「恐ろしかった」
「出るべきじゃなかった」
と言われまくったのは憶えている。
それも、そう言ってくれるのは女子ばかりで、男子は何も言ってこない。
そう言えばラストでのクスクス笑いも、すべて女子のものだった。
実は男子こそが怖がっていたのだろうとは、当時の私にも分かった。
とにかく、存在自体が恐ろしいのだ。
今ならその理由もよく分かる。
良い意味でも悪い意味でも、私は常人ではないのだ。
そのことに気づいたのがつい最近、我が子の異常さを探る中で、というのが悲しいが、これもまた現実として受け入れるしかない。
そもそも高校時代、ルービックキューブの6面を自力で完成できたというのがオカシイ。
ルービック6面完成だけでも常人からみれば悪魔的な所行だということに、最近になって気づいたというのも、これもオカシイ。
学力とはほとんど関係のない、IQとも違う、特殊な頭の回転の速さ。
ルービックキューブの6面をそろえるような、実生活では全く役に立たない、むしろ邪魔になる、無駄な頭の回転の速さ。
息子の異常さを探る中で、この世というのは、そういう回転の速い脳を持った男(まれに女)が一定の数、生じてくる仕組みになっているらしいということが分かった。
で、その才能を、社会が生かすか殺すか。
組織的に生かそうという試みも英語圏では始まっているが、効果を上げているかどうかはまだ分かっていない。
日本では、もちろん、手も触れられていない。
ただ、少年院の子らのIQが一般の子らよりも高いことが分かってきて、一部の研究者が2E(ツーイー)とかWE(ダブルイー)とか言い出してはいる。
もしかしたら将来、今でいう「発達障害」などと同じように、社会の関心が向くこともあるのかも知れない。
もちろん、ものすごく遠い将来の話である。
息子の異常さに気付いて日本の児童心理の研究者とメールのやりとりをしていて、この人たちはアメリカの教育制度には強烈な関心があっても、日本の現実の子供には全く興味がないということが分かったから。
しばらくは、そういう子らは怖れられ、むしろ当人の社会的不適応とされて、ドロップアウトしていくしかないのだろう。
そういうことが50過ぎて分かってきたというのも悲しいが、まあ、仕方ない。
反面、こういう男は、男には怖れられるが、むしろ女性には面白がられる傾向にあるらしく、それなりに楽しい前半生ではありましたわ。
人生百年時代、後半生もそれなりに楽しくやっていくつもりなので、どうそ夜露死苦。
2017年10月08日
ムラマツリサイタルホール新大阪にて。
クラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」
出演者は、お初…森井美貴、徳兵衛…谷浩一郎、お鈴…陰山裕美子、九平次…砂田麗央、稗田阿礼…浅川文恵、お粧…勝井粧子、ピアニスト…白藤望
ぴあ(セブンイレブン、サークルKサンクスにて購入) コード…337310
お問い合わせは夙川座0798558297
shukugawaza@gmail.com
入場料は、御一人様5500円(前売り5000円)
座友会メンバー4500円

出演者は、お初…森井美貴、徳兵衛…谷浩一郎、お鈴…陰山裕美子、九平次…砂田麗央、稗田阿礼…浅川文恵、お粧…勝井粧子、ピアニスト…白藤望
ぴあ(セブンイレブン、サークルKサンクスにて購入) コード…337310
お問い合わせは夙川座0798558297
shukugawaza@gmail.com
入場料は、御一人様5500円(前売り5000円)
座友会メンバー4500円

2017年10月08日
ムラマツリサイタルホール新大阪にて。
クラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」
出演者は、お初…森井美貴、徳兵衛…谷浩一郎、お鈴…陰山裕美子、九平次…砂田麗央、稗田阿礼…浅川文恵、お粧…勝井粧子、ピアニスト…白藤望
ぴあ(セブンイレブン、サークルKサンクスにて購入) コード…337310
お問い合わせは夙川座0798558297
shukugawaza@gmail.com
入場料は、御一人様5500円(前売り5000円)
座友会メンバー4500円
出演者は、お初…森井美貴、徳兵衛…谷浩一郎、お鈴…陰山裕美子、九平次…砂田麗央、稗田阿礼…浅川文恵、お粧…勝井粧子、ピアニスト…白藤望
ぴあ(セブンイレブン、サークルKサンクスにて購入) コード…337310
お問い合わせは夙川座0798558297
shukugawaza@gmail.com
入場料は、御一人様5500円(前売り5000円)
座友会メンバー4500円
2017年10月08日
ムラマツリサイタルホール新大阪にて。
クラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」
出演者は、お初…森井美貴、徳兵衛…谷浩一郎、お鈴…陰山裕美子、九平次…砂田麗央、稗田阿礼…浅川文恵、お粧…勝井粧子、ピアニスト…白藤望
ぴあ(セブンイレブン、サークルKサンクスにて購入) コード…337310
お問い合わせは夙川座0798558297
shukugawaza@gmail.com
入場料は、御一人様5500円(前売り5000円)
座友会メンバー4500円
出演者は、お初…森井美貴、徳兵衛…谷浩一郎、お鈴…陰山裕美子、九平次…砂田麗央、稗田阿礼…浅川文恵、お粧…勝井粧子、ピアニスト…白藤望
ぴあ(セブンイレブン、サークルKサンクスにて購入) コード…337310
お問い合わせは夙川座0798558297
shukugawaza@gmail.com
入場料は、御一人様5500円(前売り5000円)
座友会メンバー4500円
2017年10月08日
伊佐山紫文84
四畳半と言えば、学生時代、最初に住んだのは松山市鉄砲町の四畳半の下宿だった。
台所・トイレ共有、風呂なし。
家賃は月に7000円。
入学時としては一般的な下宿だったが、私が在学していた4年間で急速にワンルームマンションというのが普及して、あっと言う間に時代遅れになった。
入っている下宿人の質も急激に変わった。
はじめは学生ばかりだったのに、妙な流れ者が1人入り2人入り、卒業する頃には学生は少数派になってしまった。
流れ者の一人に自称「革命児」と言うのがいて、これがもう、とてつもなく変なヤツだった。
隣の三畳間の戸の名札に「革命児」と掲げてある。
「革命」と言うからには左翼に違いない、だったらどんな左翼だ、と一緒に酒を飲んでみた。
ところが、こいつがもう、底抜けのバカで、バカさ加減が知識のなさから来るものなら救いようもあるが、そうじゃなく、何か認識の根本がずれている。
どうやって革命を起こすのか、そのやり方がそもそもオカシイ、いや愚かしい。
まず歌手になるのだと。
それでファンを煽って「革命だ~!」。
ハァ?
で、どうやって歌手になるのか。
今は歌も歌えないし、こうやって流れ者としてさすらっているが、自分は神に選ばれた人間だから、必ず世に出て革命を起こす、と。
そう言って、左腕の細長い傷を見せるのだった。
冬の八甲田山に友人と登って遭難したときのものだ、と。
眠らないように自らナイフで切った、その時の傷だ、と。
「友達と賭をしたんだよ。どっちが神に選ばれた人間かって。それで、俺は生き残った。俺が神に選ばれたんだよ」
「友達は?」
「死んだよ」
本当か嘘かもわからない。
数日後、戸に張り紙がして「旅に出る。探さないでくれ」。
すぐに帰って来たから、聞けば、横浜の実家に帰省していただけ。
ところがこんなイカレポンチにも彼女が出来る。
泊まっていく。
その時の声が薄い壁を通して聞こえて来る。
で、ある夜、一晩中その声がして、革命児は姿を消し、彼女が三畳間の住人になった。
下宿のオバサンによれば、革命児は再び放浪の旅に出て、彼女は二人の想い出の部屋であいつの帰ってくるのをずっと待つのだという。
なんともはや。
その後、三畳間の彼女は、一月もせずに出て行った。
もしかしたら革命児が迎えに来たのかも知れないし、前みたいに実家に帰っていただけかも知れない。
とにかく興味もなかったから誰にも何も聞かなかった。
それより、入れ替わりに、ものすごい美人が入って、ゾクゾクした。
狭い廊下ですれ違うときなど、危うく死にそうになった。
美人は、夜の仕事に出て行く時の着替え場所にしているみたいだった。
おそらく昼間は普通に仕事をしていて、夕方、下宿に置いてある服に着替え、夜の街に消えて行く。
何度か口もきいて、店も教えてくれたのだけれど、行く金などなかった。
その頃、大家のオバサンは、とある新興宗教にはまってしまっていて、その関係で、色んな人を入れだしたのではないかと思う。
二階だった私の部屋の真下には、痩せて顔色が異様に真っ白な、明らかなシャブ中まで入った。
夜中に廊下を歩く様はまさに幽霊で、ジロリと睨まれると震え上がった。
こいつが真夜中、意味不明なことを叫んで向かいの下宿の学生とケンカを始めたり、美人は店に来てくれと色っぽい目つきで誘うし、大学も四年生になると、とても勉学の環境じゃなくなっていた。
気がつけば住人に学生はほとんど残っていなかった。
もはや限界と、大学院入学が決まった春にワンルームマンションに引っ越した。
何年か前に前を通ったら、駐車場になっていた。

台所・トイレ共有、風呂なし。
家賃は月に7000円。
入学時としては一般的な下宿だったが、私が在学していた4年間で急速にワンルームマンションというのが普及して、あっと言う間に時代遅れになった。
入っている下宿人の質も急激に変わった。
はじめは学生ばかりだったのに、妙な流れ者が1人入り2人入り、卒業する頃には学生は少数派になってしまった。
流れ者の一人に自称「革命児」と言うのがいて、これがもう、とてつもなく変なヤツだった。
隣の三畳間の戸の名札に「革命児」と掲げてある。
「革命」と言うからには左翼に違いない、だったらどんな左翼だ、と一緒に酒を飲んでみた。
ところが、こいつがもう、底抜けのバカで、バカさ加減が知識のなさから来るものなら救いようもあるが、そうじゃなく、何か認識の根本がずれている。
どうやって革命を起こすのか、そのやり方がそもそもオカシイ、いや愚かしい。
まず歌手になるのだと。
それでファンを煽って「革命だ~!」。
ハァ?
で、どうやって歌手になるのか。
今は歌も歌えないし、こうやって流れ者としてさすらっているが、自分は神に選ばれた人間だから、必ず世に出て革命を起こす、と。
そう言って、左腕の細長い傷を見せるのだった。
冬の八甲田山に友人と登って遭難したときのものだ、と。
眠らないように自らナイフで切った、その時の傷だ、と。
「友達と賭をしたんだよ。どっちが神に選ばれた人間かって。それで、俺は生き残った。俺が神に選ばれたんだよ」
「友達は?」
「死んだよ」
本当か嘘かもわからない。
数日後、戸に張り紙がして「旅に出る。探さないでくれ」。
すぐに帰って来たから、聞けば、横浜の実家に帰省していただけ。
ところがこんなイカレポンチにも彼女が出来る。
泊まっていく。
その時の声が薄い壁を通して聞こえて来る。
で、ある夜、一晩中その声がして、革命児は姿を消し、彼女が三畳間の住人になった。
下宿のオバサンによれば、革命児は再び放浪の旅に出て、彼女は二人の想い出の部屋であいつの帰ってくるのをずっと待つのだという。
なんともはや。
その後、三畳間の彼女は、一月もせずに出て行った。
もしかしたら革命児が迎えに来たのかも知れないし、前みたいに実家に帰っていただけかも知れない。
とにかく興味もなかったから誰にも何も聞かなかった。
それより、入れ替わりに、ものすごい美人が入って、ゾクゾクした。
狭い廊下ですれ違うときなど、危うく死にそうになった。
美人は、夜の仕事に出て行く時の着替え場所にしているみたいだった。
おそらく昼間は普通に仕事をしていて、夕方、下宿に置いてある服に着替え、夜の街に消えて行く。
何度か口もきいて、店も教えてくれたのだけれど、行く金などなかった。
その頃、大家のオバサンは、とある新興宗教にはまってしまっていて、その関係で、色んな人を入れだしたのではないかと思う。
二階だった私の部屋の真下には、痩せて顔色が異様に真っ白な、明らかなシャブ中まで入った。
夜中に廊下を歩く様はまさに幽霊で、ジロリと睨まれると震え上がった。
こいつが真夜中、意味不明なことを叫んで向かいの下宿の学生とケンカを始めたり、美人は店に来てくれと色っぽい目つきで誘うし、大学も四年生になると、とても勉学の環境じゃなくなっていた。
気がつけば住人に学生はほとんど残っていなかった。
もはや限界と、大学院入学が決まった春にワンルームマンションに引っ越した。
何年か前に前を通ったら、駐車場になっていた。

2017年10月07日
伊佐山紫文83
息子がインターネット中毒そのものなので、熱を出したのを理由に数日禁じてみた。
「ヒマ、ヒマ、ヒマ」
そこらの本もマンガも全部読んで飽きたと言うから、ブックオフに行って『ドラえもん』総集編を手当たり次第に買ってきた。
1冊108円を7冊。
その中に『藤子・F・不二雄の怖い話』と言うのが混じっていて、その中の一話を読んだだけで、
「こんな怖い本、買ってくるな!」
見れば、第一話は、なんと「ノスタル爺」。
『異色短編集』に入っており、私の忘れられぬ「トラウマンガ」の一つである。
横井さんや小野田さんら残留日本兵の存在を背景に、残された妻、崩壊する家、消えて行く集落を描き、強烈な印象を残す。
藤子・F・不二雄の大傑作である。
これがまた、『異色短編集』では「土蔵の爺さま」だった呼称が、ここでは「気ぶりの爺さま」と雑誌掲載時のままに戻され、これもまた強烈である。
そうか、こんな難しい話で怖くなるほど、ちゃんと読めるようになってきたってことか。
小学校4年と言えば、私が松本零士の『男おいどん』に出会った年である。
忘れもしない、小4のいつだったかは忘れたが、中津の父の友人の家に泊まりに行き、そこで『男おいどん』の載った『少年マガジン』を読んだ。
正確には、『男おいどん』が講談社出版文化賞を受賞して、その記念で書かれた外伝「おいどんの地球」を読んだのだった。
人類が汚染された地球を離れるなか、ひとり四畳半に取り残される主人公。
そのペーソスに幼い心は震えた。
以後、私は、高校に入るまで『少年マガジン』を買い続けた。
『男おいどん』の最終回の記憶も鮮明である。
『少年マガジン』の発売日、日田の中央通りの果物屋の息子で、松本零士ファンの同士が息を切らしてウチに駆け込んできた。
手には『少年マガジン』最新号。
「大変バイ! 『男おいどん』が最終回バイ」
「スラゴツ(嘘言え)!」
「この表紙、サルマタはいちょらんし、ここ……」
様々な予兆を指摘する。
そして二人で読み、間違いなく最終回であることを確認した。
二人して泣いた。
夜も、布団に入ってから泣いた。
今思えば、まだ小学5年の夏である。
挫折しかない人生を生きる「おいどん」の、いったい何に反応していたのだろう。
それからしばらくして『月刊少年マガジン』が復刊されてこれも買うようになり、そこに小さな記事を見つけた。
松本零士が監督を務めるテレビアニメが制作される、と言うもので、私は心躍らせて放映の日を待ち続けた。
これが『宇宙戦艦ヤマト』、後に一大ブームを巻き起こすのだが、当時、観ていたのはクラスで私一人だった。
今観ても素晴らしい内容なのだが、視聴率が上がらず、商業的には失敗した。
再放送でブームに火がつき、誰も彼も最初の放送で観たと言い始めたのだが、嘘である。
皆、裏番組の『SFドラマ猿の軍団』を観ていたはず。
あなたたちが観ていたのは再放送です。
それにしても、そうか……息子も、もうそんな歳か。
色々選ばないといけないな。
確かに『怖い話』は怖すぎたわ。
画面からノスタル爺の「抱けえっ!! 抱けえっ!!」が聞こえてくるようだ。
「ヒマ、ヒマ、ヒマ」
そこらの本もマンガも全部読んで飽きたと言うから、ブックオフに行って『ドラえもん』総集編を手当たり次第に買ってきた。
1冊108円を7冊。
その中に『藤子・F・不二雄の怖い話』と言うのが混じっていて、その中の一話を読んだだけで、
「こんな怖い本、買ってくるな!」
見れば、第一話は、なんと「ノスタル爺」。
『異色短編集』に入っており、私の忘れられぬ「トラウマンガ」の一つである。
横井さんや小野田さんら残留日本兵の存在を背景に、残された妻、崩壊する家、消えて行く集落を描き、強烈な印象を残す。
藤子・F・不二雄の大傑作である。
これがまた、『異色短編集』では「土蔵の爺さま」だった呼称が、ここでは「気ぶりの爺さま」と雑誌掲載時のままに戻され、これもまた強烈である。
そうか、こんな難しい話で怖くなるほど、ちゃんと読めるようになってきたってことか。
小学校4年と言えば、私が松本零士の『男おいどん』に出会った年である。
忘れもしない、小4のいつだったかは忘れたが、中津の父の友人の家に泊まりに行き、そこで『男おいどん』の載った『少年マガジン』を読んだ。
正確には、『男おいどん』が講談社出版文化賞を受賞して、その記念で書かれた外伝「おいどんの地球」を読んだのだった。
人類が汚染された地球を離れるなか、ひとり四畳半に取り残される主人公。
そのペーソスに幼い心は震えた。
以後、私は、高校に入るまで『少年マガジン』を買い続けた。
『男おいどん』の最終回の記憶も鮮明である。
『少年マガジン』の発売日、日田の中央通りの果物屋の息子で、松本零士ファンの同士が息を切らしてウチに駆け込んできた。
手には『少年マガジン』最新号。
「大変バイ! 『男おいどん』が最終回バイ」
「スラゴツ(嘘言え)!」
「この表紙、サルマタはいちょらんし、ここ……」
様々な予兆を指摘する。
そして二人で読み、間違いなく最終回であることを確認した。
二人して泣いた。
夜も、布団に入ってから泣いた。
今思えば、まだ小学5年の夏である。
挫折しかない人生を生きる「おいどん」の、いったい何に反応していたのだろう。
それからしばらくして『月刊少年マガジン』が復刊されてこれも買うようになり、そこに小さな記事を見つけた。
松本零士が監督を務めるテレビアニメが制作される、と言うもので、私は心躍らせて放映の日を待ち続けた。
これが『宇宙戦艦ヤマト』、後に一大ブームを巻き起こすのだが、当時、観ていたのはクラスで私一人だった。
今観ても素晴らしい内容なのだが、視聴率が上がらず、商業的には失敗した。
再放送でブームに火がつき、誰も彼も最初の放送で観たと言い始めたのだが、嘘である。
皆、裏番組の『SFドラマ猿の軍団』を観ていたはず。
あなたたちが観ていたのは再放送です。
それにしても、そうか……息子も、もうそんな歳か。
色々選ばないといけないな。
確かに『怖い話』は怖すぎたわ。
画面からノスタル爺の「抱けえっ!! 抱けえっ!!」が聞こえてくるようだ。
2017年10月06日
10/21土曜ムラマツリサイタルホール新大阪
クラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」
出演者は、お初…森井美貴、徳兵衛…谷浩一郎、お鈴…陰山裕美子、九平次…砂田麗央、稗田阿礼…浅川文恵、お粧…勝井粧子、ピアニスト…白藤望
ぴあ(セブンイレブン、サークルKサンクスにて購入) コード…337310
お問い合わせは夙川座0798558297
shukugawaza@gmail.com
入場料は、御一人様5500円(前売り5000円)
座友会メンバー4500円

出演者は、お初…森井美貴、徳兵衛…谷浩一郎、お鈴…陰山裕美子、九平次…砂田麗央、稗田阿礼…浅川文恵、お粧…勝井粧子、ピアニスト…白藤望
ぴあ(セブンイレブン、サークルKサンクスにて購入) コード…337310
お問い合わせは夙川座0798558297
shukugawaza@gmail.com
入場料は、御一人様5500円(前売り5000円)
座友会メンバー4500円

2017年10月06日
伊佐山紫文82
カズオ・イシグロのノーベル賞受賞は当然だと思うし、いちファンとして素直に喜びたい。
けれど思うのは、文学に賞って必要か?
新人賞は分かる。
デビューの場を作ってあげないと世に出る機会がないからね。
自然科学系の賞もあって良いと思う。
客観的に今の科学水準を示す指標にはなるだろうから。
と言うか、今の学会がどのようなパラダイムを公的に採用しているかを公表しているようなものだから、存在意義はあると思う。
けれど、文学となると……
そもそも現代人にとって、文学なんて嗜好品でしょ。
あの作家は下らんが好き、この作家は立派だけど読む気にもならん。
なんてことが平気で許される世界だし、だからこその文学ではないか。
どこかの機関が権威づけるようなもんじゃないと思う。
そもそも今回のノーベル文学賞は政治的な臭いが強すぎる。
昨年のボブ・ディラン受賞で巻き起こった、あまりにも政治的すぎるという批判をかわす狙いがあったのではないか。
あまりにも左派に傾きすぎた選考基準という批判をかわすためには、政治的発言をほとんどしない、それでいて人気のある作家を選ばなければならない。
うってつけじゃん、カズオ・イシグロ!
『浮世の画家』では軍国日本を批判したし、『日の名残り』ではナチ協力の貴族を揶揄ったしで、ノーベル文学賞のアカデミック左派的な基準は満たしている。
『充たされざる者』のような難解でカフカ的な前衛的な作品も書いてるしね。
そうそう、生命の軽重の根幹に迫る傑作『わたしを離さないで』も忘れてはならない。
これは世界的ベストセラーになった。
こういうものもしっかり見てるというアピールにもなる。
ものすごくうがった見方だとは百も承知、今回のノーベル文学賞は政治的なものだと断言する。
その上で、カズオ・イシグロのような「子供」の文学が受賞したこと、成熟ではなく、未熟の文学がその価値を認められたことは評価したい。
同じ英語圏なら、私は絶対にアメリカのコーマック・マッカーシーが受賞するべきだったと思っているが、これは、これまでの選考基準、成熟した大人が主人公の、ガッツリした闘いの物語が評価されてきた歴史があるからである。
もし、そうじゃなく、子供の、よわよわとした、行きつ戻りつの、何とも言えぬ叙情が評価されるなら、また基準も変わってくる。
カズオ・イシグロの文学は、主人ではなく召使いの、主人公ではなく脇役の、成功者ではなく失敗者の、苦い記憶を基礎に据える。
成熟した大人ではなく、子供、あるいは成熟できない大人の文学なのである。
つまり政治からは最も遠い。
たとえそれが選ばれた理由だとしても、いちファンとしては素直に喜びたい。
けれど思うのは、文学に賞って必要か?
新人賞は分かる。
デビューの場を作ってあげないと世に出る機会がないからね。
自然科学系の賞もあって良いと思う。
客観的に今の科学水準を示す指標にはなるだろうから。
と言うか、今の学会がどのようなパラダイムを公的に採用しているかを公表しているようなものだから、存在意義はあると思う。
けれど、文学となると……
そもそも現代人にとって、文学なんて嗜好品でしょ。
あの作家は下らんが好き、この作家は立派だけど読む気にもならん。
なんてことが平気で許される世界だし、だからこその文学ではないか。
どこかの機関が権威づけるようなもんじゃないと思う。
そもそも今回のノーベル文学賞は政治的な臭いが強すぎる。
昨年のボブ・ディラン受賞で巻き起こった、あまりにも政治的すぎるという批判をかわす狙いがあったのではないか。
あまりにも左派に傾きすぎた選考基準という批判をかわすためには、政治的発言をほとんどしない、それでいて人気のある作家を選ばなければならない。
うってつけじゃん、カズオ・イシグロ!
『浮世の画家』では軍国日本を批判したし、『日の名残り』ではナチ協力の貴族を揶揄ったしで、ノーベル文学賞のアカデミック左派的な基準は満たしている。
『充たされざる者』のような難解でカフカ的な前衛的な作品も書いてるしね。
そうそう、生命の軽重の根幹に迫る傑作『わたしを離さないで』も忘れてはならない。
これは世界的ベストセラーになった。
こういうものもしっかり見てるというアピールにもなる。
ものすごくうがった見方だとは百も承知、今回のノーベル文学賞は政治的なものだと断言する。
その上で、カズオ・イシグロのような「子供」の文学が受賞したこと、成熟ではなく、未熟の文学がその価値を認められたことは評価したい。
同じ英語圏なら、私は絶対にアメリカのコーマック・マッカーシーが受賞するべきだったと思っているが、これは、これまでの選考基準、成熟した大人が主人公の、ガッツリした闘いの物語が評価されてきた歴史があるからである。
もし、そうじゃなく、子供の、よわよわとした、行きつ戻りつの、何とも言えぬ叙情が評価されるなら、また基準も変わってくる。
カズオ・イシグロの文学は、主人ではなく召使いの、主人公ではなく脇役の、成功者ではなく失敗者の、苦い記憶を基礎に据える。
成熟した大人ではなく、子供、あるいは成熟できない大人の文学なのである。
つまり政治からは最も遠い。
たとえそれが選ばれた理由だとしても、いちファンとしては素直に喜びたい。
2017年10月06日
伊佐山紫文81
夙川座10月21日公演『恋の名残 新説・曽根崎心中』の練習が佳境に入ってきた。
昨年4月に神戸酒心館でやったものとはヴァージョンが違い、歌手に強いる台詞と演技も相当に過酷なものとなっているのだが、そこはもう、それぞれの努力で役に入って来ている。
役を演じると言う意味では、原作の『曽根崎心中』は相当に難しい演目だと思う。
そもそも、なぜお初が一緒に死ぬのか、原作だけではその理由がわからない。
徳兵衛の金銭的破滅はよく分かるし、そこに至る過程は事細かに描かれている。
でも、なぜ、それに随って、お初も死んでしまうのか。
原作だけではサッパリ分からない。
今回の「恋の名残」では、オリジナルのキャラクター「お鈴」を作り、お初との会話の中で、心中に至る宗教的心理的な過程を丁寧に描いたつもりである。
こういう作業を通じて痛感するのは、日本と西洋の作劇法の違い、何というか、省略の美と装飾の美、あるいは寡黙の力と饒舌の力、語られぬものに語らすか、語るものが徹底的に語るか、といった、根底的な差異である。
明治期の精神改良運動、近代的自我を確立せよと言った運動が真っ先に手を付けたのが演劇だったのもよく分かる。
西洋の近代演劇の基準で考えれば、歌舞伎だの文楽だのは説明足らずの意味不明で支離滅裂な「何か」に過ぎない。
こんなものを観ていては「近代的自我」が育つわけがない、と。
まずは演劇を改良しないといけない、と。
名目は上流階級も観ていられる上質の演劇を目指す、と言うことだったが、制作するインテリの側からすれば、それはまさに精神改良運動、近代的自我を確立するための運動に他ならなかった。
それでは彼等、明治のインテリたちの考えた近代的自我とは何だったのか。
私が思うに、それは、言葉の狭い意味での弁証法的な自我である。
つまり対話を通じて真理に至るという、プラトンからヘーゲルへと綿々と受け継がれて来た、西洋哲学の伝統に沿う自我である。
A(テーゼ)という価値観とB(アンチテーゼ)という価値観がぶつかり合い、どちらかが勝ち、あるいはどちらも敗北し(アウフヘーベン)、あるいはCという新しい価値観(ジンテーゼ)が生まれる。
そういう、価値同士のドラマが西洋演劇の根底にはある。
そこではそれぞれの価値観を登場人物がぶつけ合い、言い負かし、あるいは言い負けて、殺し殺され、泣き笑い、生き残った者はひたすら嘆き、あるいは勝ち誇る。
その価値の担い手が近代的自我であり、個性であり、キャラクターである。
価値の担い手である近代的自我同士のせめぎ合いこそが西洋演劇のドラマツルギー(作劇法)に他ならぬ。
これに対し、日本の演劇は「勧善懲悪」として批判された。
そこには価値観のせめぎ合いがない。
良いものは二枚目として固定化しており、悪役は見るからに悪い。
自分自身の価値と個性を担った近代的自我がない。
だから結論は最初から分かっている。
善は勝ち、悪は滅ぶ。
これのどこがドラマなんだ、というわけだ。
西洋的なドラマを見慣れてしまった我々には、日本の歌舞伎や文楽もそれなりに面白く、全く別物として鑑賞できるが、明治期のインテリたちの目にはただただ恥ずかしい、遅れた、幼稚なものに見えただろうことは容易に想像できる。
今回、と言うか、前回の夙川座公演『神戸事件始末 瀧善三郎の最期』でも、私は全面的に西洋的な作劇法に依っている。
せめぎ合う価値観は「生」と「死」である。
前回は「切腹」、今回は「心中」。
原作とは異なるラストに賛否両論、して欲しいと、私の近代的自我は願っているのだが。
昨年4月に神戸酒心館でやったものとはヴァージョンが違い、歌手に強いる台詞と演技も相当に過酷なものとなっているのだが、そこはもう、それぞれの努力で役に入って来ている。
役を演じると言う意味では、原作の『曽根崎心中』は相当に難しい演目だと思う。
そもそも、なぜお初が一緒に死ぬのか、原作だけではその理由がわからない。
徳兵衛の金銭的破滅はよく分かるし、そこに至る過程は事細かに描かれている。
でも、なぜ、それに随って、お初も死んでしまうのか。
原作だけではサッパリ分からない。
今回の「恋の名残」では、オリジナルのキャラクター「お鈴」を作り、お初との会話の中で、心中に至る宗教的心理的な過程を丁寧に描いたつもりである。
こういう作業を通じて痛感するのは、日本と西洋の作劇法の違い、何というか、省略の美と装飾の美、あるいは寡黙の力と饒舌の力、語られぬものに語らすか、語るものが徹底的に語るか、といった、根底的な差異である。
明治期の精神改良運動、近代的自我を確立せよと言った運動が真っ先に手を付けたのが演劇だったのもよく分かる。
西洋の近代演劇の基準で考えれば、歌舞伎だの文楽だのは説明足らずの意味不明で支離滅裂な「何か」に過ぎない。
こんなものを観ていては「近代的自我」が育つわけがない、と。
まずは演劇を改良しないといけない、と。
名目は上流階級も観ていられる上質の演劇を目指す、と言うことだったが、制作するインテリの側からすれば、それはまさに精神改良運動、近代的自我を確立するための運動に他ならなかった。
それでは彼等、明治のインテリたちの考えた近代的自我とは何だったのか。
私が思うに、それは、言葉の狭い意味での弁証法的な自我である。
つまり対話を通じて真理に至るという、プラトンからヘーゲルへと綿々と受け継がれて来た、西洋哲学の伝統に沿う自我である。
A(テーゼ)という価値観とB(アンチテーゼ)という価値観がぶつかり合い、どちらかが勝ち、あるいはどちらも敗北し(アウフヘーベン)、あるいはCという新しい価値観(ジンテーゼ)が生まれる。
そういう、価値同士のドラマが西洋演劇の根底にはある。
そこではそれぞれの価値観を登場人物がぶつけ合い、言い負かし、あるいは言い負けて、殺し殺され、泣き笑い、生き残った者はひたすら嘆き、あるいは勝ち誇る。
その価値の担い手が近代的自我であり、個性であり、キャラクターである。
価値の担い手である近代的自我同士のせめぎ合いこそが西洋演劇のドラマツルギー(作劇法)に他ならぬ。
これに対し、日本の演劇は「勧善懲悪」として批判された。
そこには価値観のせめぎ合いがない。
良いものは二枚目として固定化しており、悪役は見るからに悪い。
自分自身の価値と個性を担った近代的自我がない。
だから結論は最初から分かっている。
善は勝ち、悪は滅ぶ。
これのどこがドラマなんだ、というわけだ。
西洋的なドラマを見慣れてしまった我々には、日本の歌舞伎や文楽もそれなりに面白く、全く別物として鑑賞できるが、明治期のインテリたちの目にはただただ恥ずかしい、遅れた、幼稚なものに見えただろうことは容易に想像できる。
今回、と言うか、前回の夙川座公演『神戸事件始末 瀧善三郎の最期』でも、私は全面的に西洋的な作劇法に依っている。
せめぎ合う価値観は「生」と「死」である。
前回は「切腹」、今回は「心中」。
原作とは異なるラストに賛否両論、して欲しいと、私の近代的自我は願っているのだが。
2017年10月05日
伊佐山紫文80
唱歌の「故郷」(作詞 高野辰之 作曲 岡野貞一)と言えば誰もが知る名曲で、もちろん私も大好きなのだが、そろそろ3番の歌詞に抵抗を感じるようになって来た。
志を果して
いつの日にか帰らん
山は青き故郷
水は清よき故郷
果たすような志があるのか、あったのかどうか。
それにもう、故郷は帰る場所ではなくなった。
多くの人は異郷に働き、異郷に果てることがわかっている。
志を果たし、故郷に戻って最期の日々を過ごすのは理想かも知れないが、実際には難しいというのが現実だろう。
で、関西日田会という、関西の日田出身者の団体があって、そこで「故郷」を歌うというので、4番を作った。
日田の家を離れて
歩む道も遙かに
この身はここに朽ちるとも
魂(たま)は帰る故郷
気持ちとしてはこんなものだと思う。
もう帰れはしないけれども、この世を去った後、魂は故郷に帰っていくだろう、と。
この後、浅川社長の同郷会のために別の歌を作ったとき、同時に4番を少し変えて、
岩見沢を離れて
歩む道も遙かに
この身はここに朽ちるとも
魂は帰る故郷
にして録音し、CDを作って配った。
同郷会で歌ったら、みんなが泣く泣く。
で、もっと一般的な歌詞にしようと言うことにもなった。
それで決定版が、
遠く家を離れて
歩む道も遙かに
この身はここに朽ちるとも
魂は帰る故郷
異郷にある人間の気持ちとしてはこんなものだと思う。
志を果して
いつの日にか帰らん
山は青き故郷
水は清よき故郷
果たすような志があるのか、あったのかどうか。
それにもう、故郷は帰る場所ではなくなった。
多くの人は異郷に働き、異郷に果てることがわかっている。
志を果たし、故郷に戻って最期の日々を過ごすのは理想かも知れないが、実際には難しいというのが現実だろう。
で、関西日田会という、関西の日田出身者の団体があって、そこで「故郷」を歌うというので、4番を作った。
日田の家を離れて
歩む道も遙かに
この身はここに朽ちるとも
魂(たま)は帰る故郷
気持ちとしてはこんなものだと思う。
もう帰れはしないけれども、この世を去った後、魂は故郷に帰っていくだろう、と。
この後、浅川社長の同郷会のために別の歌を作ったとき、同時に4番を少し変えて、
岩見沢を離れて
歩む道も遙かに
この身はここに朽ちるとも
魂は帰る故郷
にして録音し、CDを作って配った。
同郷会で歌ったら、みんなが泣く泣く。
で、もっと一般的な歌詞にしようと言うことにもなった。
それで決定版が、
遠く家を離れて
歩む道も遙かに
この身はここに朽ちるとも
魂は帰る故郷
異郷にある人間の気持ちとしてはこんなものだと思う。
2017年10月04日
伊佐山紫文79
鶏の唐揚げ、と関西では言うし、これが一般的な呼び名なんだろうが、大分では同じようなものを鶏のテンプラ、「鶏天」と言う。
中津のものが有名だが、日田にもある。
学生時代を過ごした松山では同じような鶏の揚げ物を「せんざんき」と呼んでいて、最初は、独特の甘い、そして濃い味付けに戸惑った。
北海道でも同じような料理を「ザンギ」と呼ぶらしい。
鶏の揚げ物など、名こそ違え、どこにもあるのだろうが、日田でしか見たことのない鶏料理がある。
それは鶏の足で、まさに足、爪のついた足である。
これを甘辛く煮たものが店頭で売られているのである。
子供たちはこの鶏の足を買い、おやつにする。
足の皮を歯でこそげ取り、うま味の凝縮した鶏の皮を味わうのである。
40年前に1本5円かそこらだった。
鶏の頭、というのもあった。
最近は見ないが、40年前は普通に日田の鳥肉屋で売られていた。
ウチではこれを茹でて飼い犬のエサにしていた。
二頭いた犬のうち、高級な秋田犬のエサである。
そのうち異変が起きた。
秋田犬のお腹が膨らみ始め、コブとなり、突出した。
明らかに、何か腫瘍のようなものが出来ていた。
触っても痛がらないから、そのままにしていたが、気持ちの良いものではない。
もう一頭の、残飯を食わせていた雑種の方は何にも変化はない。
数年して秋田犬が死んだころ、鶏の頭が店頭から消えた。
当時、黙示録的世界観にとらわれていた私は、鶏の頭に何か良くない物質が凝縮されていて、そのせいで犬に腫瘍が出来たのだと考えた。
そして毒があるという事実を隠蔽するため、どこかの誰かが鶏の頭を店頭から消したのだ。
とまあ、こんな幼稚な陰謀説をひねり出した。
鶏肉はアブナイ。
頭と同じように、その他の部位にも、何やら腫瘍を作るような毒が含まれているに違いない……
嗤うべき妄念としか言いようがない。
その後、環境問題を扱うジャーナリストとして取材を進めていて、ある大学教授、それもその道の権威の教授が、まことしやかに、
「知ってますか? 最近では四本足のニワトリが卵を産んでるんですよ。みんなで隠してますけどね」
ハァ?
もちろん、あり得ない話である。
この教授は生物学が専攻なのに、こういう都市伝説みたいな妄説を堂々と開陳する。
環境問題を取材していると、こういう「専門家」ばかりに出会う。
それも嫌になって、環境問題からは撤退した。
ちなみに鶏の唐揚げは息子の大好物、夏の暑い時期でなければ週一で食卓に上る。
息子は夏の間も食べたいとせっつくが、冷房なしの我が家で夏の揚げ物は辛すぎる。
鶏の胸肉は10%の食塩水に前日から漬け込み、水でといた米粉にくぐらせて揚げる。
冷めても旨い。
中津のものが有名だが、日田にもある。
学生時代を過ごした松山では同じような鶏の揚げ物を「せんざんき」と呼んでいて、最初は、独特の甘い、そして濃い味付けに戸惑った。
北海道でも同じような料理を「ザンギ」と呼ぶらしい。
鶏の揚げ物など、名こそ違え、どこにもあるのだろうが、日田でしか見たことのない鶏料理がある。
それは鶏の足で、まさに足、爪のついた足である。
これを甘辛く煮たものが店頭で売られているのである。
子供たちはこの鶏の足を買い、おやつにする。
足の皮を歯でこそげ取り、うま味の凝縮した鶏の皮を味わうのである。
40年前に1本5円かそこらだった。
鶏の頭、というのもあった。
最近は見ないが、40年前は普通に日田の鳥肉屋で売られていた。
ウチではこれを茹でて飼い犬のエサにしていた。
二頭いた犬のうち、高級な秋田犬のエサである。
そのうち異変が起きた。
秋田犬のお腹が膨らみ始め、コブとなり、突出した。
明らかに、何か腫瘍のようなものが出来ていた。
触っても痛がらないから、そのままにしていたが、気持ちの良いものではない。
もう一頭の、残飯を食わせていた雑種の方は何にも変化はない。
数年して秋田犬が死んだころ、鶏の頭が店頭から消えた。
当時、黙示録的世界観にとらわれていた私は、鶏の頭に何か良くない物質が凝縮されていて、そのせいで犬に腫瘍が出来たのだと考えた。
そして毒があるという事実を隠蔽するため、どこかの誰かが鶏の頭を店頭から消したのだ。
とまあ、こんな幼稚な陰謀説をひねり出した。
鶏肉はアブナイ。
頭と同じように、その他の部位にも、何やら腫瘍を作るような毒が含まれているに違いない……
嗤うべき妄念としか言いようがない。
その後、環境問題を扱うジャーナリストとして取材を進めていて、ある大学教授、それもその道の権威の教授が、まことしやかに、
「知ってますか? 最近では四本足のニワトリが卵を産んでるんですよ。みんなで隠してますけどね」
ハァ?
もちろん、あり得ない話である。
この教授は生物学が専攻なのに、こういう都市伝説みたいな妄説を堂々と開陳する。
環境問題を取材していると、こういう「専門家」ばかりに出会う。
それも嫌になって、環境問題からは撤退した。
ちなみに鶏の唐揚げは息子の大好物、夏の暑い時期でなければ週一で食卓に上る。
息子は夏の間も食べたいとせっつくが、冷房なしの我が家で夏の揚げ物は辛すぎる。
鶏の胸肉は10%の食塩水に前日から漬け込み、水でといた米粉にくぐらせて揚げる。
冷めても旨い。
2017年10月03日
伊佐山紫文78
日本にはユダヤ教やキリスト教やイスラム教のような唯一神はいない。
だからといって無信仰ではないことは、正月やお盆がくればわかる。
神や仏はそこらじゅうにいる。
そして、そこらじゅうにいる神や仏を探すのが日本の「詩」なのである。
神や仏を探す、その姿勢は「情景描写」として詩の上に現れる。
たとえば、
古池や蛙飛びこむ水の音
芭蕉の最も知られた句であるが、ここには情景描写しかない。
苦悩であるとか、神への渇仰であるとか、そういう、西洋の詩にあるような「内面性」を全く欠く。
こういうところから桑原武夫の「第二芸術論」などが生まれて来たのだろうが、ナンセンスも甚だしい。
ただし、白状すれば、桑原の『第二芸術論』(講談社学術文庫)は学生時代、私の愛読書であり、俳句では現代人の人生は描けない、という論旨に一定の説得力があったのは事実である。
人生を描くのが芸術なのかどうか、その芸術に第一や第二があるのか、それはそれとして、もし神や仏を探し求めるのが日本の詩だという私の説が正しければ、この芭蕉の句はまさに詩の中の詩としなければならないだろう。
ここでは「死」と「生」が架橋されており、まさに神や仏が描かれているのである。
細かく見ていこう。
「古池」とは、もうすっかり忘れ去られ、うち捨てられた死んだ池である。
生きている池ならば、ただの「池」ですむ。
そうではない、誰も関心を払わないような死んだ「古池」。
この死の世界に、蛙が飛び込む。
春の季語である「蛙」が死の世界である「古池」に「飛びこ」んで、「水の音」を立てる。
芭蕉はここに「死」の冬から「生」の春への架橋を聴く。
「死」から「生」が生じる。
まさに、神や仏の世界である。
神や仏を、自らの内面にではなく、外界に探す。
これが「情景描写」として現れ、ポエジーをなす。
日本人は情景を描くことで神や仏を探し、安らぎを得る。
たとえば『古今』『新古今』のほとんどの歌は「情景描写」で成立しており、そうではない歌を探すのが大変な程である。
「情景描写」こそ、日本のポエジーの本質なのである。
ところが、戦後、現代詩はこれを否定したところから出発した。
それで自滅したとも言えるのだが、詩ではなく、歌詞を見たとき、状況は一変する。
特に演歌など、日本的な歌詞には情景描写が溢れている。
というより、情景描写がなければ歌にはならない。
JASRACが恐ろしいので具体例は差し控えるが。
う
だからといって無信仰ではないことは、正月やお盆がくればわかる。
神や仏はそこらじゅうにいる。
そして、そこらじゅうにいる神や仏を探すのが日本の「詩」なのである。
神や仏を探す、その姿勢は「情景描写」として詩の上に現れる。
たとえば、
古池や蛙飛びこむ水の音
芭蕉の最も知られた句であるが、ここには情景描写しかない。
苦悩であるとか、神への渇仰であるとか、そういう、西洋の詩にあるような「内面性」を全く欠く。
こういうところから桑原武夫の「第二芸術論」などが生まれて来たのだろうが、ナンセンスも甚だしい。
ただし、白状すれば、桑原の『第二芸術論』(講談社学術文庫)は学生時代、私の愛読書であり、俳句では現代人の人生は描けない、という論旨に一定の説得力があったのは事実である。
人生を描くのが芸術なのかどうか、その芸術に第一や第二があるのか、それはそれとして、もし神や仏を探し求めるのが日本の詩だという私の説が正しければ、この芭蕉の句はまさに詩の中の詩としなければならないだろう。
ここでは「死」と「生」が架橋されており、まさに神や仏が描かれているのである。
細かく見ていこう。
「古池」とは、もうすっかり忘れ去られ、うち捨てられた死んだ池である。
生きている池ならば、ただの「池」ですむ。
そうではない、誰も関心を払わないような死んだ「古池」。
この死の世界に、蛙が飛び込む。
春の季語である「蛙」が死の世界である「古池」に「飛びこ」んで、「水の音」を立てる。
芭蕉はここに「死」の冬から「生」の春への架橋を聴く。
「死」から「生」が生じる。
まさに、神や仏の世界である。
神や仏を、自らの内面にではなく、外界に探す。
これが「情景描写」として現れ、ポエジーをなす。
日本人は情景を描くことで神や仏を探し、安らぎを得る。
たとえば『古今』『新古今』のほとんどの歌は「情景描写」で成立しており、そうではない歌を探すのが大変な程である。
「情景描写」こそ、日本のポエジーの本質なのである。
ところが、戦後、現代詩はこれを否定したところから出発した。
それで自滅したとも言えるのだが、詩ではなく、歌詞を見たとき、状況は一変する。
特に演歌など、日本的な歌詞には情景描写が溢れている。
というより、情景描写がなければ歌にはならない。
JASRACが恐ろしいので具体例は差し控えるが。
う
2017年10月02日
伊佐山紫文77
実家には父の集めたクラシックのレコードが百枚以上あった。
これのほとんどは40年以上前のもので、よくもまあ、公務員の初任給が5万円程度だった時代に、一枚数千円もするものをこれだけ集めたものだ。
ただ、そのコレクションを見てみると、名曲名演主義というか、何冊かのガイドブックに忠実に、まるで視聴覚室のアーカイヴを作るかのように集めてきたことが分かる。
コレクションに偏りがない。
ワルターとカラヤンは枚数としていちばん多いが、これはセット物で買っているからで、バラではそれほどでもない。
若い父が一枚一枚、ガイドブックを見比べながら、おそらく子供たちのことも考えて、吟味して選ぶ姿が思い浮かぶ。
父の死後、レコードを整理しながら、何か暖かいものがこみ上げてきたものだ。
私は学生時代には金銭的余裕がなく、金が入れば即、書籍に消え、結局、一枚もレコードを買うことはなかった。
角川の社員になれと迫られていた28年前の夏、カラヤンが死んで、追悼CDボックスがドイツ・グラモフォンから出た。
60年代70年代の全盛期の名録音を集めたもので、2万円程度、確か、初任給で買った。
懐かしくて、繰り返し聴いた。
これでクラシック愛がぶり返し、しかも金銭的には余裕があるものだから、ガイドブックなどお構いなし、気の向くままにガツガツCDを買いまくった。
ちょうどソ連が崩壊した頃で、旧ソビエト軍が接収していたフルトヴェングラーの戦争中の名演が「ベルリンライブ」と銘打たれ続々とCDとなって店頭に並んだ。
今はなき、懐かしき「ワルツ堂」。
当時フルトヴェングラーにハマっていた私は、もちろん、全部買った。
戦争中というと、まるで爆撃の中、悲惨な状況の中での悲壮な演奏を想像するかもしれないが、それは違う。
ドイツ第三帝国の負け戦さが確定したのは最後の1年少しのことで、それまでは連戦連勝、破竹の勢いでヨーロッパを席巻していた。
演奏に勢いのないはずがない。
フルトヴェングラーと言えば戦後の演奏を讃える一方で戦中の活躍には沈黙するのが一般的だが、私の聴くところ、特に戦後のベートーヴェンなど、戦中と比べれば気の抜けたぬるいビールでしかない。
1942年ヒトラー誕生日前夜祭の第九を聴けば、1951年のバイロイト盤がなんとトロ臭く感じられることか。
バイロイト盤はマイク位置の問題か、やたらとティンパニが強く、まるでティンパニ協奏曲に聞こえ、これだけでもかなりの瑕疵である。
それに比べ、ヒトラーの誕生日を心から祝うフルトヴェングラーと楽員たちの「喜びの歌」!
いちど聴いてみてご覧なさい。
「Heil Hitler!」の一言も叫びたくなるから。
その他、3番も、戦後のどれより、戦前のいわゆる「ウラニアのエロイカ」の方が優れているし、5番、6番、7番もそうだと思う。
特に5番の「ベルリンライブ」盤、これは世評高い1947年盤より緊張感に満ち、第4楽章の凱旋行進では沿道から手を千切れんばかりに振りたくなる。
「Sieg Heil!Sieg Heil!」
それに忘れてはならないのがシューベルトの「ザ・グレート」。
これも戦争中の「ベルリンライブ」盤の方が戦後のスタジオ録音盤より遙かに優れ、何より第1楽章の猛烈なアッチェレランドに、どこか他の世界に連れて行かれそうになる。
それからシューマンのピアノ協奏曲。
ピアノに難はあるが、伴奏が圧倒的に素晴らしい。
透明感のまるでない、曇った音のカタマリがいきなり頭にガツンと来て、あまりの衝撃に死にそうになる。
このような名演の同時代、ヨーロッパは悲惨な状況にあったのだと思うと言葉をなくすが、芸術とはそういうものだ。
ナポレオンの惨禍なくしてベートーヴェンの「英雄」がなかったように、スターリンがいなければショスタコーヴィチもムラヴィンスキーもいなかった。
東独の恐怖政治がなければケーゲルも、スウィートナーも、ザンデルリンクも、そしてマズアやペーター・シュライヤーが活躍することなく、膨大なシャルプラッテンのアーカイヴが成立することはなかった。
無論、逆の、膨大な数の亡命音楽家たち、シェーンベルク、ワルター、セル、ショルティ……
芸術は政治的危機や独裁との相性がとても良い。
これはどうしようもない事実であり、音楽を政治的に聴いてはならない所以でもある。
これのほとんどは40年以上前のもので、よくもまあ、公務員の初任給が5万円程度だった時代に、一枚数千円もするものをこれだけ集めたものだ。
ただ、そのコレクションを見てみると、名曲名演主義というか、何冊かのガイドブックに忠実に、まるで視聴覚室のアーカイヴを作るかのように集めてきたことが分かる。
コレクションに偏りがない。
ワルターとカラヤンは枚数としていちばん多いが、これはセット物で買っているからで、バラではそれほどでもない。
若い父が一枚一枚、ガイドブックを見比べながら、おそらく子供たちのことも考えて、吟味して選ぶ姿が思い浮かぶ。
父の死後、レコードを整理しながら、何か暖かいものがこみ上げてきたものだ。
私は学生時代には金銭的余裕がなく、金が入れば即、書籍に消え、結局、一枚もレコードを買うことはなかった。
角川の社員になれと迫られていた28年前の夏、カラヤンが死んで、追悼CDボックスがドイツ・グラモフォンから出た。
60年代70年代の全盛期の名録音を集めたもので、2万円程度、確か、初任給で買った。
懐かしくて、繰り返し聴いた。
これでクラシック愛がぶり返し、しかも金銭的には余裕があるものだから、ガイドブックなどお構いなし、気の向くままにガツガツCDを買いまくった。
ちょうどソ連が崩壊した頃で、旧ソビエト軍が接収していたフルトヴェングラーの戦争中の名演が「ベルリンライブ」と銘打たれ続々とCDとなって店頭に並んだ。
今はなき、懐かしき「ワルツ堂」。
当時フルトヴェングラーにハマっていた私は、もちろん、全部買った。
戦争中というと、まるで爆撃の中、悲惨な状況の中での悲壮な演奏を想像するかもしれないが、それは違う。
ドイツ第三帝国の負け戦さが確定したのは最後の1年少しのことで、それまでは連戦連勝、破竹の勢いでヨーロッパを席巻していた。
演奏に勢いのないはずがない。
フルトヴェングラーと言えば戦後の演奏を讃える一方で戦中の活躍には沈黙するのが一般的だが、私の聴くところ、特に戦後のベートーヴェンなど、戦中と比べれば気の抜けたぬるいビールでしかない。
1942年ヒトラー誕生日前夜祭の第九を聴けば、1951年のバイロイト盤がなんとトロ臭く感じられることか。
バイロイト盤はマイク位置の問題か、やたらとティンパニが強く、まるでティンパニ協奏曲に聞こえ、これだけでもかなりの瑕疵である。
それに比べ、ヒトラーの誕生日を心から祝うフルトヴェングラーと楽員たちの「喜びの歌」!
いちど聴いてみてご覧なさい。
「Heil Hitler!」の一言も叫びたくなるから。
その他、3番も、戦後のどれより、戦前のいわゆる「ウラニアのエロイカ」の方が優れているし、5番、6番、7番もそうだと思う。
特に5番の「ベルリンライブ」盤、これは世評高い1947年盤より緊張感に満ち、第4楽章の凱旋行進では沿道から手を千切れんばかりに振りたくなる。
「Sieg Heil!Sieg Heil!」
それに忘れてはならないのがシューベルトの「ザ・グレート」。
これも戦争中の「ベルリンライブ」盤の方が戦後のスタジオ録音盤より遙かに優れ、何より第1楽章の猛烈なアッチェレランドに、どこか他の世界に連れて行かれそうになる。
それからシューマンのピアノ協奏曲。
ピアノに難はあるが、伴奏が圧倒的に素晴らしい。
透明感のまるでない、曇った音のカタマリがいきなり頭にガツンと来て、あまりの衝撃に死にそうになる。
このような名演の同時代、ヨーロッパは悲惨な状況にあったのだと思うと言葉をなくすが、芸術とはそういうものだ。
ナポレオンの惨禍なくしてベートーヴェンの「英雄」がなかったように、スターリンがいなければショスタコーヴィチもムラヴィンスキーもいなかった。
東独の恐怖政治がなければケーゲルも、スウィートナーも、ザンデルリンクも、そしてマズアやペーター・シュライヤーが活躍することなく、膨大なシャルプラッテンのアーカイヴが成立することはなかった。
無論、逆の、膨大な数の亡命音楽家たち、シェーンベルク、ワルター、セル、ショルティ……
芸術は政治的危機や独裁との相性がとても良い。
これはどうしようもない事実であり、音楽を政治的に聴いてはならない所以でもある。
2017年10月01日
10/21土曜ムラマツリサイタルホール新大阪
勝井粧子さん 地唄
10/21土曜ムラマツリサイタルホール新大阪でのクラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」に出演します。
チケットお問い合わせは、夙川座
0798-55-8297
ぴあPコード337310
是非お待ちしております。
当道友楽会三代目家元菊武厚詞の長女。6歳より箏を、10歳より三味線を始める。東京藝術大学音楽学部邦楽科箏曲生田流専攻卒業。在学中、常英賞受賞。
2015年坂東玉三郎主演・演出「アマテラス」に出演。
2015年「大阪平成中村座」、2017年「壽初春大歌舞伎」「花形歌舞伎」歌舞伎の黒御簾にて演奏。
現在、当道友楽会、邦楽あんさんぶるグループ ふぁるべ、森の会、みやこ風韻、和楽器集団 東に所属する。
10/21土曜ムラマツリサイタルホール新大阪でのクラシック音楽劇「恋の名残 新説 曽根崎心中」に出演します。
チケットお問い合わせは、夙川座
0798-55-8297
ぴあPコード337310
是非お待ちしております。
当道友楽会三代目家元菊武厚詞の長女。6歳より箏を、10歳より三味線を始める。東京藝術大学音楽学部邦楽科箏曲生田流専攻卒業。在学中、常英賞受賞。
2015年坂東玉三郎主演・演出「アマテラス」に出演。
2015年「大阪平成中村座」、2017年「壽初春大歌舞伎」「花形歌舞伎」歌舞伎の黒御簾にて演奏。
現在、当道友楽会、邦楽あんさんぶるグループ ふぁるべ、森の会、みやこ風韻、和楽器集団 東に所属する。

2017年10月01日
伊佐山紫文76
息子が一人前に食べるようになるまで、ずっと魚ばかりだった。
夕食は刺身やアラの煮物、たまに焼き物。
なぜ肉を食べなくなったのか、理由は色々あって、どれか一つには確定できないが、まあ、当時の私としては「肉なんか、陸の養殖モノ」という意識があったと思う。
つまりは「天然」を是とし「養殖」を非としていたわけで、それにも理由があった。
もう25年以上前、フリーライターとして漁業を取材していた時のことである。
とある市場での競りの場面。
養殖ブリが次々と競り落とされていったその最後、奇妙な光景を目にした。
ほとんどの仲買人が去った後、残ったカゴを競りもなく引き取っていく仲買人がいた。
何だろうとカゴの中身を見ると、骨が奇妙に歪んだ奇形のブリばかり。
これか!
と、その前に取材していた漁業の専門家の話を思い出した。
養殖の魚の中では、一定数、奇形がでる。
そして、その奇形のモノばかりを安く買う業者もいる。
切り身にすればわからないから、奇形魚も市場では同じように流通している。
と、こんな話で、目の当たりにした奇形魚の姿に震え上がり、二度と養殖物は買わなくなった。
過剰な反応と言えば、そうなのだが、私の場合、そうなる伏線があった。
父がまだ酒浸りになる前、趣味は釣りで、よく日田の花月川の光岡橋の下でフナを釣ってきた。
そのフナに、ある時期から異変が起きた。
背骨の曲がりくねった奇形魚が釣れだしたのだ。
「これも奇形……これも奇形……」
と次々と捨てられていく獲物の中に、まともなフナはほとんどいなかった。
しばらくして、近くのバネ工場の廃液に含まれる重金属が原因だと囁かれるようになり、私は恐ろしくて、しばらくその川の近くにも行けなくなった。
この時の原体験が私を環境問題に走らせたと言ってもいい。
で、その原体験が、養殖ブリの奇形魚を見たときに甦ったのである。
今では、この奇形の原因物質である有機スズの使用は禁止されており、その他の薬物も昔に比べればかなり抑えられているという。
そういうことを売りにした養殖モノも出始めている。
けれど、私が取材した80年代後半では、奇形ブリの話など都市伝説のようなもので、一般の人は全く知らなかった。
ジャーナリストたちも、そういう事実があることを知りながら、諸般の事情を推し量った上で報道しなかった。
かく言う私もその一人で、何せ媒体がコープさんの雑誌とあっちゃ、自主規制せざるを得ない。
そのかわりこれからは天然物だけを食わせて貰います、みたいな。
「陸の養殖モノ」たる肉も出来る限り遠慮させて貰います、みたいな。
こうして肉を遠ざけてきたのだが、子供の食欲の前ではそんなことも言ってられない。
ちゃんと飼料を公開しているような肉を、それも出来るだけ安い肉を買い、かさ増し調理して食べさすし、自分でも食べる。
それでも健康に過ごしているから、魚ばっかり食ってりゃいいってものでもないらしい。
夕食は刺身やアラの煮物、たまに焼き物。
なぜ肉を食べなくなったのか、理由は色々あって、どれか一つには確定できないが、まあ、当時の私としては「肉なんか、陸の養殖モノ」という意識があったと思う。
つまりは「天然」を是とし「養殖」を非としていたわけで、それにも理由があった。
もう25年以上前、フリーライターとして漁業を取材していた時のことである。
とある市場での競りの場面。
養殖ブリが次々と競り落とされていったその最後、奇妙な光景を目にした。
ほとんどの仲買人が去った後、残ったカゴを競りもなく引き取っていく仲買人がいた。
何だろうとカゴの中身を見ると、骨が奇妙に歪んだ奇形のブリばかり。
これか!
と、その前に取材していた漁業の専門家の話を思い出した。
養殖の魚の中では、一定数、奇形がでる。
そして、その奇形のモノばかりを安く買う業者もいる。
切り身にすればわからないから、奇形魚も市場では同じように流通している。
と、こんな話で、目の当たりにした奇形魚の姿に震え上がり、二度と養殖物は買わなくなった。
過剰な反応と言えば、そうなのだが、私の場合、そうなる伏線があった。
父がまだ酒浸りになる前、趣味は釣りで、よく日田の花月川の光岡橋の下でフナを釣ってきた。
そのフナに、ある時期から異変が起きた。
背骨の曲がりくねった奇形魚が釣れだしたのだ。
「これも奇形……これも奇形……」
と次々と捨てられていく獲物の中に、まともなフナはほとんどいなかった。
しばらくして、近くのバネ工場の廃液に含まれる重金属が原因だと囁かれるようになり、私は恐ろしくて、しばらくその川の近くにも行けなくなった。
この時の原体験が私を環境問題に走らせたと言ってもいい。
で、その原体験が、養殖ブリの奇形魚を見たときに甦ったのである。
今では、この奇形の原因物質である有機スズの使用は禁止されており、その他の薬物も昔に比べればかなり抑えられているという。
そういうことを売りにした養殖モノも出始めている。
けれど、私が取材した80年代後半では、奇形ブリの話など都市伝説のようなもので、一般の人は全く知らなかった。
ジャーナリストたちも、そういう事実があることを知りながら、諸般の事情を推し量った上で報道しなかった。
かく言う私もその一人で、何せ媒体がコープさんの雑誌とあっちゃ、自主規制せざるを得ない。
そのかわりこれからは天然物だけを食わせて貰います、みたいな。
「陸の養殖モノ」たる肉も出来る限り遠慮させて貰います、みたいな。
こうして肉を遠ざけてきたのだが、子供の食欲の前ではそんなことも言ってられない。
ちゃんと飼料を公開しているような肉を、それも出来るだけ安い肉を買い、かさ増し調理して食べさすし、自分でも食べる。
それでも健康に過ごしているから、魚ばっかり食ってりゃいいってものでもないらしい。
最近の記事
11月21日日曜日大阪で上方ミュージカル! (7/24)
リモート稽古 (7/22)
11月21日(日)大阪にて、舞台「火の鳥 晶子と鉄幹」 (7/22)
茂木山スワン×伊佐山紫文 写真展 (5/5)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/28)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/26)
ヘアサロン「ボザール」の奇跡 (2/25)
yutube配信前、数日の会話です。 (2/25)
初の、zoom芝居配信しました! (2/24)
過去記事
最近のコメント
notebook / 9月16土曜日 コープ神戸公演
岡山新選組の新八参上 / 9月16土曜日 コープ神戸公演
notebook / ムラマツリサイタルホール新・・・
山岸 / 九州水害について
岡山新選組の新八参上 / 港都KOBE芸術祭プレイベント
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
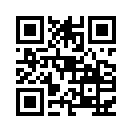
アクセスカウンタ
読者登録
